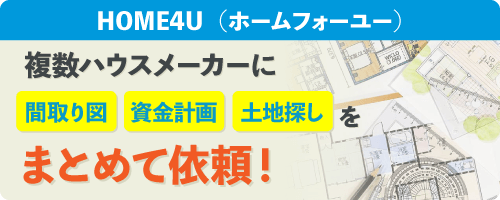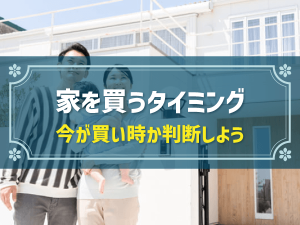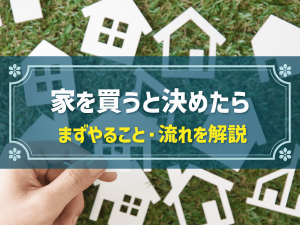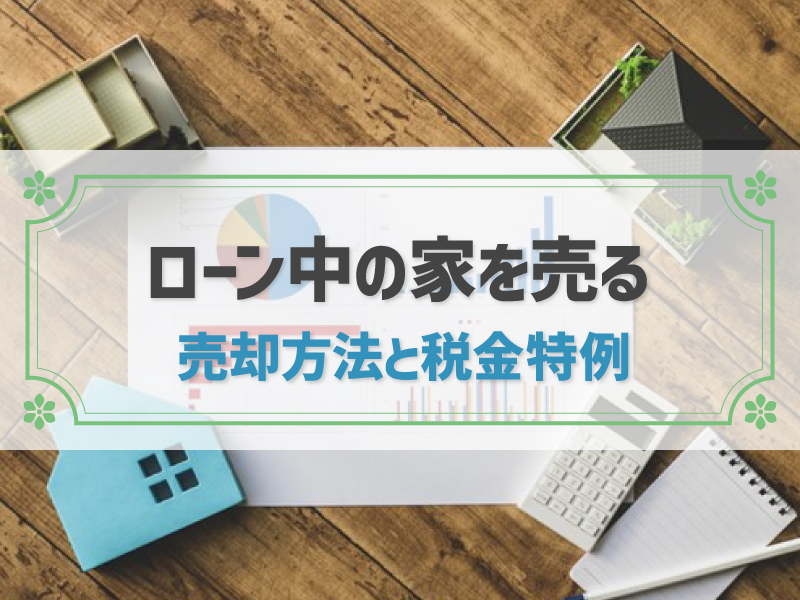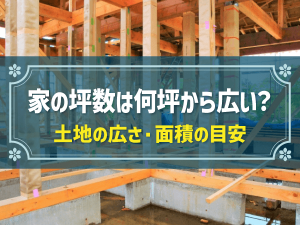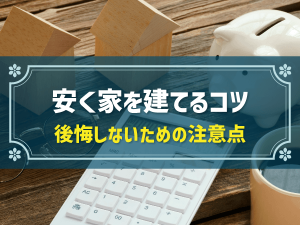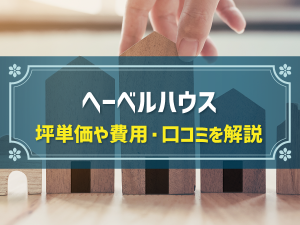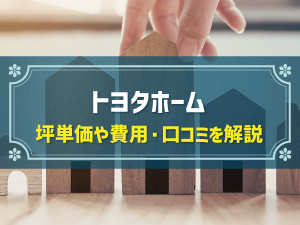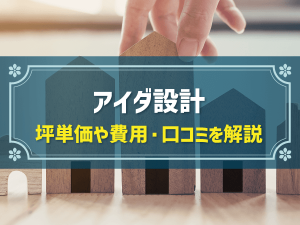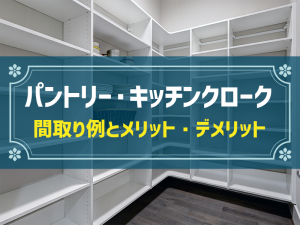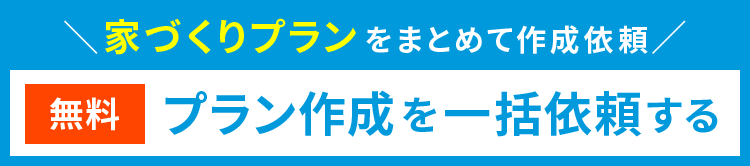この記事は、初めて「家を建てる」ことを検討し始める方向けに、実際に家を建てる「流れ」「期間」といった概要から「検討の仕方」までなるべく簡潔且つ具体的に解説しています。
- 初めて家を建てた人の「平均年収」:約731万円
- 初めて家を建てた人の「平均年齢」:約39.5歳
- 初めて家を建てた人の「注文住宅購入費用の平均」:約4,713万円
- 初めて家を建てた人の「頭金の平均金額」:約941万円
- 初めて家を建てた人が「ローンで借り入れる平均金額」:約3,772万円
- 土地に関する様々な「制限」
- 間取りの考え方
- 建築依頼先の種類と特徴
注文住宅を建てる流れの全体像を確認したい方は「注文住宅の流れ」もご覧ください。
Contents
1. 一般的に「どんな人」が、「どれくらいの頭金・ローン」で家を建てているのか?
一般的に、どんな人が、どのくらいの頭金やローンを組んで家を建てているのかについて、以下にまとめました。
年齢でみると:40歳前後
年収でみると:約700万円
頭金の平均額:約1,000万円
ローンの平均額:約4,000万円
注文住宅購入費用(土地代含む)平均額:約5,000万円
出典:国土交通省 「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」
以降、家を建てている人の「平均」についてより詳しく解説します。
1-1.初めて家を建てた人の「平均年収」:約731万円
国土交通省の調査によると、
初めて注文住宅を建てた人(一次取得者)の平均年収は約731万円
です。
注文住宅を建てた人の年収は、全国平均と都市圏では50万円ほど差があります。
これは、都市圏の方が平均年収自体高い傾向にあるため、と考えられます。
また、分譲集合住宅(マンション)の平均世帯年収がもっとも高いのは、都市部の地価が高い地域にある、高額な分譲集合住宅を高所得者層が活発に購入しているためと推測できます。
1-2.初めて家を建てた人の「平均年齢」:約39.5歳
国土交通省の調査によると、
初めて家を建てた人(一次取得者)の平均年齢は約39.5歳
です。
年齢の割合は上記の図のとおり、
- 10〜20代…16%
- 30代…45%
- 40代…23%
- 50代…8%
- 60歳以上…8%
です。
初めて家を建てた方の年齢は30代〜40代が7割を占めています。
1-3.初めて家を建てた人の「注文住宅購入費用の平均」:約4,713万円
国土交通省によると、
初めて家を建てた人の住宅購入費用の平均は約4,713万円
です。
調達方法の内訳は上記の図にあるように、
- 自己資金(頭金+諸費用)・・・941万円
- 借入金(ローンなど)・・・3,772万円
- 自己資金比率・・・20.0%
です。
1-4.初めて家を建てた人の「頭金の平均金額」:約941万円
頭金とは、「住宅を購入する際に準備する自己資金」を指します。
国土交通省によると、
住宅ローンの頭金の平均金額は、約941万円
です。
一般的に、住宅購入費用の2〜3割が目安となります。
例えば、住宅購入費用が5,000万円なら、頭金は約1,000万円が目安です。
しかし現在は、頭金がなくても住宅購入費用の全額を住宅ローンで借入することもできます。
ただし頭金がないと、その分利息が高くなるため注意が必要です。
1-5.初めて家を建てた人が「ローンで借り入れる平均金額」:約3,772万円
ローンとは、一般的に「銀行等の金融機関からお金を借りること」を指します。
国土交通省によると、
土地付き注文住宅を建てた人がローンで借り入れる平均金額は、約3,772万円
です。
また、住宅金融支援機構がフラット35の利用者を対象に実施した調査によれば、土地付き注文住宅を購入する場合の住宅資金の平均は年収の7.7倍でした。
年収別借り入れ可能額の目安は、以下のとおりです。
| 年収 | 頭金なし | 頭金2割 |
|---|---|---|
| 400万円 | 3,080万円 | 2,464万円 |
| 500万円 | 3,850万円 | 3,080万円 |
| 600万円 | 4,620万円 | 3,696万円 |
| 700万円 | 5,390万円 | 4,312万円 |
| 800万円 | 6,160万円 | 4,928万円 |
| 900万円 | 6,930万円 | 5,544万円 |
| 1,000万円 | 7,700万円 | 6,160万円 |
※利息がかかるため、返済総額は変わります
ローンの限度額や返済プランについて知りたい方は、下記記事も併せてご覧ください。
家を建てることが初めての場合、特に予算や資金計画についてお悩みの方も多いかと思います。
そんな時はぜひHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービス(無料)をご利用ください。
あなたの予算・要望に合ったハウスメーカー・工務店の実際の住宅プラン(資金計画含む)を比較できるので、具体的な費用イメージを持ちながら資金計画が立てられます。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
2.まず押さえておきたいこと3選
ここでは、家を建てる前にまず押さえておきたいことを3つ厳選して解説しています。
- 土地に関する様々な「制限」
- 間取りの考え方
- 建築依頼先の種類と特徴
2-1.土地に関する様々な「制限」
土地にはいろいろな制限・規則が定められています。
規則の内容によっては、住宅の大きさに関わるものもあるため、知らずに理想の住宅を考えてしまったことで、「実は規則違反だった…」と後から後悔するケースもあります。
そこで、下記のような基礎知識をよく調べておくことが重要です。
- 土地にはそれぞれ用途地域が定められている
- 「建ぺい率」と「容積率」により、その土地に建てられる家の最大の大きさが決まっている
- 「道路斜線制限」「北側斜線制限」「隣地斜線制限」という、その土地によって家の高さ制限がある
上記項目それぞれについては、下記記事で詳しく解説しています。
2-2.間取りの考え方
多くの場合、ハウスメーカーや工務店などが間取りを提案してくれます。
ただ自分の要望を活かしたものにできるよう、自分自身でも前もって間取りをイメージしておくことがおすすめです。
理想の間取りを考えるうえで、知っておきたいことの例を以下にまとめました。
- 希望だけを詰め込むと「生活しにくい」間取りになるため、「生活しやすい動線」を考える
- 細かい間取りを考える前に、大まかな部屋の配置や空間を設定する
- 「家族構成の変化」や「子供の成長」などライフスタイルの変化があることも想定しておく
イメージを膨らませるために、間取りの事例をたくさん見るのもおすすめです。
間取りの考え方や間取りの事例について、より詳しく知りたい方は下記記事もご覧ください。
2-3.建築依頼先の種類と特徴
建築依頼先は大きく分けて「ハウスメーカー」「工務店」「設計事務所」の3つがあります。
それぞれに特徴があるため、自分に合った建築依頼先を選ぶと良いでしょう。
| 特徴 | |
|---|---|
| ハウスメーカー |
|
| 工務店 |
|
| 設計事務所 |
|
初めての注文住宅の場合、おすすめは「ハウスメーカー」や施工対応エリアの規模が大きい「工務店」です。
より詳細に建築依頼先について知りたい方は、下記記事も併せてご覧ください。
HOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービス(無料)なら、全国に数万社あるといわれているハウスメーカー・工務店の中から厳選された優良ハウスメーカー・工務店を紹介しています。
また、土地探しをサポートしてくれるハウスメーカーや工務店もありますので、土地購入が必要な方も活用するとよいでしょう。
この記事のポイント まとめ
一般的に、どんな人が、どのくらいの頭金やローンを組んで家を建てているのかについてまとめました。
年齢でみると:40歳前後
年収でみると:約700万円
頭金の平均額:約1,000万円
ローンの平均額:約4,000万円
注文住宅購入費用(土地代含む)平均額:約5,000万円
詳細は「1.一般的に「どんな人」が、「どれくらいの頭金・ローン」で家を建てているのか?」で詳しく解説しています。
本記事では、家を建てる前にまず押さえておきたいことを3つ厳選して解説しています。
- 土地に関する様々な「制限」
- 間取りの考え方
- 建築依頼先の種類と特徴
詳細は「2.まず押さえておきたいこと3選」で詳しく解説しています。