
本記事は、これから一戸建て・一軒家を買おうと思っている方に向けて、注文住宅・建売住宅・中古住宅といった種類別に「一戸建ての値段・価格の平均」について、できる限り簡潔な内容で解説しています。
また、ここでの「値段・価格」とは建築費のみではなく、土地の購入も含めた「一戸建てを取得する費用全体」を指します。
- 注文住宅・建売住宅・中古住宅の値段・価格の平均(令和5年度基準)
- 注文住宅の土地あり・土地なしの値段・価格の平均を比較
- 諸費用の相場や住宅ローンの借入額目安について等の関連知識
まとめて依頼!
これからマイホーム購入・新築を検討する方は「お家のいろはー家を建てるー」で情報収集を始めましょう。
Contents
1.一戸建て(注文住宅)の値段・価格の平均は?
全国の一軒家を「注文住宅(土地あり・土地なし)」「建売住宅」「中古住宅」に分けて、平均価格がどのくらいなのかを見ていきます。
土地をすでに持っている方の注文住宅(建物のみ)の値段の平均は、
4,319万円です。
土地を持っていない方の注文住宅(建物+土地)の値段の平均は、
5,811万円です。
建売住宅(建物+土地)の値段の平均は、
4,290万円です。
中古住宅(建物+土地)の値段の平均は、
2,983万円です。
参考:国土交通省「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
「注文住宅」「建売住宅」「中古住宅」それぞれの特徴について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
2.注文住宅の値段は平均4,034万円(建築費のみ)
注文住宅の一戸建てを建てた場合、平均で4,034万円(建築費のみ)の費用がかかります。
注文住宅の値段の平均は、ここ5年間で851万円増加しています。
これは、円安により外国から輸入している建材価格が上昇したことや、物価高による人件費の高騰が理由と考えられます。
2-1.「土地あり・土地なし」ケース別に値段の平均を比較
土地をすでに持っている方の注文住宅(建物のみ)の値段の平均が4,034万円なのに対し、土地を持っていない方の注文住宅(建物+土地)の値段の平均は、5,811万円です。
土地を持っていない方は「土地の取得」にもお金をかける必要があるので、+1,000万以上多く費用をかけています。
「土地なし」と「土地あり」の注文住宅の値段についてエリア毎に比較したい方や、より詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
どう進めていいかわからない方へ
ハウスメーカーと土地は
同時に探すのがおすすめ!
土地費用を抑え、家にお金をかけられた
ノウハウ豊富なハウスメーカーに相談できたから、斜面など、特殊なぶん安価な土地でも希望通りの家が建てられた!
家づくりプランをもらう
HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
3.建売住宅の値段は平均4,290万円
建売で一戸建てを購入した場合、平均で4,290万円(建物+土地)の費用がかかります。
建売住宅の値段の平均は、ここ5年間で439万円増加しています。
こちらも、建材価格の上昇や物価高による人件費の高騰が理由と考えられます。
4.中古住宅の値段は平均2,983万円
建売で一戸建てを購入した場合、平均で2,983万円(建物+土地)の費用がかかります。
中古住宅の値段の平均は、ここ5年間で398万円増加しています。
最近では、若年層を中心に「低コストで中古物件を購入し、リノベーションしたい」という方が増えており、中古物件の需要も高いため、それが価格上昇の原因と考えられます。
HOME4U(ホームフォーユー)無料サポートサービス
実際の見積もりを
複数比較・検討したい
簡単なスマホ入力だけで、複数のハウスメーカーの見積もりが無料でもらえる「プラン作成サービス」がおすすめ!
資金計画や補助金活用の
コツが知りたい
ハウスメーカー出身のアドバイザーに、自宅から簡単に相談できる「無料オンライン相談サービス」がおすすめ!
5.その他の費用
ここでは、
- 諸費用
- 住宅ローン
について解説します。
5-1.諸費用:注文住宅も建売も中古も「土地+建物代の10%程度」
諸費用とは、登記費用や建築確認申請料など、主に事務的な部分で必要な費用です。
土地+建物費用のおおよそ10%程度が相場であり、200〜500万円程かかります。
注文住宅の諸費用の詳細については、下記関連記事をご参照ください。
5-2.住宅ローンの借入額:年収の約5~6倍
住宅ローンの借入額は一般的に年収の約5~6倍の金額で設定しておくと無理なく返済を行うことができます。
ここでは、下記条件で借入金額と月々の返済額の目安を算出します。
- 年収:300万円~1,000万円 ※100万円ごとに算出
- 借入金額:35年
- 金利タイプ:全期間固定
- 金利:1%
- 返済方法:元利均等
- ボーナス:なし
| 年収 | 借入金額の目安 | 月々の返済額の 目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 1,500万~ 1,800万円 |
42,342~ 50,811円 |
| 400万円 | 2,000万~ 2,400万円 |
56,457~ 67,748円 |
| 500万円 | 2,500万~ 3,000万円 |
70,571~ 84,685円 |
| 600万円 | 3,000万~ 3,600万円 |
84,685~ 101,622円 |
| 700万円 | 3,500万~ 4,200万円 |
98,799~ 118,559円 |
| 800万円 | 4,000万~ 4,800万円 |
112,914~ 135,497円 |
| 900万円 | 4,500万~ 5,400万円 |
127,028~ 152,434円 |
| 1,000万円 | 5,000万~ 6,000万円 |
141,142~ 169,371円 |
※住宅保証機構株式会社「住宅ローンシミュレーション」より算出
住宅ローンに関してより詳細に知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
自分の建てたい家の費用はいくらくらいなのか、また、具体的にはどのような家になるのかが知りたい方は、ぜひ一度HOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービス(無料)をご利用ください。
ハウスメーカー・工務店があなたのために作成した住宅プランを複数比較できるので、予算やこだわりのイメージがつきやすく、具体的な資金計画が立てられます。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
「一軒家に関する記事」を他にも用意しております。あわせてご覧ください。
この記事のポイント まとめ
一軒家(注文住宅・建売住宅・中古住宅)の平均的な値段は以下のとおりです。
- 注文住宅(建物のみ):4,034万円
- 注文住宅(建物+土地):5,811万円
- 建売住宅:4,290万円
- 中古住宅:2,983万円
参考:国土交通省「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」
詳細はそれぞれ「2.注文住宅の値段は平均4,034万円(建築費のみ)」「3.建売住宅の値段は平均4,290万円」「4.中古住宅の値段は平均2,983万円」で解説しています。





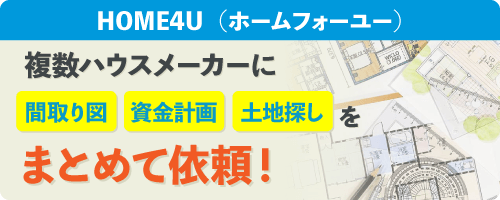


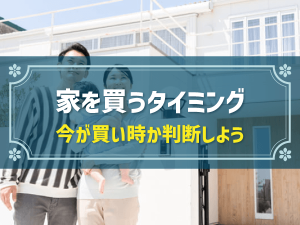
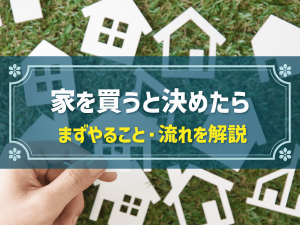





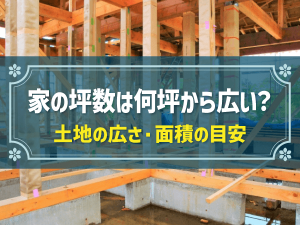
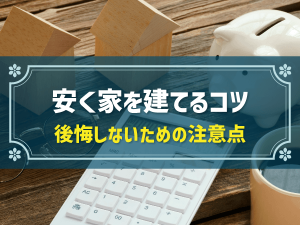

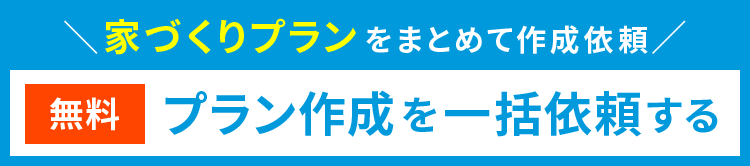
まさかの…土地探しが振り出しに!?
住みたいエリアの条件だけで土地を探していたけど、よくよく建てる家を考えた結果、4人家族の家にするには狭すぎて断念…。