
この記事では土地の値段を自分で調べる方法を解説します。
Contents
1. 土地の価格はどのように決まるのか?
土地の価格は「ただ立地が良ければ高い」という単純なものではありません。
ここでは土地価格に影響を与える代表的な5つの要素を解説します。
1-1. 土地の需要と供給のバランス
土地の価格において最もベースとなるのが、需要と供給の関係です。
人口が集中している都市部や開発計画が進むエリアでは、需要が高まるため価格は上昇する傾向にあります。
反対に、過疎化が進んでいる地域や利便性が低いエリアでは買い手が少なく、価格は下落しやすくなります。
地価の推移や地域の人口動態も価格決定に直結します。
もし「自分の土地の価格が今どのくらいなのか」を具体的に知りたい場合は、不動産一括査定サービスを活用するのも一つの方法です。
不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)のような信頼性の高い一括査定サイトなら、複数の不動産会社から査定額を比較でき、相場感をつかんだうえで納得できる売却の一歩を踏み出せます。
1-2. 土地の立地
駅やバス停など公共交通へのアクセス、周辺の商業施設や医療機関、教育施設の有無など、生活利便性が高い場所ほど需要が高まり価格にも反映されます。
また、再開発エリアや将来的な都市計画の対象エリアでは、「期待値」から相場が上がることもあります。
1-3. 土地の形状
整形地(長方形・正方形など)は建物が建てやすく、評価が高くなる傾向にあります。
反対に、旗竿地や三角形、不整形地などは建築の自由度が低く、利用価値が制限されるため価格も割安になります。また、接道長さや道路幅、間口・奥行きのバランスも査定時に重要視されます。
1-4. 土地の面積
広い土地ほど価格が高くなるイメージがありますが、実際は用途やエリアによって異なります。
住宅地では60〜80平米程度の土地に需要が集まり、それ以上になると逆に買い手が限られてしまうことも。土地を分筆(分けて売却)できるかどうかも、面積評価に影響します。
1-5. 近隣の取引事例との比較
過去に取引された近隣の土地価格(実勢価格)は、現在の市場価格を把握するうえで非常に重要な情報です。
エリア・面積・形状・用途地域などが似た物件であれば、価格の目安として大いに参考になります。不動産会社の査定でもこの「取引事例比較法」がよく用いられます。
- 「土地を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格
- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
2. 土地の値段を自分で調べる方法
土地の価格は、不動産会社に頼らずともある程度は自分で調べることが可能です。
ここでは公的に発表されている4つの地価情報を活用し、自力で土地の相場を把握する方法をご紹介します。
2-1. 公示地価を使う
公示地価は国土交通省が毎年3月に公表する、標準的な土地に対する1平米あたりの価格です。
全国に約26,000カ所ある「標準地」での価格が示され、不動産鑑定士によって評価されます。土地総合情報システムを利用すれば、住所や地図から簡単に確認できます。
あくまで標準条件下の価格であり、個別事情(形状・日照・接道など)は反映されないため、目安として活用しましょう。
2-2. 基準地価を使う
基準地価は都道府県が毎年9月頃に発表する地価情報で、公示地価の補完的な位置づけです。
主に地方や公示地価のない地域の価格をカバーしており、評価時点は7月1日です。
公示地価との大きな違いは調査主体と評価時期で、両方を比較することで半年間の地価変動を見ることも可能です。土地総合情報システムまたは都道府県のホームページで調べることができます。
2-3. 路線価を使う
路線価は国税庁が毎年発表する、相続税や贈与税の課税基準となる土地価格です。
市街地では道路ごとに「1平米あたりの価格」が設定され、地図上で確認することができます。
国税庁の「路線価図」で該当エリアを探し、表示された価格(例:360D=36万円/平米)を参考にします。
ただし、実勢価格よりも低く、公示地価の約8割が目安となるため、補助的な資料として活用しましょう。
2-4. 固定資産税評価額を使う
固定資産税評価額は、市区町村が課税のために設定する土地の価格です。3年に1度評価替えが行われ、評価額は納税通知書や役所で確認できます。
公示地価の6〜7割程度が目安とされますが、実勢価格とのズレがあるため、あくまで相場をつかむ「参考価格」としての利用が適しています。
3.地価情報4指標の比較表
「土地の値段を自分で調べる方法」で説明した4つの指標についての比較表です。
| 指標名 | 管轄機関 | 主な目的 | 更新頻度 | 評価時点 | 価格水準(目安) | 調査エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示地価 | 国土交通省 | 不動産取引・価格の目安 | 年1回(3月頃) | 毎年1月1日 | 実勢価格に近い | 主に都市部・全国主要地点 |
| 基準地価 | 都道府県 | 公示地価の補完/地価動向把握 | 年1回(9月頃) | 毎年7月1日 | 公示地価と同程度 | 地方・都市部全域 |
| 路線価 | 国税庁 | 相続税・贈与税の課税評価 | 年1回(7月頃) | 毎年1月1日 | 公示地価の約8割 | 道路単位(市街地中心) |
| 固定資産税評価額 | 市区町村 | 固定資産税・都市計画税の課税 | 3年に1度 | 原則1月1日 | 公示地価の6〜7割 | 全国すべての土地 |
土地の売却を進めているなら、相場についてある程度把握した後は、不動産会社に査定依頼をしましょう。
プロに相談することでスムーズに手続きを進めることができます。
4. まとめ|自分で調べた価格を目安に、必要に応じて査定も検討を
ここまで土地の価格が決まる仕組みや自分で価格を調べる方法について解説してきました。
複数の情報を組み合わせて相場をつかむことが、正確で納得感のある売却につながります。
4-1. 複数の情報を照らし合わせて相場を掴む
土地の価格を正しく理解するためには、公示地価・基準地価・路線価・固定資産税評価額といった複数の公的情報を比較・組み合わせて判断することが大切です。
それぞれの指標には特性や評価目的が異なるため、1つの数値に依存せずに全体を俯瞰して価格感をつかむことが重要です。
4-2. 正確な価格は不動産会社の現地査定が不可欠
公的データは「目安」にはなりますが、形状・接道・地盤・地形・周辺環境など、土地個別の条件までは反映されません。
正確な売却価格を知るためには、やはり現地を確認してもらう「訪問査定」が必要不可欠です。
特に市街地にある変形地や高低差のある土地、接道が複雑な土地などは、実際に見てもらわないと正確な査定が難しいケースが多くあります。
4-3. 価格感を持って査定を依頼すれば納得できる
公的な指標で価格の相場感をつかんでおけば、査定結果に対して「高すぎる/安すぎる」といった判断がしやすくなります。
営業トークや過度な値引き提案に流されることなく、冷静に対応できるようになるのです。
不動産一括査定サービスを使う前に、この記事で紹介したような調査をしておくことで、「納得して依頼する」姿勢が持てます。
土地の売却や相続を検討しているなら、まずは公的情報で価格の目安を把握するところから始めてみましょう。
そして、必要に応じて不動産会社に査定を依頼すれば、より納得感のある取引が実現できます。
「調べて知る」ことが、失敗しない不動産売却の第一歩です。
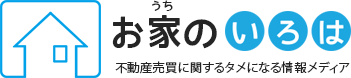
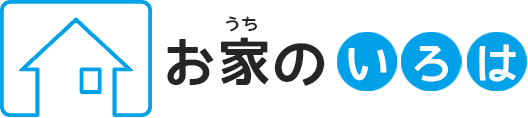

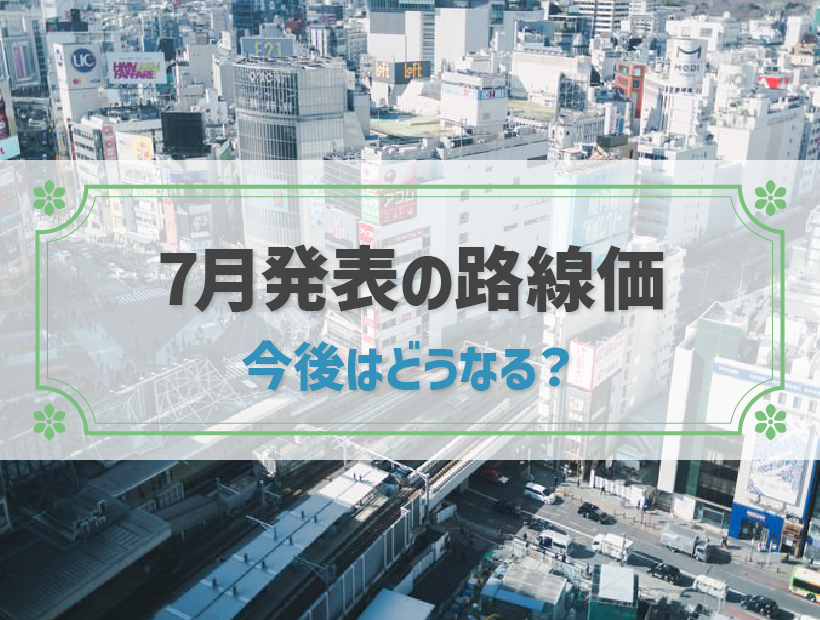
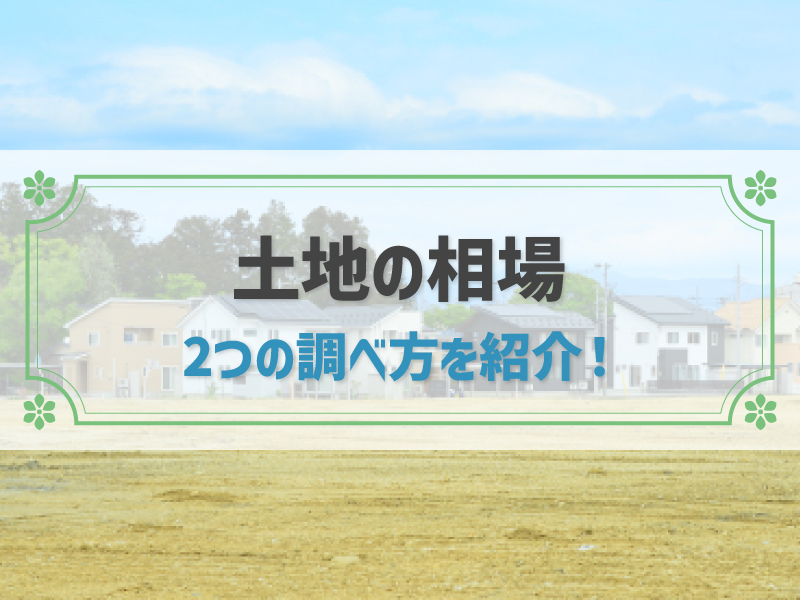

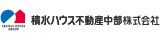

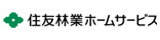
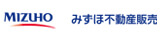


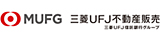
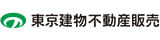



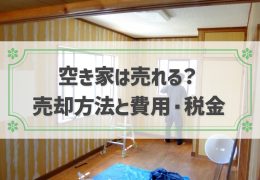




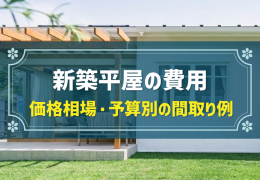

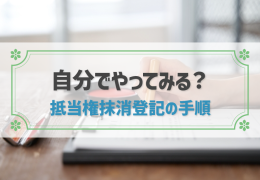




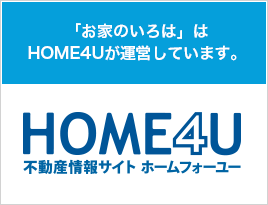
![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)
![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)