
この記事は、家を新築するのに際して補助金利用を検討している方向けに、2024年度に使える補助金・助成金、減税措置ついて、国・自治体が提供しているものを一覧形式で分かりやすく解説しています。
- 新築住宅に対する国の補助金・助成金
- 新築住宅の建築・購入に対する減税制度
- 自治体提供の補助金や助成金 例
まとめて依頼!
これからマイホーム購入・新築を検討する方は「お家のいろはー家を建てるー」で情報収集を始めましょう。
Contents
1.新築住宅の補助金・助成金・減税制度一覧
新築住宅を購入、建てるときに利用できる補助金・助成金・減税制度は以下のようになります。
| 子育てエコホーム支援事業 | |
|---|---|
| 支援対象 | 子育て世帯・若者夫婦世帯による、高い省エネ性能を有する住宅の新築及び住宅の省エネ改修工事等に対して支給 |
| 補助金額 |
|
| 申し込みに ついて |
子育てエコホーム支援事業者経由で申し込み 子育てエコホーム支援事業者の検索 |
| 給湯省エネ2024事業 | |
| 支援対象 | 戸建、共同住宅等によらず、高効率給湯器を設置する方 |
| 補助金額 | 最大20万円/台 |
| 申し込みに ついて |
給湯省エネ事業者経由で申し込み 給湯省エネ事業者の検索 |
| ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業 | |
| 支援対象 | 「ZEH」又は「ZEH+」の戸建住宅を新たに建築する、又は新築建売住宅を購入する方 |
| 補助金額 |
|
| 申し込みに ついて |
ZEH住宅の建築を依頼するZEHビルダーのハウスメーカー経由(個人でも可)で申請 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業「戸建てZEH」 |
| LCCM住宅整備推進事業 | |
| 支援対象 | ライフサイクルカーボンマイナス(LCCM)住宅を新築する方 |
| 補助金額 | 設計費、建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用の合計額の1/2 (補助限度額 140万円/戸) |
| 申し込みに ついて |
住宅供給事業者が申請をする |
| 減税制度 | 内容 |
|---|---|
| 住宅ローン減税 (住宅ローン控除) |
13年間、年末時に残っている住宅ローンの額の0.7%分が、その年に支払った所得税額等から控除される |
| 登録免許税の 税率軽減 |
〈住宅〉所有権の保存登記:0.15% 〈土地〉所有権の移転登記:1.5% 抵当権の設定登記:0.1% |
| 印紙税の軽減 | 最大50%軽減 |
| 不動産取得税の 軽減 |
税率が「4%」から「3%」に軽減 |
| 固定資産税の 軽減 |
通常の住宅だと3年間、認定長期優良住宅だと5年間、固定資産税額が2分の1になる |
| 贈与税 住宅取得等資金に 係る 非課税措置 |
最大1,000万円までの贈与が非課税になる |
| 【東京都】 東京ゼロエミ住宅導入促進事業(助成事業) |
|
|---|---|
| 概要 | 省エネ性能の高い住宅を新築で建築する際に受けられる補助制度 |
| 補助金額 | 最大210万円 |
| 申し込みについて | 電子申請で申し込み 令和6年度東京ゼロエミ住宅導入促進事業 |
| 【兵庫県神戸市】 老朽空家等解体補助制度 |
|
| 概要 | 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した建物で腐朽・破損のある空き家を解体する場合に補助を受けられる制度 |
| 補助金額 | 解体工事に要した費用の3分の1以内(上限60万円) |
| 申し込みについて | すまいるネットの窓口にて申し込み 神戸市老朽空家等解体補助事業 |
| 【千葉県市川市】 住宅の耐震診断・耐震改修に関する補助制度 |
|
| 概要 | 住宅が地震にどの程度の強さを持っているかを、市川市に登録している耐震診断士によって調査(耐震診断)する費用の一部と、その調査に基づいて行う改修(補強)工事等の費用の一部を助成する制度 |
| 補助金額 | 上限100万円 |
| 申し込みについて | 木造住宅耐震診断士に見積もりを依頼後、施工者に概算見積書の依頼をし、市川市へ「補助金交付申請書」を提出 建築物の耐震診断・改修工事の助成に関して |
| 【静岡県藤枝市】 子育てファミリー移住定住促進事業 |
|
| 概要 | 子育てファミリーが藤枝市内で新築住宅を取得した際の補助金制度 |
| 補助金額 |
|
| 申し込みについて | オンライン申請する 藤枝市子育てファミリー移住定住促進事業費補助金交付申請フォーム |
| 【愛知県】 愛知県移住支援事業(移住支援金の支給) |
|
| 概要 | 東京23区からの移住者に「移住支援金」を支給する制度 |
| 補助金額 |
|
| 申し込みについて | 転入した市町村役場へ申請する 愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)について |
2.国による新築住宅への補助金・助成金 解説
国が行っている新築住宅への補助金や助成金制度には、次のようなものがあります。
- 子育てエコホーム支援事業
- 給湯省エネ2024事業
- ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業
- LCCM住宅整備推進事業
制度の概要や適用するための要件、申請方法を1つずつ確認していきましょう。
2-1.子育てエコホーム支援事業
制度の概要
子育てエコホーム支援事業は、子育て世代・若者夫婦世帯が「高い省エネ性能を持つ住宅」を建てやすくするために補助金を支援する制度です。
適用条件
適用条件は、省エネ住宅を建築・購入する、もしくは条件を満たすエコリフォームを実施することです。
ただし、新築建築・購入の場合は、申請時点で以下のいずれかの条件に該当する世帯(両方ともに該当する必要はありません)のみが対象となります。
新築建築・購入の対象世帯
- 子育て世帯:2005年4月2日以降に出生した子がいる(2024年3月31日までに建築着工する場合は2004年4月2日以降に出生した子がいること)
- 若者夫婦世帯:夫婦のどちらか一方が1983年4月2日以降生まれ(2024年3月31日までに建築着工する場合は1982年4月2日以降生まれである)
いずれの世帯も2023(令和5)年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手したものが対象となります。
工事請負契約日の期間は不問ですが、建築着工までに契約が締結されている必要があるのでご注意ください。
補助金額
| 住宅種類 | 補助金額 |
|---|---|
| 長期優良住宅 | 最大100万円/戸 |
| ZEH住宅 | 最大80万円/戸 |
申請方法・期限
申請はハウスメーカー・工務店によって行われるため、建築主や購入者は実際の手続きをする必要がありません。
建築依頼先には、子育てエコホーム支援事業に登録しているハウスメーカー・工務店を選びましょう。
なお、交付申請期間 は2024(令和6)年4月2日から同年12月31日までが予定されていますが、予算上限に到達すると終了になるため注意が必要です。
2-2.給湯省エネ2024事業
制度の概要
高効率給湯器の導入をサポートすることで、安定したエネルギー需給を維持しつつ温室効果ガスの排出量を削減することを目的とした制度です。
適用条件
戸建て住宅・共同住宅によらず、住宅に高効率給湯器を購入・設置するときに適用されます。
補助金額
| 設置する給湯器 | 補助金額 | 性能 加算額 |
|---|---|---|
| ヒートポンプ給湯器 (エコキュート) |
8万円 /台 |
最大 5万円 /台 |
| 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式 併用型給湯器 (ハイブリッド給湯器) |
10万円 /台 |
最大 5万円 /台 |
| 家庭用燃料電池 (エネファーム) |
18万円 /台 |
最大 2万円 /台 |
なお、戸建て住宅ではいずれか2台まで、共同住宅ではいずれか1台までが適用上限台数です。
性能によっては、1台あたり最大5万円が加算されます。
申請方法・期限
申請手続きは、新築注文住宅の場合は建築事業者、新築分譲住宅と既存住宅購入の場合は販売事業者、既存住宅のリフォームの場合は施工業者が行います。
交付申請期間 は2024(令和6)年3月中下旬から遅くとも同年12月31日までの予定ですが、予算上限に到達すると終了になるため注意が必要です。
2-3.ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業
制度の概要
電気やガスといったエネルギーをあまり使わなくても快適に過ごせる家、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の建築を奨励するための支援事業です。
適用要件
適用要件として、居住用の住宅であることと、ZEHビルダーとして登録されている施工会社がZEHの要件を満たした家を新築することが求められます。
補助金額
| ZEH住宅の 種類 |
内容 | 補助金額 |
|---|---|---|
| ZEH | 一般的なZEHの要件である一定以上の断熱性能・省エネ基準比20%以上・再生可能エネルギー導入100%以上を満たしていること。 | 55万円 |
| Nearly ZEH | 断熱性能・省エネ性能はZEHと同等基準。 太陽光発電によるエネルギー生産率が75%以上。(寒冷地や都市狭小地等に限る) |
|
| ZEH oriented | 断熱性能・省エネ性能はZEHと同等基準。 太陽光発電なしでOK。(狭小地等に限る) |
|
| ZEH+ | 断熱性能・省エネ性能はZEHと同等基準を満たし、さらに一次エネルギー消費量25%以上削減。 決められた高性能機器の導入が必要。 |
100万円 |
| Nearly ZEH+ | 断熱性能・省エネ性能はZEHと同等基準。 太陽光発電によるエネルギー生産率が75%以上。 (寒冷地や都市狭小地等に限る) |
いずれのZEH住宅も「蓄電システム」など高性能機器を追加で取り付けると、さらに補助金が加算されます。
申請方法・期限
ZEH住宅の建築を依頼するZEHビルダーのハウスメーカー経由(個人でも可)で申請を行います。ZEHハウスメーカーについて調べておき、タイミングよく動けるよう準備しておくことをおすすめします。
公募期間は以下のとおりです。
- 一般公募(単年度事業):2024年4月26日~2025月1月7日
- 一般公募(複数年度事業):2024年11月5日~2025年1月7日
基本的に公募期間内であっても、予算に達すれば受付を終了します。
参照:一般社団法人 環境共創イニシアチブ「経済産業省及び環境省による戸建ZEH補助事業」
2-4.LCCM住宅整備推進事業
制度の概要
脱炭素化住宅であるLCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅を新築する際に補助金が出る制度です。
適用要件
この制度の補助となる住宅は、戸建て住宅の新築であることなど11項目の要件を満たす必要があります。
詳細は令和6年度サステナブル建築物先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建て住宅部門概要をご覧ください。
補助金額
「設計費」と「建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用」の合計額の1/2
(補助限度額 140万円/戸)
申請方法・期限
令和6年度より交付申請先が一般社団法人環境共生まちづくり協会へ変更となっていますが、申請はハウスメーカー・工務店等の事業者によって行われるため、建築主や購入者は実際の手続きをする必要がありません。
公募期間は2024(令和6)年5月17日から2025(令和7年)1月20日までになります。
参照:一般社団法人 環境共生まちづくり協会「令和6年度サステナブル建築物先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建て住宅部門」
3.家を新築した際の減税制度 解説
家を新築した際は、要件を満たせばいくつかの減税制度・措置を適用することが可能です。
- 住宅ローン減税(住宅ローン控除)
- 登録免許税の税率軽減
- 印紙税の軽減
- 不動産取得税の軽減
- 固定資産税の軽減
- 贈与税 住宅取得等資金に係る非課税措置
確定申告が必要なものもあるため、忘れずに申請したり申告したりするようにしましょう。
3-1.住宅ローン減税(住宅ローン控除)
内容
住宅ローン減税は「13年間、年末時に残っている住宅ローンの額の0.7%分が、その年に支払った所得税額等から控除される」制度です。
ただし、控除される上限額は住宅性能等により異なります。
上限金額の一番高い認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合、1年あたり「最大31.5万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は35万円)」が控除されます。
具体的な控除対象になる「ローン借入額」の上限は以下の通りです。
| 家の性能 | 控除対象になる 「ローン借入額」の上限 |
|
|---|---|---|
| 2024年に入居 | 2025年に入居 | |
| 長期優良住宅・ 低炭素住宅*1 |
4,500万円 5,000万円 |
4,500万円 |
| ZEH水準の 省エネ住宅*1 |
3,500万円 4,500万円 |
3,500万円 |
| 省エネ基準 適合住宅*1 |
3,000万円 4,000万円 |
3,000万円 |
| 上記に該当しない 住宅*2 |
0円 | 0円 |
*1 下段は子育て世帯・若者夫婦世帯が対象
*2 2023年までに新築の建築確認をした場合、2,000万円となります。
適用要件
住宅ローン減税を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 住宅を取得した日から6ヵ月以内に住み始めること
- 床面積が50平米以上の住宅であること(年間所得が1,000万円以下の場合は40平米以上)
- 10年以上の返済期間の住宅ローンを組んでいること
- 控除を受ける年の年収が2,000万円を超えないこと
適用に必要な手続き
住宅ローン控除を適用する初年は、住宅を取得した翌年2~3月中に確定申告が必要です。
2年目以降は、給与所得者であれば年末調整の際に必要書類を提出すれば、確定申告なしで控除を受け取ることができます。
参照:国税庁「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
参照:国土交通省「住宅ローン税制」
3-2.登録免許税の税率軽減
登録録免許税は、不動産の登記手続きを法務局で行う際に納める税金です。
内容
新築や建て替えをする際に必要となる登記手続きに2027(令和9)年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、次のようになります。〈土地の移転登記は2026(令和8)年3月31日まで〉
| 登記の種類 | 本則税率 | 特殊税率 |
|---|---|---|
| 〈住宅〉所有権の保存登記 | 0.4% | 0.15%※ |
| 〈土地〉所有権の移転登記 | 2.0% | 1.5%※ |
| 抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.1% |
※条件により変動
参照:財務省「登録免許税に関する資料」
参照:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
参照:法務局「令和4年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ」
3-3.印紙税の軽減
工事請負契約書や不動産譲渡契約書を作成するときには、印紙税がかかります。
内容
印紙税額は契約金額によって決まりますが、2027(令和9)年3月31日までに契約を締結する場合は、特例措置として最大50%軽減されます。
参照:国土交通省「令和6年度国土交通省税制改正概要」
参照:国税庁「「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について」
3-4.不動産取得税の軽減
内容
不動産取得税の税率を2027年3月31日までに取得した場合3%に軽減されます(本則:4%)。
また、新築の家を取得した場合、居住用の家で課税される床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であれば、建物の固定資産税評価額から1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)控除されて、不動産取得税が計算されます。
加えて、宅地においても評価額が1/2に軽減され、さらに減額措置が適用される場合があります。
参照:国土交通省「 令和6年度国土交通省税制改正概要」「不動産取得税に係る特例措置」
参照:東京都主税局「不動産取得税」
3-5.固定資産税の軽減
内容
2026(令和8)年3月31日までに新築された住宅に対して、固定資産税の軽減を受けられます。
通常の住宅だと3年間、認定長期優良住宅だと5年間、固定資産税額が2分の1になります。
参照:国土交通省「 令和6年度国土交通省税制改正概要」
参照:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
3-6.贈与税 住宅取得等資金に係る非課税措置
内容
家を新築したり購入したりする際に、父母・祖父母などの「直系尊属」から購入資金として贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
2026年12月31日まで延長されましたが、非課税の対象となる金額は最大1,000万円に縮小となりました。
贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までの間に、贈与税の申告が必要です。
| 贈与の時期 | 一定の基準を満たした住宅※ | 一般住宅 |
|---|---|---|
| 2022年4月1日~2026年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
※省エネルギー性の高い住宅、耐震性の高い住宅、バリアフリー性の高い住宅を意味します。
参照:国土交通省「 令和6年度国土交通省税制改正概要」
参照:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
HOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスなら、専任コーディネーターによる複数ハウスメーカーへの資金計画作成依頼のほか、間取り図や土地探しを依頼できます。
4.自治体による補助金や助成金 例
国や税金の優遇制度だけでなく、各自治体にもさまざまな補助金や助成金があります。
- 【東京都】東京ゼロエミ住宅導入促進事業(助成事業)
- 【兵庫県神戸市】老朽空家等解体補助制度
- 【千葉県市川市】住宅の耐震診断・耐震改修に関する補助制度
- 【静岡県藤枝市】子育てファミリー移住定住促進事業
- 【愛知県】愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)
以下でそれぞれの制度について説明しますが、詳細は各自治体の公式HPをご確認ください。
4-1. 【東京都】東京ゼロエミ住宅導入促進事業(助成事業)
各自治体で省エネ住宅に独自の補助金を設けていますが、東京都では、2019(令和元)年度から、高省エネ住宅に向けて助成事業を行っています。
助成金の金額は、3段階の水準に応じて異なり、最大210万円/戸の助成が受けられます。
令和6年10月1日から水準1~3の三段階が水準C~Aに代わり、助成額も新基準に応じたものになります。
本年度から大幅な見直しが実施されるため、以前から情報集め整理していたという方もチェックしておきましょう。
申し込み方法
電子申請で申込みます:令和6年度東京ゼロエミ住宅導入促進事業
参照:東京都環境局「「東京ゼロエミ住宅」とは?」
4-2. 【兵庫県神戸市】老朽空家等解体補助制度
この助成金は、築年数が古い家や倒壊の恐れがある家などを解体する場合に、自治体が費用の一部を負担してくれるというものです。
神戸市では、次の条件に該当する家を解体する際に助成金を受給できる「老朽空家等解体補助制度」を実施しています。
補助金額は解体工事に要した費用の3分の1以内かつ上限60万円(1件あたり)です。
古い空き家の処分に困っている場合だけでなく、築年数の経っている家を解体して新しく建て替えたい場合でも要件を満たせば適用できます。
申し込み方法
すまいるネットの窓口にて申し込みます:神戸市老朽空家等解体補助事業
参照:神戸市「老朽空家等解体補助制度の申請受付」
4-3. 【千葉県市川市】住宅の耐震診断・耐震改修に関する補助制度
耐震性能に不安のある古い木造住宅を建て替える際に、補助金が出る自治体もあります。
千葉県市川市の住宅耐震化促進事業における耐震改修(現地建替を含む)では上限100万円の補助金が出ます。
耐震基準を満たすように改修を行った場合、補助金の利用有無にかかわらず、固定資産税の減額・所得税の特別控除を受けることも可能です。
申し込み方法
木造住宅耐震診断士に見積もりを依頼後、施工者に概算見積書の依頼をし、市川市へ「補助金交付申請書」を提出します:建築物の耐震診断・改修工事の助成に関して
※期間内であっても予定数の上限に達すると募集は終了します。
参照:市川市「建築物の耐震診断・改修工事の助成に関して」
4-4. 【静岡県藤枝市】子育てファミリー移住定住促進事業
静岡県藤枝市では、子育てファミリー移住定住促進事業の一環として18歳以下の子どもがいる世帯に補助金事業を用意しています。
市外からの転入世帯は50万円、市内賃貸住宅からの転居世帯は30万円を上限として、購入費用の2分の1を受け取ることができます。
申し込み方法
藤枝市子育てファミリー移住定住促進事業費補助金交付申請フォームにてオンライン申請します。
参照:藤枝市「【新築住宅補助】子育てファミリー移住定住促進事業費補助金」
4-5. 【愛知県】愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)
愛知県では、東京23区からの移住者に「移住支援金」を支給しています。
補助金額は世帯の場合:100万円/世帯、世帯単身の場合:60万円/人です。
申し込み方法
転入した市町村役場へ申請します:愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)について
参照:愛知県「愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)について」
この他にも、各自治体ではさまざまな補助金・助成金事業を実施しています。
新築住宅を建てる際には、住む予定の自治体に補助金や助成金制度があるかどうかを確認しましょう。
家づくりの資金計画についてお悩みの方は、ぜひ無料のHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスをご利用ください。
あなたの予算・要望に合ったハウスメーカー・工務店の実際の住宅プラン(資金計画含む)を比較できるので、具体的な費用イメージを持ちながら資金計画が立てられます。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
5.家を新築した際利用できる優遇制度
家を新築した際は、一定の条件を満たすことで住宅ローンの金利や保険料などで優遇を受けられることがあります。
- 住宅ローン【フラット35】の金利優遇制度
- 住宅の構造による火災保険料の軽減
- 地震保険優遇制度
詳しくは下記記事をご覧ください。
この記事のポイント まとめ
- 子育てエコホーム支援事業
- 給湯省エネ2024事業
- ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業
- LCCM住宅整備推進事業
それぞれの詳細は「2.国による新築住宅への補助金・助成金」をご覧ください。
- 住宅ローン減税(住宅ローン控除)
- 登録免許税の税率軽減
- 印紙税の軽減
- 不動産取得税の軽減
- 固定資産税の軽減
- 贈与税 住宅取得等資金に係る非課税措置
それぞれの詳細は「3.家を新築した際の減税制度」をご覧ください。
その他、各自治体がそれぞれ、様々な補助金制度を提供しています。

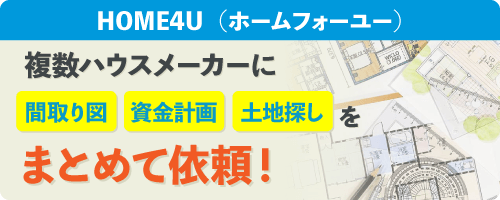


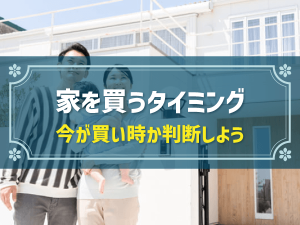
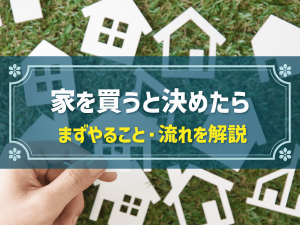



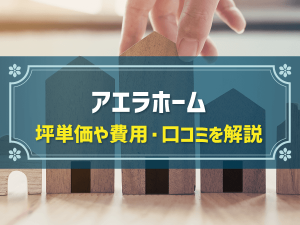
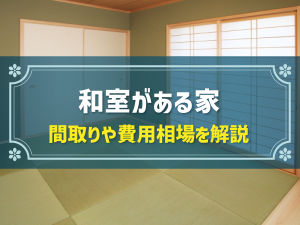




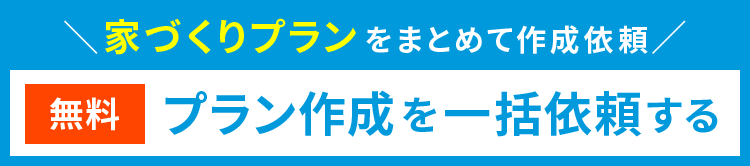
HOME4U(ホームフォーユー)無料サポートサービス
実際の見積もりを
複数比較・検討したい
簡単なスマホ入力だけで、複数のハウスメーカーの見積もりが無料でもらえる「プラン作成サービス」がおすすめ!
▷【無料】プラン作成依頼はこちら
資金計画や補助金活用の
コツが知りたい
ハウスメーカー出身のアドバイザーに、自宅から簡単に相談できる「無料オンライン相談サービス」がおすすめ!
▷【無料】オンライン相談はこちら