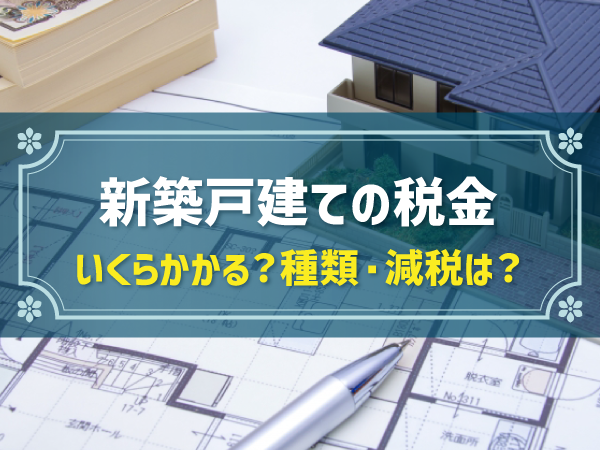
新築の戸建て住宅のマイホームを購入する際にかかる税金は以下の5つです。
- 不動産取得税
- 登録免許税・印紙税
- 消費税(土地にはかからない)
- 固定資産税
- 都市計画税
中でも、土地の購入・家の新築時にかかる「不動産取得税」と家を建てた翌年から毎年発生する「固定資産税」については、家を建てる前に必ず確認しておきましょう。
税金と聞くと、大変な金額が取られてしまうのではないかと心配になってしまうかもしれませんが、新築の住宅購入については、税金の負担を軽減するさまざまな優遇制度が味方をしてくれます。
本記事では以下の内容について、詳しく解説していきます。
- 新築戸建て住宅にかかる税金の金額目安と支払うタイミング
- 各種税金の解説と算出方法、減税・軽減措置
- その他に活用できる減税制度、固定資産税を軽減させるテクニック
家づくりにかかる税金や税金を抑えるコツを押さえ、後悔のない資金計画を立てましょう。
家の全国費用平均や予算別の目安、費用項目の内訳を知りたい方は「家を建てる費用」の記事もご覧ください。
Contents
1.新築戸建て住宅にかかる税金の「種類」一覧!現在の控除・減税の優遇措置
新築の戸建て住宅を建築・購入するときは、次の税金がかかります。
土地代に消費税はかかりません。
また、住宅取得後には、毎年次の税金がかかります。
それぞれの税金を納付する時期や納付先、適用可能な控除制度や減税措置について解説します。
1-1.不動産取得税
| 手続きが必要なタイミング | 購入から一定期間の間。都道府県によって異なるが、20~60日程度が目安。 |
|---|---|
| 支払い時期・回数 | 手続き後、納付書が送付される(半年~1年以内が目安)。支払いは一回のみ。 |
出典:東京都主税局「都税:不動産取得税 | 都税Q&A」・国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
不動産取得税とは、不動産(土地・建物)を購入・取得した際に発生する税金です。
購入・取得してから半年~1年ほど後に自治体から納付書が郵送されるため、記載されている期限までに納付しましょう。
なお、相続の場合は、不動産取得税はかかりません。ただし、生前贈与の場合は不動産取得税が発生します。
一定の条件をクリアした配偶者には、状況に応じて大きな軽減措置が適用されるため、事前に確認しておきましょう。
不動産取得税の計算方法
課税標準額(固定資産税評価額)× 税率
住宅・宅地の不動産取得税には、課税標準額にかかる軽減措置、税率にかかる軽減措置がそれぞれ適用されます。
1-1-1.宅地・新築住宅への税率の軽減:4%→3%
まず、税率についての軽減措置は以下の通りです。
| 不動産の種類 | 税率 |
|---|---|
| 土地 | 3%(軽減税率*) |
| 住宅 | 3%(軽減税率*) |
| 住宅以外の建物 | 4% |
*軽減税率は、2027年3月31日まで適用されます。
出典:東京都主税局「不動産取得税 | 税金の種類」
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
1-1-2.新築住宅の課税標準額にかかる軽減措置:1,200万円の控除
課税標準額(固定資産税評価額)を算出する際に、家屋(住宅)の場合、固定資産税評価額から1,200万円を上限に減額されます。
また、長期優良住宅の場合は控除額が上がり、最大1,300万円控除されます。
例:課税標準額(固定資産税評価額)が1,800万円の場合
課税標準額 = 1800万円-1200万円 = 600万円
出典:千葉県「不動産取得税の軽減について」
なお、この時点で課税評価額がゼロ以下になった場合、家屋(住宅)の不動産取得税は発生しません。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
1-1-3.宅地にかかる税金の減額措置
宅地には、以下2つの軽減措置が取られています。
- 住宅を建てた土地への課税標準額を1/2にする
- 不動産取得税からの減額
住宅を建てた土地への課税標準額を1/2にする
宅地への課税標準額は、1/2に軽減されるため、以下のように計算されます。
(土地の課税標準額× 1/2 )×税率3% [軽減税率適用後]
不動産取得税からの減額
また、宅地(住宅を建っている土地)には、以下のような軽減措置が適用されます。
以下の2点のうち、多いほうの金額を不動産取得税から減額
- 45,000円
- 敷地1平米当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍* × 3%
*1戸につき200平米が上限。
例:
土地の課税標準額が980万円、敷地1平米あたりの価格が12万円、住宅の床面積が100平米の場合、以下のようになります。
12万円 × 100平米 × 2 × 3% = 72万円
上記は45,000円よりも大きいため、不動産取得税から72万円が減額されます。
土地の課税標準額:980万円 × 1/2 × 3% = 14.7万円
14.7万円 - 72万円 はゼロよりも小さな数字になってしまうため、土地にかかる不動産取得税はゼロとなります。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
1-2.登録免許税・印紙税
1-2-1.登録免許税
| 手続きが必要なタイミング | 登記申請前に現金で納付。オンライン申請の場合は、電子納付が可能。 |
|---|---|
| 支払い時期・回数 | 登記時に一回のみ。 |
登録免許税は、不動産の登記にかかる税金です。
不動産の登記手続きを法務局で行う際に支払います。
新築戸建て住宅のマイホームを購入する場合には、それぞれの状況によって、以下の登録免許税が必要となります。
- 所有権の移転登記:購入した土地の登記を変更する。
- 所有権の保存登記:新築住宅の新たな登記を行う。
- 抵当権の設定登記:住宅ローンの抵当権を設定する。
上記の登記は、住宅・土地の購入において、以下のような計算方法・軽減措置が取られています(2027年3月31日まで適用)。
| 【土地・住宅購入】 | 固定資産税評価額 × 税率 = 登録免許税 |
|---|---|
| 【抵当権設定】 | 抵当権設定金額 × 税率= 登録免許税 |
| 対象 | 種別 | 通常の税率 | 軽減措置 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 所有権の移転登記 | 2% | 1.5%** |
| 住宅* | 所有権の保存登記 | 0.4% | 0.15% |
| 住宅ローン* | 抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.1% |
*個人の住宅の用に供される床面積50平米以上の家屋である必要があります。
**長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合、0.1%に軽減されます(2027年3月31日まで)。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
出典:財務省「登録免許税に関する資料」
1-2-2.印紙税
| 手続きが必要なタイミング | 契約締結時に収入印紙によって納付。 |
|---|---|
| 支払い時期・回数 | 契約時に一回のみ。 |
印紙税は契約書にかかる税金です。契約金額(購入金額)によって、税額が定められています。
土地・住宅の建築工事に関する契約書には、以下のように軽減措置が適用されます。
印紙税は、契約書を作成・発行するときに収入印紙を貼付することで納付する国税です。
土地・住宅の建築工事に関する契約書の印紙税は、2027(令和9)年3月31日までは以下のように軽減措置が適用されます。
| 契約金額 | 通常の税額 | 軽減措置 |
|---|---|---|
| 500万円超~1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 契約金額 | 通常の税額 |
|---|---|
| 500万円超~1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 6万円 |
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
出典:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
1-3.消費税(土地にはかからない)
| 手続きが必要なタイミング | 特になし。 |
|---|---|
| 支払い時期・回数 | 支払い時、一回のみ。 |
土地の購入費においては、消費税は非課税ですが、建物や外構の工事費用・引っ越し費用・土地購入の仲介手数料(不動産会社を経由する場合)にはすべて消費税がかかります。
消費税は、代金を支払うときに上乗せする形で支払う国税です。代金を受け取った事業者が後日、申告・納税します。
なお、保険料や各種税金は非課税です。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
1-4.固定資産税
| 手続きが必要なタイミング | 契約締結時に収入印紙によって納付。 |
|---|---|
| 支払い時期・回数 | 年に1度。 |
固定資産税とは不動産(土地・建物)を所有する方にかかる税金です。原則としては、以下の方法で計算されます。
固定資産税の金額=固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
1-4-1.固定資産税評価額の目安
建物の固定資産評価額は新築工事にかかった金額の50%~60%が目安と言われています。
しかし、実際には構造・設備面の充実といった要素によって点数が設定され、それを加算したものを元に計算されているため、異なるケースもあります。
また、経年劣化することも含めて計算される(経年減点補正率)ため、同様の構造・設備であれば、新築した年以降、年々評価額は減少します。
土地の固定資産税評価額は、各自治体が定める土地の評価額によって定められますが、公示地価の70%程度が目安と言われています。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
1-4-2.新築住宅:3年間、2分の1に軽減(令和6年までに新築したもの)
新築住宅には、以下のように固定資産税の減額措置が設けられています。
*2026(令和8)年3月31日までに新築したものに限る。
*期限は新築後3年間。長期優良住宅の場合は、5年間に延長されます。
新築工事費用が2,800万で、新築した住宅の固定資産税評価額が1,600万円だった場合、
1,600万円 × 1.4%× 1/2 = 11.2万円
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
出典:国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」
1-4-3.宅地:固定資産税評価額×1/6
宅地については、「小規模住宅用地」「一般住宅用地」の2つの分類に分けて軽減措置が設けられています。
| 種類 | 条件 | 評価額の減額 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200平米までの部分 | 6分の1 |
| 一般住宅用地 | 小規模住宅用地(200平米)を超える部分 | 3分の1 |
140平米の土地で、固定資産税評価額が1,200万円の場合、敷地のすべてが小規模住宅用地に該当するため、以下のようになります。
1,200万円 × 1/6 × 1.4% = 2.8万円
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
出典:つくば市公式ウェブサイト「住宅用地に対する課税標準の特例(固定資産税・都市計画税)」
1-5.都市計画税
都市計画税は市街化区域に定められている土地や家を持っている方に課せられる税金です。
都市部や市街地では、大半のエリアで課税されますが、自治体によっては課税をしなかったり、独自の軽減措置が実施されていたりするケースもあります。
都市計画税の金額 =課税標準額(固定資産税評価額)× 0.3%〔上限〕
1-5-1.都市計画税の軽減措置
現在、新築戸建て住宅には軽減措置はありません。
土地は以下のような軽減措置が取られています。
| 種類 | 条件 | 評価額の減額 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200平米までの部分 | 3分の1 |
| 一般住宅用地 | 小規模住宅用地(200平米)を超える部分 | 3分の2 |
新築工事費用が3,000万で、新築した住宅の固定資産税評価額が1,800万円。また、140平米の土地で、固定資産税評価額が1,200万円の場合、以下のようになります。
住宅: 1,800万円 × 0.3% = 5.4万円
土地: 1,200万円 × 1/3 × 0.3% = 1.2万円
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
出典:つくば市公式ウェブサイト「住宅用地に対する課税標準の特例(固定資産税・都市計画税)」
「自分の要望を反映したら、予算相場はどれくらい?」
「自分はどれくらいの予算に設定したらいい?」
と、マイホームの資金計画についてお悩みの方は、ぜひ無料のHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスをご利用ください。
あなたの予算・要望に合ったハウスメーカー・工務店の実際の住宅プラン(資金計画含む)を比較できるので、具体的な費用イメージを持ちながら資金計画が立てられます。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!

10年間の固定資産税・都市計画税シミュレーション!
いつから、いくらかかる?
シミュレーションの条件は以下の通りです。
- 長期優良住宅を新築。新築工事費用が2,800万で、新築した住宅の固定資産税評価額が1,600万円だった場合
- 140平米の土地で、固定資産税評価額が1,200万円の場合
| 居住年 | 種類 | 金額 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 初年度 | 固定資産税 | 支払いは発生しません。 | |
| 都市計画税 | |||
| 2年目 | 固定資産税 | 14.0万円 | 20.0万円 |
| 都市計画税 | 6.0万円 | ||
| 3年目 | 固定資産税 | 14.0万円 | 20.0万円 |
| 都市計画税 | 6.0万円 | ||
| 4年目 | 固定資産税 | 14.0万円 | 20.0万円 |
| 都市計画税 | 6.0万円 | ||
| 5年目 | 固定資産税 | 14.0万円 | 20.0万円 |
| 都市計画税 | 6.0万円 | ||
| 6年目 | 固定資産税 | 14.0万円 | 20.0万円 |
| 都市計画税 | 6.0万円 | ||
| 7年目 | 固定資産税 | 25.2万円 | 31.2万円 |
| 都市計画税 | 6.0万円 | ||
| 8年目 | 固定資産税 | 25.2万円 | 31.2万円 |
| 都市計画税 | 6.0万円 | ||
| 9年目 | 固定資産税 | 25.2万円 | 31.2万円 |
| 都市計画税 | 6.0万円 | ||
| 10年目 | 固定資産税 | 25.2万円 | 31.2万円 |
| 都市計画税 | 6.0万円 | ||
| 合計 | 224.8万円 | ||
なお、それぞれの計算シミュレーションは以下の通りです。
【建物の固定資産税】
2年目~6年目の各年:1,600万円* × 1.4% × 1/2 = 11.2万円
7年目~10年目の各年:1,600万円* × 1.4% = 22.4万円*
【土地の固定資産税の計算シミュレーション】
2年目~10年目の各年:1,200万円 × 1/6 × 1.4% = 2.8万円
【建物の都市計画税の計算シミュレーション】
2年目~10年目の各年:1,600万円* × 0.3% = 4.8万円
【土地の都市計画税の計算シミュレーション】
2年目~10年目の各年:1,200万円 × 1/3 × 0.3% = 約1.2万円
*建物について、経過年数に応じた固定資産税評価額の減額は加味していません。実際は建物の固定資産税評価額は3年に一度見直され、経過年数に応じて価格も下がります。(一般的に10年で50%程度の価格に下がるといわれています)
建物の固定資産税の減額措置(税額が1/2になる措置)は、長期優良住宅の場合は5年間です。それ以降は減額措置がなくなるため、固定資産税の負担が大きくなる傾向があります。
しかし、実際には建物自体の固定資産税評価額が経過年数によって下がるため、そのため、上記のシミュレーションよりも税額は下がるケースが多くなります。
なお、先にお伝えした通り、住み始めた初年度には、固定資産税・都市計画税の支払いは発生しません。
2.その他に活用できる税金が減税される制度
新築購入した家や土地など、不動産に対して支払う税金以外にも、私たちは所得税や住民税など税金を支払っています。
また、親や祖父母から家を建てる資金の提供を受ける場合は、贈与税が発生します。
この章では、住宅を建てることで、受けられる税金の優遇について、幅広く解説します。
2-1.住宅ローン減税(住宅ローン控除)による「所得税」の減税
住宅ローン減税(住宅ローン控除)は、毎年末の住宅ローン残高に応じて、所得税の減税を行うものです。
なお、所得税で控除しきれなかった分は、一部住民税からも控除することが可能です。
消費税増税によって生まれた制度ですが、2024年3月時点では2025年(令和7年)12月31日までに入居する場合も住宅ローン減税制度を利用できることが決まっています。
基本的にSDGsにならい、環境に配慮される家であればあるほど、手厚い優遇措置を受けることができます。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)の特徴まとめ
- 減税(控除)の対象
- 所得税(控除額が余った場合は住民税も一部控除)
- 減税(控除)額
-
ローン残高(年末時点)の0.7%を所得税から控除
ローン残高としてカウントされる限度額 住宅の種別 2024年に入居 2025年に入居 長期優良住宅・低炭素住宅*1 4,500万円
5,000万円4,500万円 ZEH水準の省エネ住宅*1 3,500万円
4,500万円3,500万円 省エネ基準適合住宅*1 3,000万円
4,000万円3,000万円 その他の住宅*2 0円(2023年までに新築の建築確認をした場合は2,000万円) *1 下段は子育て世帯・若者夫婦世帯
*2 2025~2026年に「その他の住宅」に入居した場合、控除期間が10年間となります。 - 適用期間
- 2025年までに入居の場合、控除期間は最長13年間。
ただし、その他の住宅において本制度が適用される場合は、控除期間は最長10年間。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
出典:国土交通省「![]() 令和6年度 国土交通省税制改正概要」
令和6年度 国土交通省税制改正概要」
2-2.ZEH住宅・長期優良住宅・低炭素住宅への軽減措置まとめ
ZEH住宅・長期優良住宅・低炭素住宅を推奨するため、以下のような税金の優遇措置があります。
- 住宅ローン控除における減税額の増額(「2-1.住宅ローン減税(住宅ローン控除)による「所得税」の減税」を参照)
- 住宅ローン控除における減税額の増額(「2-1.住宅ローン減税(住宅ローン控除)による「所得税」の減税」を参照)
- 登録免許税の軽減
- 不動産取得税の軽減
- 固定資産税の減税期間の延長
- 住宅ローン控除における減税額の増額(「2-1.住宅ローン減税(住宅ローン控除)による「所得税」の減税」を参照)
- 登録免許税の軽減
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
各税金の優遇措置・今活用できる補助金などの情報についてもっと知りたい方は、以下の関連記事も合わせてご参照ください。
2-3.親・祖父母からの住宅資金贈与にかかる「贈与税」の減税
住宅購入に対する資金提供には、通常の基礎控除額(年間110万円まで)のほか、特別な非課税措置が適用されます。
- 減税(非課税)の対象
- 贈与税(親・祖父母から)
- 減税(非課税)額
-
住宅の種類 非課税額の上限 省エネ等住宅 1,000万円 それ以外の住宅 500万円 - 適用期間
- 2022年1月1日~2025年12月31日まで
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
【自分の予算に合ったハウスメーカー・工務店を効率よく探したい方へ】
全国には数万社のハウスメーカーがあるといわれています。
手当たり次第に調べだすと、無駄な時間や労力をかけてしまうので注意してください。
おすすめは、まず無料のHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスをご利用いただくこと。
- スマホやパソコンからあなたに合ったハウスメーカー・工務店がわかる!
- 家づくりの要望・情報を専任コーディネーターが電話で整理!
- 実際の住宅プランを最大5社分比較できる!
資金計画でよくあるのが「実際に見積もりを出してもらったら予算と合わず、はじめからプランを立て直した」という失敗です。
HOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスなら、専任コーディネーターによる複数ハウスメーカーへの資金計画作成依頼のほか、注文住宅のプロであるアドバイザーに「予算の立て方」や「補助金制度の活用方法」などをオンライン上から相談することもできます。
完全無料、営業トークは一切ないので、ぜひお気軽にご活用ください。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!

相続税対策として新築住宅を建てる
家を建てるのはマイホームが必要なときだけではありません。
相続税対策として新築住宅を建てることがあります。
現金として財産を残すと、額面金額で相続税額が計算されます。
遺産が1億円なら、1億円に対して相続税額を計算しなくてはいけません。
一方、不動産として財産を残す場合、路線価評価額や固定資産評価額で相続税額が計算されます。
路線価評価額や固定資産評価額は、いずれも実際の不動産の価格よりも低いため、算出される相続税額も低くなることが一般的です。
一般的に路線価評価額は公示価格の80%ほど、固定資産評価額は公示価格の70%ほどとされるため、相続税の課税対象額も70~80%ほどになると考えられます。
相続人の税負担を軽減するためにも、現金ではなく不動産として遺すことを検討できるでしょう。
また、宅地として遺す場合、相続人が配偶者もしくは同居家族などの要件を満たすと、小規模宅地等の特例が適用されます。
小規模宅地等の特例が適用されると、相続税の課税対象額に含める土地の価格を最大80%減額できます。
3.新築戸建て住宅にかかる税金はいくら?相場をシミュレーション
住宅を建てるときは、住宅建築にかかる費用だけでなく、税金についても事前に確認しておくことが大切です。
ここでは、以下の条件で注文住宅を建てる際の税金シミュレーションしてみましょう。
- 土地1,400万円(40坪)
- 建物3,000万円(本体価格、建築面積30坪)
- 土地の固定資産税評価額900万円
- 建物の固定資産税評価額2,000万円(長期優良住宅)
- 住宅ローンの借入金額:2,500万円
以下より、家を建てるときと建てた後に分けて解説します。
3-1.家を建てるときにかかる税金
家を建てるときには、次の税金がかかります。
| 税金項目 | 費用 | 支払時期 |
|---|---|---|
| 土地の不動産取得税 | 13.5万円 | 自治体から納付書が届いたとき |
| 建物の不動産取得税 | 21万円 | 不動産取得税時 |
| 登録免許税 | 15.5万円 | 登記時 |
| 消費税(土地代以外) | 300万円 | 購入時 |
| 印紙税 | 4万円 | 契約締結時 |
| 小計 | 354万円 | |
以下より1つずつ見ていきましょう。
3-1-1.土地の不動産取得税
土地の不動産取得税は本来、固定資産税評価額(今回は900万円)に不動産取得税率(4%)をかけて税額を求めます。
しかし、2027年3月31日までの特例措置では、取得した土地の価格に1/2をかけ、軽減税率3%をかけて税額を求めるため、大幅な減税が可能です。
土地の不動産取得税額=900万円×1/2×3%=13.5万円
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
3-1-2.建物の不動産取得税
建物の不動産取得税は本来、固定資産税評価額(今回は2,000万円)から1,200万円の特別控除額を差し引き、住宅用の不動産取得税率(3%)をかけて税額を求めます。
しかし、2026年3月31日までの特例措置で、長期優良住宅の特別控除額は1,300万円のため、以下のように計算できます。
建物の不動産取得税額=(2,000万円ー1,300万円)×3%=21万円
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
3-1-3.登録免許税
土地を購入したとき(売買による移転登記)にかかる登録免許税額は土地の固定資産税評価額の2%、建物を新築・取得したときは建物の固定資産税評価額の0.4%です。
しかし、2027年3月31日までの特例措置で、土地に関しては1.5%、建物(長期優良住宅)に関しては0.1%のため、以下のように計算できます。
- 土地の登録免許税額(所有権保存登記)=900万円×1.5%=13.5万円
- 建物の登録免許税額(所有権保存登記)=2,000万円×0.1%=2万円
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
3-1-4.消費税(土地代以外)
消費税は土地代以外にかかりますが、ここでは建物本体代以外は発生しなかったとして計算してみましょう。消費税率は10%です。
消費税額(建物)=3,000万円×10%=300万円
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
3-1-5.印紙税
不動産譲渡契約書と建築請負契約書を作成したときは、それぞれ印紙税が必要です。
建物本体以外に代金が発生しなかった場合、通常、土地代・建物本体代に対してそれぞれ2万円の印紙税額が課せられますが(1,000万~5,000万円の場合)、2027年3月31日までの特例措置では以下のように軽減されます。
- 不動産譲渡契約書:1万円(土地代1,400万円に対して)
- 建築請負契約書:1万円(建物本体代3,000万円に対して)
また、住宅ローンを組むときには、「金銭消費貸借契約書」を作成します。
この場合も印紙税が課せられますが、特例措置の対象ではないため、通常の印紙税額が必要です。
金銭消費貸借契約書:2万円(借入金額2,500万円に対して)
以上が、家を建てるときにかかる税金のシミュレーションです。
登録免許税は登記時、消費税は購入時、印紙税は契約締結時にそれぞれ支払いますが、不動産取得税のみ後で自治体から納付書が届く点に注意が必要です。
スムーズに支払うためにも、前もって準備しておきましょう。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
3-2.家を建てた後にかかる税金
家を建てた後には、固定資産税と都市計画税が毎年かかります。
固定資産税と都市計画税は、いずれもその年の1月1日時点で所有している場合に課せられる税金です。
1月1日に登記手続きはできない(祝日のため法務局は休業)ため、取得した翌年から課せられます。
なお、住み始めた翌年には、次の税額がかかるとシミュレーションできます。
| 土地の固定資産税 | 2.1万円 |
|---|---|
| 建物の固定資産税 | 14万円 |
| 土地の都市計画税 | 0.9万円 |
| 建物の都市計画税 | 6万円 |
| 小計 | 23万円 |
3-2-1.土地の固定資産税
固定資産税率は1.4%ですが、住宅用地の特例措置が適用されて1/6を乗じるため、次のように土地の固定資産税額を計算できます。
土地の固定資産税額=900万円×1/6×1.4%=2.1万円
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
3-2-2.建物の固定資産税
建物の固定資産税においては、2026年3月31日までの特例措置が適用されて、3年間(長期優良住宅は5年間)は1/2になります。
建物の固定資産税額=2,000万円×1.4%×1/2=14万円
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
3-2-3.土地の都市計画税
都市計画税率は0.3%ですが、住宅用地の特例措置が適用されて1/3を乗じるため、次のように土地の都市計画税額を計算できます。
土地の都市計画税額=900万円×1/3×0.3%=0.9万円
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
3-2-4.建物の都市計画税
建物の都市計画税率においては、特例措置はないため、以下のように計算します。
2,000万円×0.3%=6万円
建物の固定資産税の特例措置は5年間(長期優良住宅以外は3年間)で終了するため、6年目以降(長期優良住宅以外は4年目以降)に本来の税額に戻ります。
いきなり増えたように感じることもあるので、注意が必要です。
ただし、その頃には建物の評価額も少しは下がっているため、建物の固定資産税額・都市計画税額が減っていると予想されます。
前もって税額をシミュレーションし、準備しておきましょう。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
4.【住宅の新築前に必見!】固定資産税を軽減させる対策テクニック
戸建て住宅のマイホームを新築する前に、毎年発生する固定資産税を軽減させる対策テクニックを使って、かしこく計画を立てていきましょう。
4-1.床面積を減らす
固定資産税は床面積を小さくすることで、建物の固定資産税評価額を下げることができます。
床面積にカウントされない空間を上手に使うことが大切です。具体的には、以下のような工夫を行いましょう。
スキップフロアやロフトの場合、天井高1.4m以下であれば固定資産税の対象にならないため、用途に合わせて、上手に活用することが大切です。
また、ビルトインガレージの場合は、建物全体の床面積の1/5以下に抑える必要があります。
4-2.1月1日時点で空き地であることを避ける
固定資産税は、1月1日時点の土地の状況に合わせて、課税額が決まります。
つまり、1月1日時点で、まだ建物が建っていない場合は、更地として見なされ、住宅用地としての軽減措置を受けることができません。
土地:1,000万円×1.4%(標準税率)= 14万円
建物:建っていないため、なし。
なお、建て替えの場合は、別途救済措置がありますが、一定の条件があり、手続きも必要です。必ず各自治体の窓口やHPを確認してみてください。
4-3.クレジットカード払いでポイントを貯める
自治体によっては、固定資産税をクレジットカード払いで納付することが可能です。
クレジットカード払いをすることで、以下のようなメリットもあります。
- クレジットカードのポイントを貯めることができる
- クレジットカードのルールに沿って、支払回数を決めることができる
ただし、別途手数料がかかるため、各自治体のHPを通じて、事前に確認しておきましょう。
また、現在口座の自動引き落としにしている場合は、そのまま引き落とされてしまいます。クレジットカードで支払いたい方は、一度自動引き落としを停止し、納付書が手元に届くように手続きをする必要があるため、注意してください。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
5.注文住宅に活用できる補助金制度もチェックしておこう
注文住宅を建てるときに利用できる補助金制度があります。補助金制度は返還不要のため、受給できればその分、コストを抑えられる点がメリットです。
- 子育てエコホーム支援事業
- 給湯省エネ2024事業
- 先進的窓リノベ2024事業
それぞれの制度概要や補助金額、申込方法について見ていきましょう。
5-1.子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業とは、子育て世帯と若者夫婦世帯が長期優良住宅かZEH住宅を建築・購入するときに利用できる制度です。
補助金額は以下をご覧ください。
| 新築として建築・購入する住宅の種類 | 補助金額 |
|---|---|
| 長期優良住宅 | 最大100万円 |
| ZEH住宅 | 最大80万円 |
なお、子育て世帯と若者夫婦世帯の定義については、以下をご覧ください。
| 子育て世帯 | 2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯。ただし、2024年3月末までに着工する場合は、2004年4月2日以降に出生した子を有すること |
|---|---|
| 若者夫婦世帯 | 申請時点で夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降の生まれであること。ただし、2024年3月末までに着工する場合は、いずれかが1982年4月2日以降の生まれであること |
子育てエコホーム支援事業は、2024年3月中下旬~遅くとも2024年12月31日までに申請することが必要です。
ただし、予算上限に達すると、期間中であっても受付が終了するため、条件を満たしている場合は早めに行動してください。
なお、申請手続きは住宅所有者ではなく、エコホーム支援事業者が行います。
エコホーム支援事業者に登録されているハウスメーカー・工務店に早めに相談するようにしましょう。
また、一定の要件を満たしてエコリフォームを実施するときにも、補助金を受給できることがあります。
リフォームに関しては補助金の上限額は60万円で、子育て世帯と若者夫婦世帯を含むすべての世帯が対象となります。
5-2.給湯省エネ2024事業
給湯省エネ2024事業とは、高効率給湯器を導入するときに利用できる制度です。
補助金額は以下をご覧ください。
| 設置する給湯器 | 補助金額 |
|---|---|
| ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | 8万円/台 |
| 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器) | 10万円/台 |
| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 18万円/台 |
給湯器の性能によっては、給付金額が最大5万円/台、加算されます。
また、給湯器を設置する際に電気蓄熱暖房機を撤去する場合は10万円/台、電気温水器を撤去する場合は5万円/台が加算されます。
対象世帯は特に決まっていないため、応募しやすいのではないでしょうか。
なお、給湯省エネ2024事業は、2024年3月中下旬~遅くとも2024年12月31日までに申請することが必要です。
子育てエコホーム支援事業と同じく、予算上限に到達すると受付を終了するため、条件を満たしている場合は早めに行動するようにしてください。
申請手続きは、給湯省エネ2024事業の登録事業者を通して行います。登録事業者を通さずに設置した場合は補助金の対象外となるため、本制度を利用するときは登録事業者か確認してから設置を依頼しましょう。
5-3.先進的窓リノベ2024事業
先進的窓リノベ2024事業とは、窓ガラスを断熱性能の高いものに交換するときに利用できる制度です。
補助金額は最大200万円です。対象となる工事は以下をご覧ください。
- ガラス交換
- 内窓設置
- 外窓設置
- ドア交換
ただし、ドア交換だけを実施するときは、先進的窓リノベ2024事業の対象とはなりません。
ガラス交換や外窓設置と同時にドア交換するときは、本事業の申請をしましょう。
また、先進的窓リノベ2024事業は築1年が経過した既存住宅が対象です。
新築住宅を建築・購入した後で、断熱性能の高い窓にリフォームしたいときに活用してください。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
6.購入後の税金に関しても相談できるパートナーを探す方法
新築住宅の税金は、購入時だけでなく、毎年かかる固定資産税も考えて、検討しなくてはいけません。
そのように、新築住宅の購入後のことまで、親身になってくれるハウスメーカーと契約を結ぶには、実績と経験を積み重ねた信頼ある会社であるかを見極める必要があります。
しかし、信頼できるハウスメーカーかどうかを判断しながら、自分に合ったハウスメーカーを探すのは、とても難しい作業です。
そこでおすすめなのが、HOMU4U家づくりのとびらの2つの無料サポートサービスです。
まとめ
新築戸建て住宅のマイホームを購入する際には、さまざまな税金がかかります。
購入時だけかかるものだけでなく、購入後から課税される固定資産税・都市計画税などについても、しっかりと組み込みながら、費用計画を行うことが大切です。
この記事のポイント
ファミリー向けの新築住宅(土地40坪を1,400万円で購入し、建築面積30坪の家を3,000万円(本体価格)で新築)の場合、以下の通りです。
| 購入時にかかる税金の総額 | 381.1万円 |
|---|---|
| 住み始めて2年目以降、毎年かかる税金 | 23万円 |
詳細は「3.新築戸建て住宅にかかる税金はいくら?相場をシミュレーション」をご確認ください。
| 流れ | 支払う税金 |
|---|---|
| 土地購入時 | 土地の不動産取得税 |
| 土地の登録免許税 | |
| 売買契約書の印紙税 | |
| 仲介手数料にかかる消費税* | |
| 新築工事前 | 住宅ローンの印紙税 |
| 工事契約の印紙税 | |
| 家の引き渡し後 | 建物の登録免許税 |
| 建物の不動産取得税 | |
| 住み始めて2年目~ | 土地・建物の固定資産税 |
| 土地・建物の都市計画税 |
詳細は、「1.新築戸建て住宅にかかる税金の「種類」一覧と控除・減税の優遇措置」にて解説しています。
- 不動産取得税
- 登録免許税・印紙税
- 消費税(土地にはかからない)
- 固定資産税
- 都市計画税
上記の税金には、新築住宅や住宅用地(宅地)に対して、軽減措置が設定されています(消費税以外)。
具体的な軽減措置や税金の計算方法については「1.新築戸建て住宅にかかる税金の「種類」一覧と控除・減税の優遇措置」の各項目をご参照ください。
新築住宅の固定資産税を軽減させるために、以下のようなテクニックがあります。
- 床面積を減らす
- 1月1日時点で空き地であることを避ける
- クレジットカード払いでポイントを貯める
より具体的な方法について知りたい方は、「4.節税するなら毎年発生する固定資産税に注目!軽減テクニック」をご覧ください。
家を建てる費用や予算別のイメージまとめ

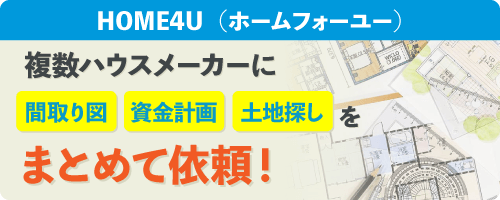


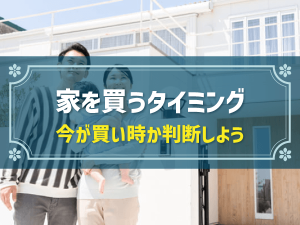
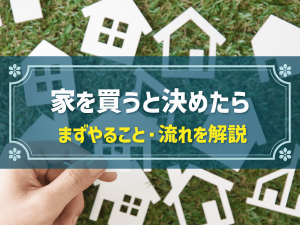



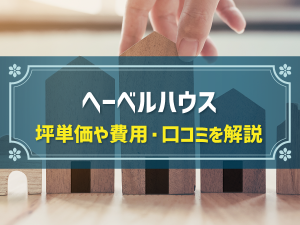
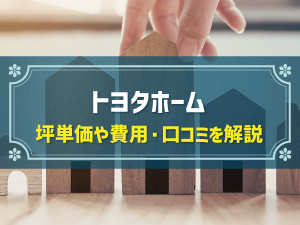


無料サポートサービスのご紹介
あなたの家づくりの検討状況や検討の進め方にあわせて、ご活用ください!
実際の建築プランを複数みて、
比較・検討したい
複数のハウスメーカーの建築プランが、かんたんな入力だけで、無料でもらえる「プラン作成サービス」がおすすめ!
▷【無料】プラン作成依頼はこちら
費用や、ハウスメーカー選びの
コツを詳しく直接聞きたい
ハウスメーカー出身のアドバイザーに自宅から簡単に相談できる「無料オンライン相談サービス」がおすすめ!
▷【無料】オンライン相談はこちら