
ペアローンとは、夫婦や親子などで住宅ローンを組む住宅ローンの1つです。
「借入条件を、夫婦それぞれで決められる」「団信に2人とも加入できる」「それぞれが住宅ローン控除を受けられる」といったメリットがある反面、以下のようなデメリットもあるため、契約前に把握しておく必要があります。
- 手数料が2人分かかる
- どちらかの収入が減ると返済が苦しくなる
- 贈与税が発生するケースがある
なお、同じく夫婦や親子などで住宅ローンを組む方法に「収入合算」という選択肢もあります。
似て非なるものなので、それぞれの特徴、メリット・デメリットを事前に確認したうえで、自分たちに合った住宅ローンを選択しましょう。
- ペアローンの特徴
- ペアローンと収入合算との違い
- ペアローンと収入合算のメリット・デメリット
ペアローンが適しているケースと収入合算が適しているケースについてもお伝えするので、ぜひ最後までご覧いただき、理想のマイホーム購入に向けた資金調達の参考にしてください。

田宮 有莉
大手金融機関に8年勤務。(FP、ビジネス会計、ビジネス法務等の資格を保有)自身が家を購入したことで住宅、家づくり、インテリアのジャンルに興味を持ち、SNSで住宅やインテリアについて発信する傍ら、ライターとして活動。現在2児の母。
住宅ローンの種類について全体像を把握しておきたい方は「住宅ローンの種類一覧」もご覧ください。
1.ペアローンとは
マイホームの購入資金として、住宅ローンを利用する方も多いでしょう。
借入額によって住宅購入予算が変わる場合もあるため、住宅購入を検討する際に、まず住宅ローンの借入可能額について考える方も少なくありません。
より多くの借入額を検討している方には、夫婦や親子で住宅ローンを組む「ペアローン」も選択肢に入るでしょう。
ここではペアローンの特徴および、ペアローンと似た借入方法である「収入合算」との違いを解説します。
1-1.ペアローンは2人が債務者になる住宅ローン
ペアローンは一定の収入がある親子や夫婦が、1つの物件に対しそれぞれ借り入れをする住宅ローンです。
1つの物件を購入するために2つのローン契約を行い、お互いが相手の連帯保証人になる点が大きな特徴といえます。
単独で借り入れるローンでは借入額が足りない、2人で協力して資金調達をしたいと考えているのであれば、ペアローンは有力な選択肢の1つとなるでしょう。
ペアローンで購入した住宅は共有名義となり、持分は多くの場合、購入金額の負担割合によって決まります。
以下の例を見てみましょう。

仮に5,000万円の住宅購入にあたり夫が3,000万円(住宅ローン借入2,000万円+自己資金1,000万円)、妻が2,000万円(住宅ローン借入1,500万円+自己資金500万円)を負担したとすると、持分割合は夫が5分の3で妻が5分の2となります。
1-2.収入合算との違い
収入合算は、夫婦や親子といった2人の収入を合算し、1つの住宅ローンを契約する仕組みです。
ペアローンと収入合算の違いを以下で確認しましょう。
| 項目 | ペアローン | 収入合算※ | |
|---|---|---|---|
| 連帯保証型 | 連帯債務型 | ||
| 契約者 | 夫・妻 | 夫 | |
| ローン本数 | 2本 | 1本 | |
| 連帯保証人 | お互いがお互いの連帯保証人 | 妻 | 妻が連帯保証人 |
| 事務手数料 | 2本分 | 1本分 | |
| 団信への加入 | 夫・妻 | 夫 | 夫 ※夫婦連生団信であれば妻も加入可能 |
| 住宅ローン控除 | 夫・妻 | ||
| 所有権 | |||
※主債務者を夫、収入合算者を妻とする場合
ペアローンは夫と妻がそれぞれ住宅ローン契約をするため、お互いに団信(団体信用生命保険)加入や住宅ローン控除の利用ができます。
ただし借り入れに際しては、2つのローンを契約するための2人分の手数料がかかります。
一方、収入合算には「連帯保証型」と「連帯債務型」があります。
| 連帯保証型 | 夫婦・親子のどちらかが債務者となり、もう一方が連帯保証人となる方法 |
|---|---|
| 連帯債務型 | 夫婦・親子のどちらかが主となる債務者となり、もう一方が連帯債務者となる方法 |
「連帯保証型」は、主債務者がメインとなり1本のローンを借り入れる仕組みです。
収入合算者は、連帯保証人となります。
仮に夫を主債務者、妻を連帯保証人として4,000万円の住宅ローンを借り入れた場合、何らかの理由で夫が返済不能になったときには妻が残債を返済します。
なお、団信への加入や住宅ローン控除は、主債務者のみが利用可能です。
一方の「連帯債務型」は、片方が主債務者、もう片方が連帯債務者として住宅ローンを借り入れる仕組みとなります。
お互いが住宅ローン控除を利用できるだけでなく、どちらにも所有権がえられる点が特徴です。
仮に連帯債務型で3,000万円を借り入れた場合、夫と妻の2人でローンを返済していかなければなりません。
どちらか片方が返済不能になったときには、残った1人が2人分の返済を続けます。
ちなみに、親子で住宅ローンを組む際には「リレーローン」も選択肢の1つに入るでしょう。

FP
田宮有莉
住宅ローンを組む際、選択肢の一つとして提案されることが多いペアローンや収入合算。共働き世帯が増えた現在、活用を検討している方も多いと思います。
実際に住宅を購入した世帯の4割がペアローンを選んでいるというデータもあり、メジャーな手段になっているといえるでしょう。
住宅ローン控除や借入額の上限を考えるとメリットが多いように思われますが、次章以降記載の通りデメリットもあります。それぞれのメリット・デメリットを考慮したうえで、自分たちの収入に合ったローン返済方法を選びましょう。
「自分の要望を反映したら、予算相場はどれくらい?」
「自分はどれくらいの予算に設定したらいい?」
と、資金計画についてお悩みの方は、ぜひ無料のHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスをご利用ください。
あなたの予算・要望に合ったハウスメーカー・工務店の実際の住宅プラン(資金計画含む)を比較できるので、具体的な費用イメージを持ちながら資金計画が立てられます。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
2.ペアローンのメリット
夫婦で住宅ローンを借りたいと考えた時に、ペアローンと収入合算のどちらを選ぶかで悩む方も多いのではないでしょうか。
最適な住宅ローンを選ぶには、それぞれの概要とあわせて、メリット・デメリットを知っておくことが重要です。
ここでは、ペアローンの3つのメリットを紹介します。
- 借入条件をそれぞれ決められる
- 団体信用生命保険(団信)に2人とも加入できる
- それぞれが住宅ローン控除を受けられる
2-1.借入条件をそれぞれ決められる
ペアローンは、夫と妻がそれぞれローン契約を結びます。
そのため収入額や借入額に合わせて、金利タイプや返済期間などを夫婦それぞれで選択することが可能です。
仮に夫が3,500万円、妻が2,000万円のローンをそれぞれ組む場合、夫は借入額が多いため返済期間25年、妻は借入額が少ないため返済期間15年と設定することもできます。
また夫は変動金利、妻は固定金利など異なる金利プランを選べば、将来金利が変動したときに受ける影響の軽減を図れるでしょう。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
2-2.団信(団体信用生命保険)に2人とも加入できる
ペアローンであれば、夫と妻双方で「団信(団体信用生命保険)」の加入が可能です。
団信とは、契約者が死亡または高度障害状態となったときに、住宅ローン残債が保険によって返済される保険制度です
団信への加入がなければ、ペアローン返済中に夫か妻のどちらかが死亡、または高度障害状態により返済不能になったとき、残された家族がすべての残債を返済する必要があります。
残債額によっては毎月の返済額が大幅に増え、返済を継続できないといった事態に陥る可能性もあるでしょう。
その点、団信加入が可能なペアローンであれば、万が一のことがあった債務者のローン返済は免除になります。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
2-3.それぞれが住宅ローン控除を受けられる
夫と妻のそれぞれが住宅ローン控除を受けられるのも、ペアローンの魅力です。
住宅ローン控除とは、一定の条件のもと住宅ローン等の年末残高の合計額から計算した金額を、各年分の所得税額から控除できる制度です。
控除の適用期間は、10年または13年の長期にわたります。
住宅ローン控除を受けると、所得税の節税が可能です。ペアローンは、単独ローンより大きな節税効果があるというメリットがありますよ。

FP
田宮有莉
単独ローンでは借入が厳しい場合でも、ペアローンにすれば上限額が上がります。また、夫と妻それぞれが住宅ローン減税を受けられるのも、大きなメリットです。
団信も両者加入が可能です。ただし、片方の債務者に万が一のことがあった際、その債務者のローン返済は免除されますが、自分のローン返済義務は残るので注意が必要です。
3.ペアローンのデメリット

ペアローンで考えられるデメリットは、主に次の3点です。
- 契約にかかる諸費用の負担が増える
- どちらかの収入が減ると返済が苦しくなる
- 贈与税が発生するケースがある
住宅ローンは一般的に金額が大きく、借入期間も長期にわたります。
借入後に後悔しないよう、デメリットもしっかりと確認しておきましょう。
3-1.契約にかかる諸費用の負担が増える
ペアローンのデメリットとして、契約にかかる諸費用の負担が増える点が挙げられます。
ペアローンの場合、夫と妻それぞれが住宅ローンを契約するため、契約にかかる諸費用が単独ローンと比べて多くなります。
住宅ローンの借入で費用負担が増える可能性がある諸費用は、以下のとおりです。
- 融資事務手数料
- 印紙代
- 司法書士への報酬
- 保証会社事務手数料
具体的な手数料額は契約によって異なりますが、100万円を超えるケースも少なくありません。
2人分となれば、さらに金額は上がります。
ペアローンの利用を考えているのであれば、手数料に必要な資金をしっかりと準備しておくことが重要です。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
3-2.どちらかの収入が減ると返済が苦しくなる
ペアローンには、どちらかの収入が減ると返済が苦しくなるデメリットもあります。
- 産休や育休の取得
- 病気やケガ
- 転職や退職
住宅ローンは通常、20年や30年といった長期で借り入れます。
その間の収入の変動をゼロにするのは、簡単ではありません。
ペアローンの返済を滞りなく続けるには、一時的に収入が減ったときに補てんできるような資金を用意しておくことが重要です。
また、多少収入が減っても、借入を返済可能な額に留めることも念頭に置いておきましょう。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
3-3.贈与税が発生するケースがある
ペアローンのデメリットとして、贈与税が発生する可能性も挙げられます。
贈与税とは、贈与により個人から財産を取得したときにかかる税金です。
年間110万円を超える贈与が発生したときには、たとえ夫婦間の財産の移動で合ったとしても贈与税を納めなければなりません。
ペアローンにおいて贈与が発生する主なケースには、以下が挙げられます。
- 返済中に夫婦で借り換えを行ったとき
- 住宅ローンの負担割合と登記している所有割合が異なるとき
ペアローンを利用していれば、夫または妻が何らかの理由で返済できなくなったときに、代わりに返済をすることもあるでしょう。この返済額が年間110万円を超えると、贈与税の対象となる可能性があります。
また、ペアローンにおける所有権の持分は、一般的に購入金額の負担割合で決定しますが、場合によっては、負担割合以外の割合で、所有権の登記が行われるケースもあるようです。
負担割合よりも持分割合が多いときには、贈与税の納税義務が発生する可能性があります。
出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
全国には、数万社のハウスメーカーがあるといわれています。
各社で坪単価や建築費用相場は異なるため、手当たり次第に調べ始めると、無駄な時間や労力をかけてしまうので注意してください。
おすすめは、まず無料のHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスをご利用いただくことです。
- スマホやパソコンからあなたに合ったハウスメーカー・工務店がわかる!
- 家づくりの要望・情報を専任コーディネーターが電話で整理!
- 実際の住宅プラン・資金計画を最大5社分比較できる!
資金計画でよくあるのが「実際に見積もりを出してもらったら予算と合わず、はじめからプランを立て直した」という失敗です。
HOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスなら、専任コーディネーターによる複数ハウスメーカーへの資金計画作成依頼のほか、注文住宅のプロであるアドバイザーに「予算の立て方」や「補助金制度の活用方法」などをオンライン上で相談できます。
完全無料、営業トークは一切ないので、ぜひお気軽にご活用ください。
4.収入合算のメリット・デメリット
2人での住宅ローンの借入を検討しているのであれば、収入合算におけるメリット・デメリットも押さえておきましょう。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
4-1.【メリット1】手数料を抑えられる
収入合算は「連帯債務型」も「連帯保証型」も、契約する住宅ローンは1本です。
そのため、契約に必要な融資事務手数料、印紙代、司法書士への報酬、保証会社事務手数料などの諸費用が1本分しかからず、初期費用を抑えた住宅ローンの借入を目指せます。
2人分の諸費用がかかるペアローンと比較してコストを抑えられる点は、収入合算の大きなメリットといえるでしょう。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
4-2.【メリット2】連帯債務型なら夫婦それぞれが住宅ローン控除の対象
収入合算のうち「連帯債務型」であれば、夫婦それぞれが住宅ローン控除の対象となります。
連帯債務型のローン契約は1本であるものの、妻と夫の両方が返済義務を負うため、住宅ローン控除もそれぞれが対象となります。
連帯債務型を選択しており住宅控除の受給要件をクリアしている方は、住宅ローン控除を活用しましょう。
なお、住宅ローン控除を受けるには、初年度に確定申告をする必要があります。
申告には以下の書類が必要なため、前もって用意しておくと手続きもスムーズに行えるでしょう。
| 書類の種類 | 入手場所 |
|---|---|
| 建物や土地の登記事項証明書 | 住所地管轄の法務局 |
| 住宅借入金特別控除額の計算明細書 | 国税庁ウェブサイト・税務署 |
| 不動産売買契約書の写し | 不動産会社 |
| 住宅ローン年末残高証明書 | ローンを借り入れている金融機関 |
必要書類や手続きに不安がある方は、住宅ローンを借り入れている金融機関や税務署窓口で相談してもよいでしょう。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
4-3.【デメリット1】連帯債務者は団信に加入できないケースがある
収入合算の「連帯債務型」は2人で返済を行いますが、連帯債務者は団信に加入できないケースがあります。
団信に加入していない場合、死亡や高度障害状態といった状況が発生しても住宅ローンがゼロになることはありません。
そのため連帯債務者が払えなくなった返済分は、主債務者が返済する必要があります。
金額によっては、返済の継続が難しくなる可能性がある点は注意が必要です。
金融機関によっては、連帯債務者も加入できる「夫婦連生団信」を用意している場合があるため、事前に確認しておきましょう。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)

FP
田宮有莉
夫婦連姓団信とは、どちらか一方が死亡した際、保険金でローンの全額が保険金で完済される仕組みのことです。フラット35(ペア連姓団信)や一部の民間金融機関のみ取り扱いがあり、加入する場合は金利が上乗せされます。万が一のリスクを考えて、検討するのもよいでしょう。
4-4.【デメリット2】連帯保証人は団信、住宅ローン控除とも対象外
収入合算の「連帯保証型」における連帯保証人は、団信の加入および住宅ローン控除の適用ともに対象外となります。
これは、主債務者が返済不能とならない限り、連帯保証人は返済義務を負わないためです。
ただし、主債務者が死亡または高度障害状態になった場合は、団信によって住宅ローン残債がゼロになります。
そのため、連帯保証人に返済義務が発生するケースは、多くないと考えてよいでしょう。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
5.ペアローンと収入合算のどちらを選ぶべきか

ペアローンと収入合算、どちらのローンを選ぶべきかは、夫婦の年齢や年収、今後のライフプランなどによって異なります。
最後に、ペアローンが適しているケースと収入合算が適しているケースを解説します。
自身に合ったローンを選択し、納得がいくマイホーム購入の第一歩をスタートしましょう。
5-1.ペアローンが適しているケース
ペアローンが適しているケース例は、以下のとおりです。
- 夫婦ともに安定した収入がある
- 夫婦で住宅ローン控除を受けたい
- 産休や育休、転職などによる収入の変動に備えた貯蓄がある
2人とも安定した収入があり、双方が住宅ローン控除を受けたいと考えている方は、ペアローンを検討しましょう。
ただし、現在の収入状況に加え、産休・育休や転職などによる収入変動の見通しがある程度立っていたり、不測の事態で収入が減少した場合にも補填できる貯蓄が確保されていたりすることが重要です。
これらの点を踏まえたうえで、ペアローンを検討・契約するようにしましょう。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
5-2.収入合算が適しているケース
収入合算が適しているケース例は、以下のとおりです。
- コストを抑えて住宅ローンの契約をしたい
- 夫婦の収入に差がある
- 今後収入が変動する可能性がある
1本のローン契約で借入ができる収入合算は、コストを抑えた借入を希望する方に適した住宅ローンです。
夫婦の収入に差がある場合や今後収入が変動する可能性があるときには、収入合算を検討しましょう。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
まとめ
ペアローンとは、1つの物件に対し一定の収入がある夫婦や親子が2人で組む住宅ローンです。
それぞれがローンを契約しお互いがお互いの連帯保証人となる仕組みで、夫婦ともに団信や住宅ローン控除の対象となります。
また、ペアローンと似たものに、収入合算があります。
収入合算は1本の住宅ローンを契約し、主債務者がメインとなり返済する仕組みです。
主債務者ではないほうの人は、連帯債務者または連帯保証人となります。
夫婦の収入が同水準であり、ある程度の貯蓄がある場合は、ペアローンを検討するのもよいでしょう。
今後も大きく収入が減少する可能性が低いことも、ペアローンを借り入れるうえで確認したいポイントです。
コストを抑えてローンを借り入れたいのであれば、収入合算もよい選択肢といえます。
夫婦の収入額に差がある方や、今後の収入の変動が不透明な場合は、収入合算の利用を検討しましょう。
無料サポートサービスも活用しながら、自分に合った資金計画を立てて理想のマイホームを手に入れてくださいね。

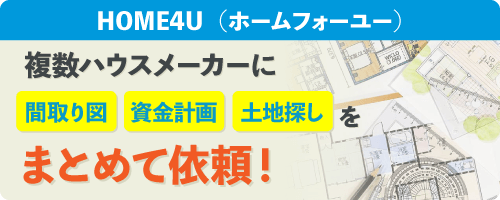


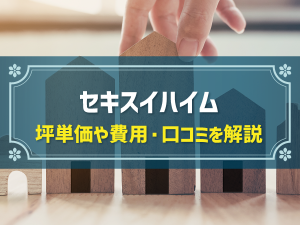
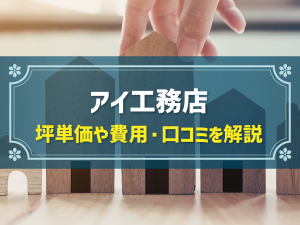

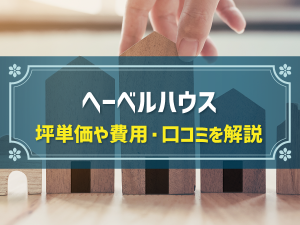

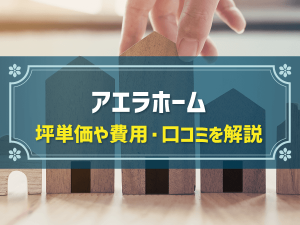
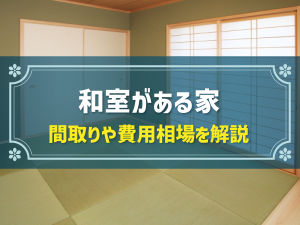




HOME4U(ホームフォーユー)無料サポートサービス
実際の見積もりを
複数比較・検討したい
簡単なスマホ入力だけで、複数のハウスメーカーの見積もりが無料でもらえる「プラン作成サービス」がおすすめ!
▷【無料】プラン作成依頼はこちら
資金計画や補助金活用の
コツが知りたい
ハウスメーカー出身のアドバイザーに、自宅から簡単に相談できる「無料オンライン相談サービス」がおすすめ!
▷【無料】オンライン相談はこちら