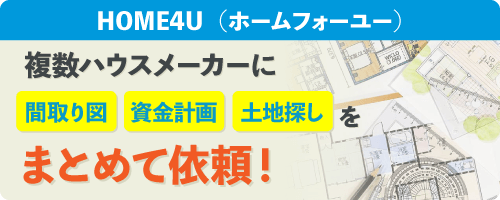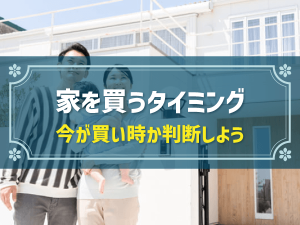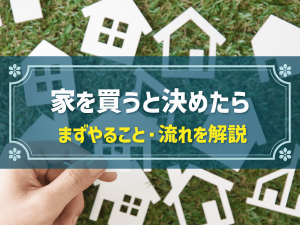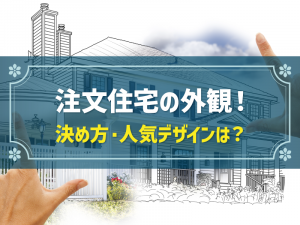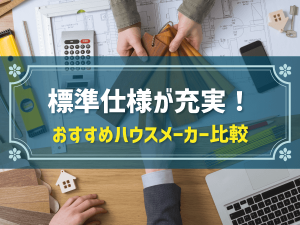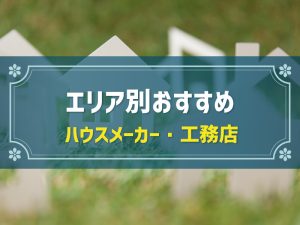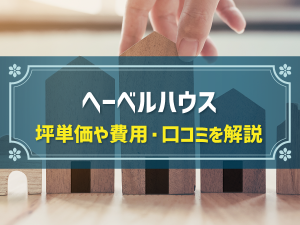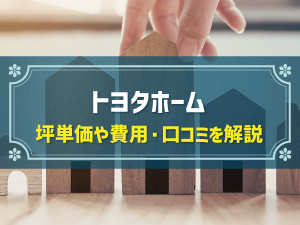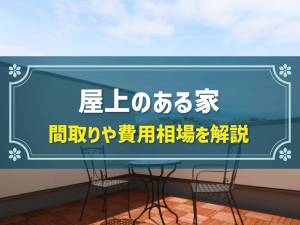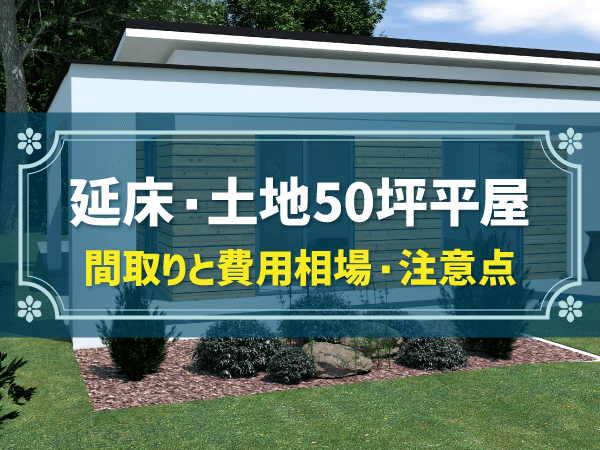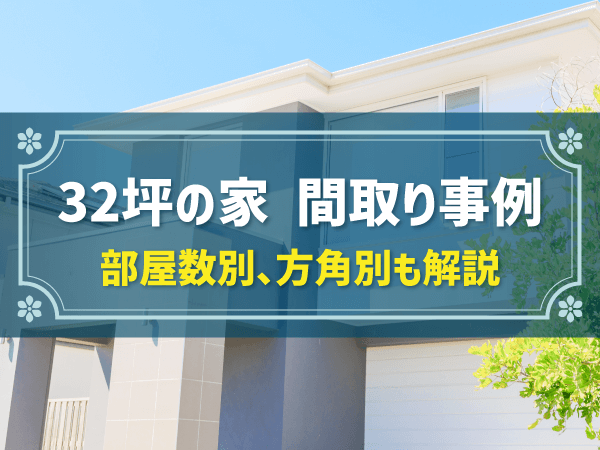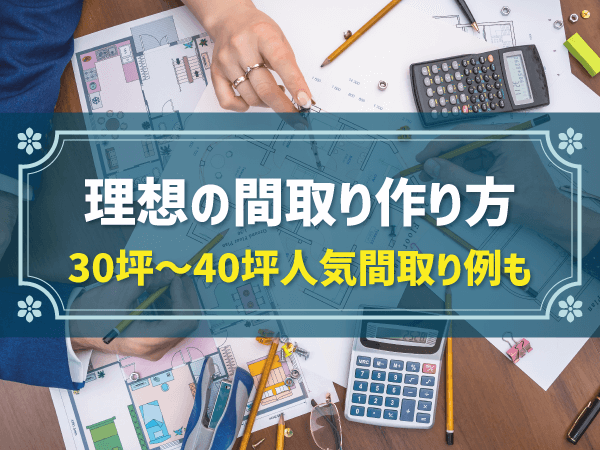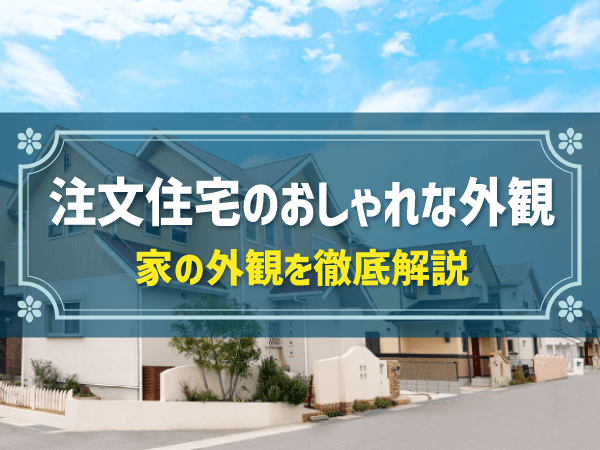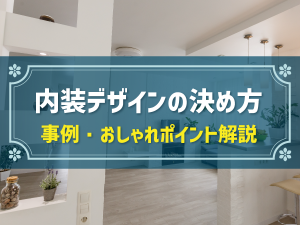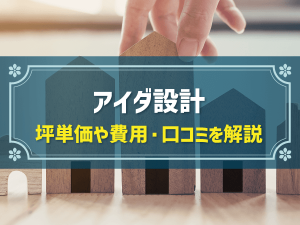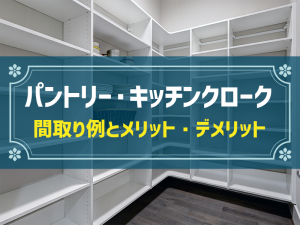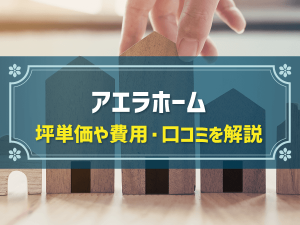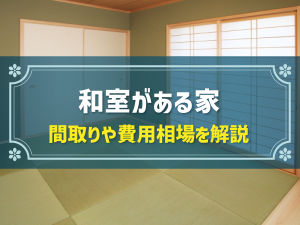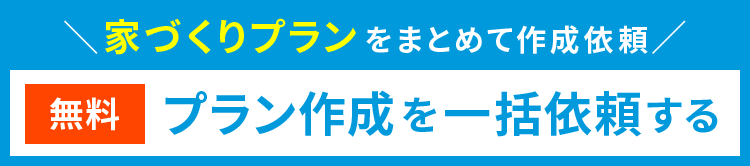長期優良住宅とは、簡単にいえば、「長く安心・快適に暮らせる高品質な家」です。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。
長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
出典:国土交通省「長期優良住宅のページ」
長期優良住宅の認定を受ければ、税金の優遇やローン金利の優遇など、多くのメリットが受けられますが、デメリットもあるためしっかり両者を把握したうえで検討しましょう。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
長期優良住宅の認定を受けて家を建てれば、国が定めた基準を満たした良質な住宅という「お墨付き」があるため、大きな安心感があるのは間違いありません。
また、長期優良住宅の認定を受ける一戸建ては毎年10万戸以上となっており、人気の高さが伺えます。
この記事では、長期優良住宅を建てる場合のポイントや、どこのハウスメーカーに依頼すれば良いかなど、知っておきたい知識をわかりやすく解説します。
また、長期優良住宅の条件をクリアしながら、家づくりの希望もクリアした住宅を建てるためには、ハウスメーカーや間取りプランの比較検討が欠かせません。
そこでおすすめなのが「HOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービス」です。
- 土地、予算などのフォーム入力
- アドバイザーがご希望ヒアリング
- 最適なハウスメーカーと、家づくりプラン・見積もりのご提案
主な住宅商品の種類や特徴を比較したい方は「注文住宅の商品」もご覧ください。
Contents
1.長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、2009年(平成21年)に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による基準をクリアして認定を受けた家のことをいいます。
そのため、長期にわたって安心して住むことができます。
建物の着工前に都道府県知事等に申請を行い、一定の基準に適合していれば、長期優良住宅の認定を受けられます。
完成後の建物検査はなく、書類審査のみで認定されます。
出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「![]() 長期優良住宅認定制度の概要について[新築版]」
長期優良住宅認定制度の概要について[新築版]」
2.長期優良住宅のメリット
長期優良住宅を建てるメリットは、以下のとおりです。
- 長期的に安心して暮らせる
- 売却するときに付加価値となる
- 適用される減税・優遇・補助金が多い
以下より1つずつ解説します。
2-1.長期的に安心して暮らせる
長期優良住宅は、その名のとおり、長期的に安全かつ快適に生活できる住宅です。
耐震性能が高く、数世代にわたって暮らすことが想定されているため、安心して生活できます。
また、長期優良住宅はリフォームしやすいのも特徴です。
暮らしにくさを感じたときや新しい設備を導入したいときも、長期優良住宅なら建て替えなくてもリフォーム工事で対応でき、住宅にかかる費用を抑えやすくなります。
2‐2.売却するときに付加価値となる
長期優良住宅は国の認定制度であり、高性能な家であることを客観的に示すことができます。
事情があってマイホームを売却することになった場合に、長期優良住宅は大きなアピールポイントとなります。
売却時に提示できるように、長期優良住宅に関する認定書類はしっかりと保管しておきましょう。
2-3.適用される減税・優遇・補助金が多い
まず、なんといっても長期優良住宅のメリットは、適用される減税・優遇・補助金が多く、お得に家を建てられる点でしょう。
- 住宅ローン控除の拡充
- 投資型減税(所得税額の特別控除)
- 不動産取得税の減税
- 登録免許税の税率引き下げ
- 固定資産税の減税
- 住宅ローンの金利の優遇
- 地震保険料の割引
- 補助金
それぞれ詳しく見ていきましょう。
出典:国土交通省「![]() 令和6年度国土交通省税制改正概要」
令和6年度国土交通省税制改正概要」
2-2-1.住宅ローン控除の拡充
「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン減税、住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入する際に、条件を満たすと受けられる所得税と住民税の控除のことをいいます。
出典:国土交通省「住宅ローン減税」
最大13年間にわたって、年末の住宅ローン残高の0.7%以下が、所得税・住民税から戻ってきます。
長期優良住宅においては、この控除対象になる借入限度額が優遇されており、4,500万円(2024年に関しては子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円)までとなります。
| 住宅種類 | 2024年入居 | 2025年入居 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 5,000万円 |
4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 4,500万円 |
3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 4,000万円 |
3,000万円 |
| その他の住宅 | 0円(2023年までに新築の建築確認をした場合は2,000万円) | |
※下段は子育て世帯・若者夫婦世帯
2024年度の税制改正により、「住宅ローン減税」の仕組みが以下のように変更されました。
- 2024年に入居する場合は、子育て世帯・若者夫婦世帯は借入限度額が住宅に応じて500万円~1,000万円増える
- 所得要件は2,000万円以下(床面積40平米以上50平米未満の住宅で本制度を利用する場合は1,000万円以下)
2-2-2.投資型減税(所得税額の特別控除)
住宅ローン減税は10年間控除が続きますが、投資型減税は一度きりの減税制度です。
投資型減税では、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅を建てるために割高になった費用(掛かり増し費用)の10%が年末の所得税から控除されます。
控除率は10%ですが、床面積×45,300円(上限額650万円)を超えて控除されない点に注意が必要です。
2-2-3.不動産取得税の減税
不動産取得税は、家を新築したときや取得したときに1度だけかかる税金です。
一般住宅の場合は控除額が1,200万円のところ、長期優良住宅においては1,300万円に引き上げられています。
| 控除額 | |
|---|---|
| 一般住宅 | 1,200万円 |
| 長期優良住宅 | 1,300万円 |
この軽減措置を利用すると、長期優良住宅の不動産取得税は、(固定資産税評価額-1,300万円)×3%となります。
現在のところ、2026(令和8)年3月31日までに新築された住宅が対象です。
2-2-4.登録免許税の税率引き下げ
家を建てたり買ったりしたときには、法務局で所有権保存登記や所有権移転登記を行いますが、このとき登録免許税がかかります。
下記のとおり、長期優良住宅は一般住宅に比べて税率が低くなります。
| 税率 | |
|---|---|
| 一般住宅 | 保存登記0.15% 移転登記0.3%(一戸建て) |
| 長期優良住宅 | 保存登記0.1% 移転登記0.2%(一戸建て) |
現在のところ2027(令和9)年3月31日までに新築された住宅が対象です。
2-2-5.固定資産税の減税(新築住宅の減額期間の延長)
新築住宅を建てると、一定期間内は固定資産税が2分の1に軽減されます。
下記の表のとおり、減額される期間は一般住宅よりも長期優良住宅の方が長くなります。
| 新築住宅の減額期間 | |
|---|---|
| 一般住宅 | 3年間(一戸建て) |
| 長期優良住宅 | 5年間(一戸建て) |
現在のところ2026(令和8)年3月31日までに新築された住宅が対象です。
減額を受けるためには、長期優良住宅認定通知書等を市区町村に提出する必要があります。
また、住宅面積が50平米以上280平米以下、居住部分の床面積が全体の2分の1以上といった基準があります。
2-2-6.住宅ローンの金利の優遇
長期優良住宅は、住宅ローン商品「フラット35」の金利優遇制度があります。
フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構の提携によって提供される、長期固定金利の住宅ローンです。
フラット35を利用するために必要な技術基準に加えて、更に省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性・耐久性・可変性などの面で一定の技術基準を満たすと、【フラット35】Sを利用することができます。
長期優良住宅なら、【フラット35】Sの金利A・Bプランのうち、優遇の高い金利Aプランが適用され金利引き下げ期間が10年間となります。
また、長期優良住宅なら、返済期間が最長50年で全期間固定金利となる【フラット50】も利用することが可能です。
【フラット50】では住宅を売却することになった際に、購入者に住宅ローンを引き継ぐことができます。
2-2-7.地震保険料の割引
長期優良住宅は、耐震等級2以上と定められていて高い耐震性をクリアしているため、地震保険料が割引されるメリットがあります。
耐震等級2で30%割引、耐震等級3で50%割引など、耐震等級に応じた割引率が適用になります。
なお、地震保険はどの保険会社で申し込んでも、政府が定めた一定の制約により保険料・補償内容は同じです。
また、地震保険のみ加入することはできず、火災保険に加入していることが必須となります。
2-2-8.補助金
そのほかにも長期優良住宅もしくはZEH住宅を新築するときには、「子育てエコホーム支援事業」による補助金を受けられる可能性があります。
この制度は、国土交通省の採択を受けた認定事業者で新築住宅を建築・購入するときに利用でき、長期優良住宅なら最大100万円、ZEH住宅なら最大80万円の補助金を受給できます。
ただし、申請できるのは子育て世帯か若者夫婦世帯に限られる点に注意しましょう。
また、エコリフォームを実施する場合も、一定の基準を満たせば最大60万円の「子育てエコホーム支援事業」による補助が受けられます。
なお、エコリフォームに関しては、子育て世帯・若者夫婦世帯に限らず、全世帯が対象です。
そのほかにも、長期優良住宅を建てる際に国や地域の補助金制度を利用できることがあります。
補助金制度に詳しいハウスメーカーの担当者にも相談し、かしこく家づくりを進めていきましょう。
【自分に合ったハウスメーカー・工務店を効率よく探したい方へ】
全国には数万社のハウスメーカーがあるといわれています。
手当たり次第に調べだすと、無駄な時間や労力をかけてしまうので注意してください。
おすすめは、まず無料のHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスをご利用いただくこと。
- スマホやパソコンからあなたに合ったハウスメーカー・工務店がわかる!
- 家づくりの要望・情報を専任コーディネーターが電話で整理!
- 実際の住宅プランを最大5社分比較できる!
資金計画でよくあるのが「実際に見積もりを出してもらったら予算と合わず、はじめからプランを立て直した」という失敗です。
HOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスなら、専任コーディネーターによる複数ハウスメーカーへの資金計画作成依頼のほか、注文住宅のプロであるアドバイザーに「予算の立て方」や「補助金制度の活用方法」などをオンライン上から相談することもできます。
完全無料、営業トークは一切ないので、ぜひお気軽にご活用ください。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
3.長期優良住宅のデメリット
制度を利用すればお得に建てられる長期優良住宅ですが、一方でデメリットもあるので確認しておきましょう。
3‐1.申請コストがかかる
長期優良住宅の認定を受けるためには費用がかかります。
自分で申請する場合は、審査書類、図面などの書類を揃える手間もかかります。
審査・認定に関する手数料は行政により多少のバラつきがありますが、自分で行うとおよそ5万~6万円です。
ハウスメーカー、工務店などに申請を代行してもらうと、手数料を上乗せされるため、およそ20万~30万円程度かかるのが一般的です。
3‐2.建築コストがアップしたり建築期間が長くなったりする場合がある
ハウスメーカーの多くは、標準仕様で長期優良住宅の認定規準をほぼクリアできることが多いので、長期優良住宅にしても建築コストはあまり変わらないことが多いです。
中小工務店では、一般住宅よりも20~30%程度割高になる可能性があり、工期も一般的な住宅の建築期間より数週間~数か月長くかかってしまう場合があります。
長期優良住宅の実績があるかどうかをハウスメーカーに事前に確認し、建築コストや建築期間の違いについて確認しておきましょう。
3‐3.定期点検が必要
長期優良住宅は、建築した後も継続的な点検やメンテナンスを行って、良好な状態を保つ必要があります。
建築前に提出する「維持保全計画」に沿って定期点検を行い、修繕を要する場合には実施します。
構造耐力上主要な部分や、給排水のための配管設備についての点検は少なくとも10年に一度は必要です。
点検・修繕費用は、長く安心して快適な生活をするためには必要なコストです。
また、長期優良住宅について点検や修繕を行ったら、その情報を大切に保管しておく義務があります。
点検やメンテナンスなどの維持保全を計画通りに実施しないと、長期優良住宅の認定が取り消される可能性もあるため注意が必要です。
なお、定期点検が必要なことをデメリットの一つとして挙げましたが、定期点検を確実に行えば安心して暮らせるため、メリットの側面もあります。
ハウスメーカーのアフターサービスも比較しながら、住み始めてからも安心なマイホームを建てましょう。
以上が、長期優良住宅のデメリットです。
長期的なスパンで見れば長期優良住宅はお得な家といえますが、初期費用をなるべく抑えたい方には向かないかもしれません。
初期費用・住み始めてからのランニングコストも含め、しっかりとした資金計画を立てたうえで長期優良住宅を検討したい方は、ぜひ一度、無料のHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスをご利用ください。
あなたの予算・要望に合ったハウスメーカー・工務店の実際の住宅プラン(資金計画含む)を比較できるので、具体的な費用イメージを持ちながら資金計画が立てられます。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
4.長期優良住宅の認定手続きと確認方法

長期優良住宅の条件を満たした住宅を建てても、長期優良住宅として認定を受けなければ「長期優良住宅」とは呼べません。
長期優良住宅に対して適用される優遇制度や節税制度も、長期優良住宅の認定証がなければ適用されない点に注意が必要です。
また、長期優良住宅の認定を受けるための申請は、着工前までに行わなくてはいけない点にも注意してください。
事後認定ができないため、建築前に所管行政庁(都道府県または市区町村)で申請手続きを行います。
このとき技術審査や認定手数料などの費用が5万~6万円程度かかることもあります。
4-1長期優良住宅の手続き方法
長期優良住宅の認定手続きは以下の流れに沿って進めていきます。
- お住まいの自治体の長期優良住宅管轄機関に相談する
- お住まいの自治体に必要書類を提出し、審査を受ける
- 審査に通過すると適合通知書が交付される。指定確認検査機関に適合通知書を提出して、建築確認を受ける
- 審査に通過すると確認済証が交付される
- 登録住宅性能評価機関に技術的審査もしくは設計住宅性能評価を申込む
- 技術的審査確認書もしくは設計住宅性能評価書が交付される
- お住まいの自治体の長期優良住宅管轄機関に長期優良住宅建築計画を提出する
- 長期優良住宅認定通知書を受領後、建築工事に着工する
長期優良住宅の建築実績が豊富なハウスメーカーなら、申請をサポートしてくれるので安心してくださいね。
技術審査や登記書類の取得をまとめて代行してくれるケースもあります。
注文住宅を建築するときは、内装や設備を決めたり住宅ローンの手続きがあったりと、何かと忙しいものです。
実績豊富なハウスメーカーに相談して、スムーズに長期優良住宅の認定手続きを進めましょう。
4-2.長期優良住宅の確認方法
長期優良住宅であることは、お住まいの自治体の長期優良住宅管轄機関から交付された「認定通知書」で確認できます。
認定通知書がないと工事に着工できないだけでなく、長期優良住宅に適用される各種制度を利用できません。
受領した認定通知書は大切に保管しておきましょう。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
5.長期優良住宅の認定基準
長期優良住宅の認定を受けるためには、一定の基準をクリアする必要があります。
定められている主な基準は下記のとおりです。
| 認定基準項目 | 概要 | 住宅性能表示・基準内容 |
|---|---|---|
| 劣化対策 | 数世代に渡って長く住めること | 劣化対策等級3 床下・小屋裏点検口 |
| 耐震性 | 地震に強いこと | 等級2以上 |
| 維持管理・更新の容易性 | 補修・リフォームしやすいこと | 等級3 |
| バリアフリー性 | 将来の改修に備えてスペースが確保されていること | 高齢者等配慮対策等級3 |
| 省エネルギー性 | 省エネに配慮していること |
|
| 居住環境への配慮 | 居住環境への配慮 居住環境の維持・向上に配慮されていること |
|
| 住戸面積 | 良好な居住水準を維持できる規模を有すること | 延床面積75平米以上(一戸建て)、少なくとも一の階の床面積が40平米以上 |
| 維持保全計画 | 定期的な点検・補修計画が策定されていること |
参考:![]() 長期優良住宅に係る認定基準 技術解説(令和6 年4 月1 日版)
長期優良住宅に係る認定基準 技術解説(令和6 年4 月1 日版)
ひとつずつチェックして基準をクリアするように建築するのは大変と思うかもしれませんが、長期優良住宅の実績を豊富に持つハウスメーカーに依頼すればスムーズに建築することができます。
長期優良住宅の規定をほぼ「標準仕様」でクリアしているハウスメーカーや、長期優良住宅の認定取得率が90%以上のハウスメーカーもあります。
次章より詳しく見ていきましょう。
6.長期優良住宅の建築におすすめのハウスメーカー
長期優良住宅を建てるなら、実績豊富なハウスメーカーに相談しましょう。
おすすめのハウスメーカー3社の特徴を解説します。
6-1.ダイワハウス
ダイワハウスでは、すべての注文住宅において、標準仕様で長期優良住宅に対応しています。
また、独自の保証・点検プログラムを通じて、住宅を良好な状態に保つサポートを実施します。
例えば、鉄骨造の注文住宅「 XEVO Σ PREMIUM」は、天井高272センチの開放感ある空間を特徴とする商品です。
強度を維持しつつも軽量な窯業系サイディングを活用し、耐震等級3の1.3倍の強さを実現しています。
また、プランの自由度が高く、理想を実現しやすいのもXEVO Σ PREMIUMの特徴です。
断熱性能・気密性能共に高く、ZEH住宅の基準もクリアしています。
出典:ダイワハウス 公式HP
6-2.セキスイハイム
長期優良住宅が長期間にわたって暮らしやすい住宅であるためにも、長期のサポートシステムがあるハウスメーカーを選ぶことが大切です。
最長60年の長期サポートシステムを提供しているセキスイハイムなら、大切な住宅の点検とメンテナンスを安心してまかせられるのではないでしょうか。
セキスイハイムの「GREENMODEL」は、地球温暖化抑制を目指す住宅です。
太陽光発電システムと蓄電池システムを活用し、1年で使うエネルギーの3/4を自然エネルギーでまかなうことが可能です。
二酸化炭素の排出量を抑えるだけでなく、光熱費も抑えられるため、地球にもお財布にも優しい生活を実現できるでしょう。
出典:セキスイハイム 公式HP
6-3.タマホーム
タマホームは高品質と適正価格にこだわるハウスメーカーです。
中間業者をはさまずに施工を直接管理することで、コストを抑え、工期短縮も実現しています。
高い住宅性能をさらに高く進化させたのが「大安心の家」シリーズです。
構造や基礎工事にこだわり、標準仕様で長期優良住宅に対応しています。
また、最長60年の保証サポートシステムにも対応しているため、住宅を常に優れた状態に維持できるのも特徴です。
地盤沈下による建物の損害やシロアリ被害にも、最長10年の補償制度が適用されます。
出典:タマホーム 公式HP
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
7.長期優良住宅を建てるときの3つのポイント
長期優良住宅には大きなメリットがありますが、申請は着工前までという期限があります。
下記5つのポイントを押さえて、早めにハウスメーカーに相談してみましょう。
7-1.十分な時間があるか確認する
長期優良住宅を建てるためには、建築工事が始まるまでに長期優良住宅認定通知書を受け取る必要があります。
しかし、認定通知書を受け取るには、自治体の審査を受けたり長期優良住宅管轄機関に建築計画を提出したりと多くの手続きがあり、通常の住宅よりも時間がかかってしまう点に注意が必要です。
また、認定通知書を受領した後も、減税制度や補助金制度の申請・適用に時間がかかることもあります。
そのため、急いで住宅を建てる必要があるときには、長期優良住宅の認定通知書を受け取ったり、各種制度に申請したりする時間がないかもしれません。
利用できる制度を可能な限り多く利用するためにも、十分に時間を取って、手続きを始めていくことが求められます。
また、減税制度や補助金制度には申請期限が決まっているため、あまりゆっくりと家づくりを手掛けていると、利用できる制度が減ることも想定されます。
長期優良住宅の実績豊富なハウスメーカーに相談し、無理のない家づくりスケジュールを立てましょう。
7-2.資金計画を立てる
長期優良住宅を建てるには、通常よりも高性能な設備や資材、工期が長引く可能性のある工法などが必要になるため、建築費用が高くなる傾向にあります。
補助金制度や減税措置を活用しても、一般的な住宅よりは高額な費用がかかるかもしれません。
無理なく家づくりを進めていくためにも、まずは資金計画を立てましょう。
長期優良住宅の建築実績が豊富なハウスメーカーなら、資金を抑えるポイントについての具体的なアドバイスももらえることがあります。
7-3.長期優良住宅の実績の多いハウスメーカーに依頼する
ここまでお伝えしてきたように、長期優良住宅の認定を受けるためには申請費用が必要で、建築費もアップする場合があります。
長期優良住宅を建てる際には、コストアップを最小限に抑えるため、長期優良住宅の実績の多いハウスメーカーに依頼することをおすすめします。
長期優良住宅とするための規定をほぼ「標準仕様」でクリアできているハウスメーカーや、長期優良住宅対応の商品が用意されている企業で建築すれば、コストアップが抑えられます。
長期優良住宅の実績が豊富な企業なら、申請や施工のノウハウがあり、点検等の長期的なフォローも受けることができます。
7-4.コストと税制優遇等を比較する
コストがかかっても、長期優良住宅を建てるメリットが大きいかどうかを検討することが大切です。
特に住宅ローン控除については、実際の納税額が控除額の上限となる点に注意が必要です。
つまり、長期優良住宅を建てればもれなく、10年間で500万円の控除を受けられるとは限らないということです。
住宅ローン控除は所得に応じて納めている所得税、住民税が還付される制度なので、そもそも所得税が少ない場合や、ローン借入額が少ない場合にはメリットが小さくなります。
一般的に所得(所得税)が多く、ローン借入額が大きい場合に、ローン控除のメリットは大きくなります。
7-5.信頼できるハウスメーカーを見極めること
長期優良住宅は申請書類の内容だけで認定され、工事中のチェックや完成後の検査などはありません。
施行の品質をチェックするような制度ではないため、質の高い住宅を建ててもらえるハウスメーカーを見極めることが大切です。
長期優良住宅は認定コストがかかるため、住宅ローンの借入額が少ない場合などは、税制優遇によるメリットがコストを上回らない可能性があります。
節税メリットが大きくない場合には、優良なハウスメーカーを見つけて高機能な住宅を建てれば、必ずしも長期優良住宅の認定を受ける必要はないかもしれません。
認定を受けない場合には、第三者による住宅診断(ホームインスペクション)を定期的に受けて、住宅の施工品質や劣化状態を確認するという選択肢もあります。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
まとめ
それではおさらいです。
長期優良住宅は、長期的に安心して快適に住み続けられる優良な住宅です。
税制優遇等のメリットとコストを比較した上で、長期優良住宅を建てたい場合には建築実績の豊富なハウスメーカーを選ぶようにしましょう。
この記事のポイント
【メリット】
- 長期的に安心して暮らせる
- 売却するときに付加価値となる
- 適用される減税・優遇・補助金が多い
【デメリット】
- 申請コストがかかる
- 建築コストがアップしたり建築期間が長くなったりする場合がある
- 定期点検が必要
詳細は「2.長期優良住宅のメリット」「3.長期優良住宅のデメリット」で解説しています。
家の大きさや性能によって異なるため相場は出せませんが、長期優良住宅は一般的な住宅よりも建築コストがかかります。
ただし、減税や金利の優遇があるため、これらを活用すればお得に高性能な家を建てることができます。
詳しくは「2‐3.適用される減税・優遇・補助金が多い」をご覧ください。
パッと見て「この家は長期優良住宅である」と判断することは難しいかもしれませんが、ハウスメーカーによっては、長期優良住宅に対応した住宅商品をシリーズとして用意していることもあるため、公式HPやカタログをチェックしてみるとよいでしょう。
詳細は「5.長期優良住宅の認定基準」でお伝えしています。