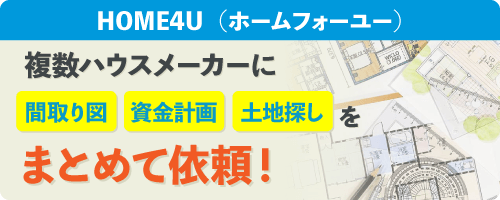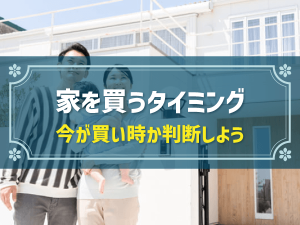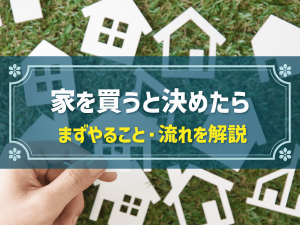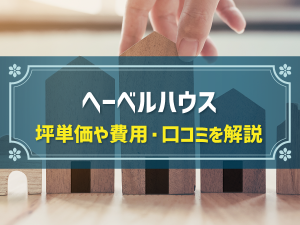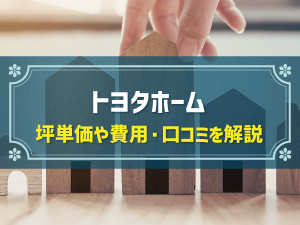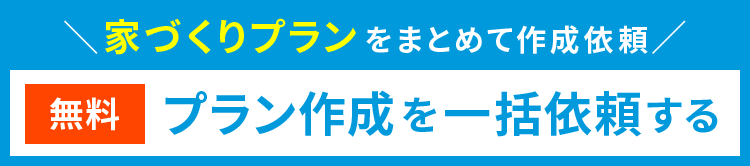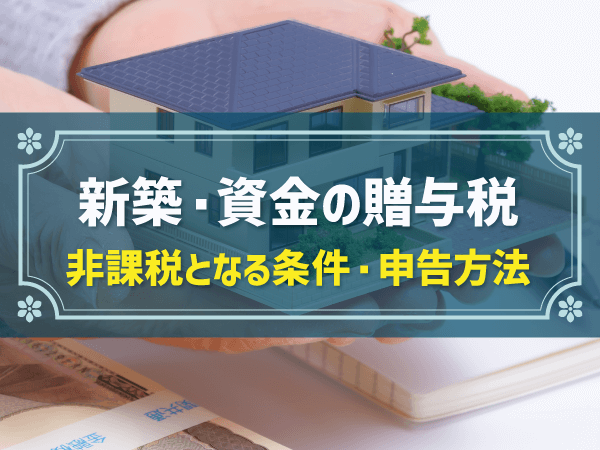
住宅取得のために親や祖父母からの援助を受ける場合、最大1,000万円までの贈与を非課税にする特例措置があります。
| 期間や条件など | 内容 |
|---|---|
| 特例が 適用できる期間 |
2026(令和8)年12月31日までに贈与を受けた場合 |
| 非課税枠の 上限額 |
省エネ等住宅:1,000万円 上記以外の住宅:500万円 |
| 贈与を受ける 人の条件 |
贈与する人が父母・祖父母などの「直系尊属」であること 等 |
| 住宅の条件 | 住宅の床面積2分の1以上が、贈与を受ける者の居住用であること 等 |
| 利用方法 | 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの期間に贈与税の申告をする |
| 必要書類 | 贈与税の申告書や戸籍謄本、源泉徴収票 等 |
本記事を読むことで、新築住宅を建てるために親や祖父母から資金援助を受けた場合の非課税枠の金額や活用の仕方を理解し、実際に非課税措置を利用することができるようになります。
- 住宅を新築する際の「贈与税の非課税措置」の条件や非課税額
- 贈与税の非課税措置を利用する方法
- 贈与税の非課税措置を利用するための必要書類
なお、注文住宅にかかる税金は「贈与税」だけではありません。
詳しくは「注文住宅の税金」もご覧ください。
Contents
1.【2024年最新版】新築住宅資金贈与の非課税枠について
住宅資金贈与の非課税枠(措置)とは、
父母・祖父母などの「直系尊属」から住宅取得のための贈与を受けたときに、一定の条件を満たすことで一定の額(枠)まで贈与税の優遇が受けられる制度です。
通常なら贈与額が1年に110万円を超えると贈与税がかかりますが、この非課税措置を利用することで節税が可能となります。
| 期間や条件など | 内容 |
|---|---|
| 特例が 適用できる期間 |
2026(令和8)年12月31日までに贈与を受けた場合 |
| 非課税枠の 上限額 |
省エネ等住宅:1,000万円 上記以外の住宅:500万円 |
| 贈与を受ける 人の条件 |
贈与する人が父母・祖父母などの「直系尊属」であること 等 |
| 住宅の条件 | 住宅の床面積2分の1以上が、贈与を受ける者の居住用であること 等 |
参照:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」
以下より詳しく解説していきます。
1-1.贈与税の非課税措置は2026年12月31日まで
2026(令和8)年12月31日までに贈与を受けた場合に対象となります(2024年6月時点)。
本来は2021年12月31日までの特例措置でした。
しかし、2022年度・2024年度の税制改正により、内容を変更しつつ適用期間も延長されています。
1-2.非課税枠は最大1,000万円まで
質の高い住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円まで非課税です。
「質の高い住宅」として判断される条件は、以下の3つからいずれかを満たす必要があります。
- 断熱等性能等級が4、または一次エネルギー消費量等が4以上の省エネルギー性が高い住宅
- 耐震等級2以上または免震建築物で、耐震性が高い住宅
- 高齢者等配慮対策等級3以上のバリアフリー性が高い住宅
最近の新築住宅なら「質の高い住宅」にあてはまることがほとんどですが、建築会社の担当者に確認しておくとよいでしょう。
贈与税の課税方法
贈与税には以下の2つの課税方法があり、いずれかを選ぶことができます。
| 課税方法 | 内容 |
|---|---|
| 暦年課税 | 毎年110万円までの贈与なら贈与税が非課税になる。 |
| 相続時 精算課税 |
最大2,500万円まで贈与税が非課税になる。 ただし、贈与者が亡くなったときに相続税額を計算して一括して納税する。 |
それぞれに非課税枠が設けられており、住宅資金の非課税枠と加算して併用することが可能です。
参照:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
参照:一般社団法人全国銀行協会「「相続時精算課税制度」っていったいどんな制度?」
1-3.贈与を受ける人の条件|贈与者の直系尊属が基本
住宅資金贈与の非課税措置を利用するには、「贈与を受ける人」についての条件があります。
- 贈与をする人が「直系尊属」である(養子縁組も可)
- 贈与を受ける人は年齢が1月1日の時点で「18歳以上」
- 贈与を受けた年の合計所得が「2,000万円以下」
(40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は所得1,000万円以下) - 贈与を受ける人は「日本国内」に住所がある
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与金を住宅用家屋の新築・取得に「全額使用」する
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに該当の住宅に「居住」する
(または、住むことが確実であること)
参照:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
1-4.住宅の条件
住宅資金贈与の非課税措置で贈与を受ける場合の「住宅の条件」は、以下のとおりです。
- 住宅の登記簿上の床面積が50平米以上
(受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平米以上) - 住宅の床面積2分の1以上が、贈与を受ける者の居住用
- 日本国内にある住宅
参照:国土交通省「住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持(所得税・個人住民税)」
なお、中古・増改築の場合には、これらに加えてさらにいくつかの条件を満たす必要があります。
1-5.非課税措置を利用した贈与税シミュレーション
住宅資金贈与の非課税措置を利用した場合の「贈与税」についてシミュレーションを行ってみます。
シミュレーションは
- 【ケース1】非課税措置を受けて、贈与税が0円になった場合
- 【ケース2】非課税措置を受けたうえでも、贈与税が発生する場合
の2つのケースで行いました。
【ケース1】非課税措置を受けて、贈与税が0円になった場合
| 建てた新築住宅 | 省エネ等に該当しない一般住宅 |
|---|---|
| 贈与額 | 600万円 |
| 贈与税の課税方法 | 暦年課税 |
600万円〈贈与額〉- 500万円〈住宅資金の非課税措置〉- 110万円〈暦年贈与の基礎控除〉
=贈与税は0円
上記のように住宅取得のために親から贈与を600万円受けた場合、住宅資金の非課税措置を「利用しなければ」110万円の暦年贈与の基礎控除のみ適用となるので490万円分が贈与税の課税対象額となります。
しかし住宅資金の非課税措置を「利用すれば」課税対象額は0円になり、結果「贈与税は0円」となります。
【ケース2】非課税措置を受けたうえでも、贈与税が発生する場合
| 建てた新築住宅 | 省エネ等に該当する優良住宅 |
|---|---|
| 贈与額 | 1,500万円 |
| 贈与税の課税方法 | 暦年課税 |
課税対象額(1,500万円〈贈与額〉- 1,000万円〈住宅資金の非課税措置〉- 110万円〈暦年贈与の基礎控除〉✕ 15%〈税率〉- 10万円〈控除額〉
=贈与税は48万5,000円
上記のように住宅取得のために親から贈与を1,500万円受けた場合、住宅資金の非課税措置を「利用しなければ」110万円の暦年贈与の基礎控除のみ適用となるので1,390万円分が贈与税の課税対象額となります。
しかし住宅資金の非課税措置を「利用すれば」課税対象額は390万円になります。
390万円が課税対象額だった場合の特例税率(15%)を掛けて、控除額(10万円)を引くことで結果「贈与税は48万5,000円」となります。
特例税率と控除額は、下記の「贈与税の速算表」から求めることが可能です。
適用税率は「一般税率」と「特例税率」があり、住宅資金の非課税措置を利用する場合は「特例税率」で算出します。
| 基礎控除後の 課税対象額 |
特例税率(控除額) ※住宅資金の非課税措置はこちらの税率 |
一般税率 (控除額) |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10%(0円) | 10% (0円) |
| 200万円超 300万円以下 |
15%(10万円) | 15% (10万円) |
| 300万円超 400万円以下 |
20% (25万円) |
|
| 400万円超 600万円以下 |
20%(30万円) | 30% (65万円) |
| 600万円超1,000万円以下 | 30%(90万円) | 40% (125万円) |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 40%(190万円) | 45% (175万円) |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 45%(265万円) | 50% (250万円) |
| 3,000万円超4,500万円以下 | 50%(415万円) | 55% (400万円) |
| 4,500万円超 | 55%(640万円) |
参照:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
家づくりを検討しだしたら、まずは無料のHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスをご利用ください。
あなたの予算・要望に合ったハウスメーカー・工務店の実際の住宅プラン(資金計画含む)を比較できるので、具体的な費用イメージを持ちながら資金計画が立てられます。
最大5社にプラン作成依頼が可能!
【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で
注文住宅を契約・着工された方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
2.新築住宅資金の贈与の非課税措置を利用する手順
「住宅取得等資金の贈与税」を非課税にするには、税務署に申告する必要があります。
- 申告に必要な書類を準備する
- 贈与税を申告する
- 贈与税を納税する
それぞれにについて解説します。
【手順1】申告に必要な書類を準備する
申告には下記の書類が必要になります。
贈与税の申告書は「税務署でもらう」、または国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成することが可能です。
| 必要書類 | 取得場所 |
|---|---|
| 贈与税の申告書 | 税務署または 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー |
| 贈与を受けた人の戸籍謄本 | 役所 |
| 源泉徴収票 | 勤務先 |
| 建築請負契約書 または売買契約書の写し |
建築会社や不動産会社 等 |
| 登記事項証明書 | 登記所または法務局証明サービスセンター |
| 省エネ住宅等を示す書類 | 建築会社に準備を依頼する |
参照:国税庁「住宅取得等資金の贈与税の特例に係る「チェックシート」及び「添付書類」の区分<令和5年分用>」
必要書類等の内容については年度によって変更される場合がありますので、しっかりと確認しましょう。
【手順2】贈与税の申告をする
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの期間に贈与税の申告を行います(3月15日が土日の場合は翌日)。
贈与税は必要書類を管轄の税務署に持参または郵送で提出するほか、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxで提出することができます。
なお、e-Taxを利用する際は必要書類をPDFで送信する必要があるので、注意が必要です。
【手順3】贈与税を納税する
贈与税を申告して納税額が確定したら、3月15日までに税金を納めます。
贈与税は現金一括で納付するのが原則ですが、次の条件を満たして本来の納付期限までに所轄の税務署長に必要書類を提出した場合は、5年以内に延納できます。
- 贈与税額が10万円を超えていること
- 現金による一括納付が難しい理由があること
- 延納する税額が100万円超もしくは延納期間が3年超のときは担保を提供すること
ただし、延納すると利子税が発生するため、本来の贈与税額よりも増えることがあるので注意が必要です。
【自分の予算に合ったハウスメーカー・工務店を効率よく探したい方へ】
全国には数万社のハウスメーカーがあるといわれています。
手当たり次第に調べだすと、無駄な時間や労力をかけてしまうので注意してください。
おすすめは、まず無料のHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスをご利用いただくことです。詳しくは下記のサービスページをご覧ください。
3.新築住宅資金の贈与の非課税措置を利用できるケース/利用でいないケース
「住宅資金贈与の非課税措置」を利用できるかどうかについて、ケースごとに解説します。
| 贈与の非課税措置を 利用したいケース |
できる/ できない |
内容 |
|---|---|---|
| 夫が妻の親から贈与してもらう | できない | 住宅資金贈与の非課税対象となるには、自分の父母や祖父母などの「直系尊属」からの贈与が条件。 |
| 妻が自分の親から贈与してもらったのに、家の名義は夫のみ | できない | 贈与を受けたら、住宅の名義も持つこと。 住宅を共有名義にすれば、夫婦それぞれが住宅取得資金の贈与税非課税制度を利用すること可能。 |
| 贈与金を住宅ローンの返済に使う | できない | 贈与された翌年の3月15日までに、贈与された全額を使って住宅を取得する必要がある。 |
| 土地代金に使った | できる | 新築住宅を建てる前の土地を購入する場合でも対象。 |
| 二世帯住宅に使った | できる | 二世帯住宅にも適用されるが、住宅の名義に注意が必要。 |
| 贈与額が400万円なので、申告しなかった | できない | 納税額0円でも申告が必要。 贈与税の申告をすれば、特別に非課税になる。 |
| 贈与を受けてから、3年後に家を建てた | できない | 贈与された翌年の3月15日までに住宅を取得して、居住する必要がある。 |
| 住宅取得と子育て支援のための親からの援助も非課税にしたい | できる | 住宅取得以外にも「教育資金」や「結婚・子育て」資金の贈与税の非課税措置がある。 |
参照:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
この記事のポイント まとめ
住宅資金贈与の非課税措置とは、父母・祖父母などの「直系尊属」から住宅取得のための贈与を受けたときに、一定の条件を満たすことで贈与税の優遇が受けられます。
詳しくは「1.【2024年最新版】新築住宅資金贈与の非課税枠について」で解説しています。
非課税枠は質の高い住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円までです(2022年1月1日~2026年12月31日まで適用)。
詳しくは「1-2.非課税枠は最大1,000万円まで」をご覧ください。
「住宅取得等資金の贈与税」を非課税にするには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの期間に贈与税の申告を税務署にする必要があります。
- 申告に必要な書類を準備する
- 贈与税を申告する
- 贈与税を納税する
「2.住宅資金贈与の非課税措置を利用する手順」で詳しく解説しています。