
不動産売却時の仕訳方法の理解は、確定申告・税務申告や会計処理をスムーズに進めるために不可欠です。個人事業主と法人では仕訳の方法や経費の計上方法が異なるため、それぞれに適した処理が求められます。
本記事では、不動産売却時の仕訳の基本的な方法から仕訳例、注意すべきポイント、さらに困ったときの相談先までを詳しく解説します。場合によっては、専門家のアドバイスを活用して、仕訳を円滑に進めましょう。

大橋 誠一
様々な規模や業種の企業での税務監査・財務諸表監査経験を有し、国税不服審判所の国税審判官として、法人税・所得税・相続税・消費税・加算税の審査請求事件の調査・審理に従事。税務署長・国税局長による課税処分を取消判断を行ってきた。
Contents
1.不動産売却の仕訳を行うための基礎
不動産を売却したあとは、仕訳を正確に行うことが重要です。ここでは、不動産売却に関する仕訳の基本的な知識を詳しく解説します。
これらの基礎知識を押さえておくことで、税務申告や経理処理をスムーズに行えるでしょう。
1-1.個人・法人で異なる勘定科目
まず、個人事業主と法人では不動産売却時に使用する勘定科目が異なります。
不動産事業を営んでいない個人事業主が事業用の不動産を売却する場合、売却益は「譲渡所得」として扱われます。
利益が出た場合は「事業主借」、損失が出た場合は「事業主貸」として記録してください。
一方、法人の場合はより詳細な勘定科目を使用します。
不動産売却による利益は「固定資産売却益」、損失は「固定資産売却損」として記録します。
また、個人事業主・法人のいずれも、売却した不動産の取得価額は「土地」と「建物」に分けて仕訳します。
関連する費用は「一般管理費」として、「支払手数料」や「租税公課」などの勘定科目を使用して計上しましょう。
法人は活動の全てが営利目的であり不動産の売却もその法人の課税所得を構成するため「売却益」「売却損」という損益科目を用います。しかし、個人事業主は不動産の売却は事業所得を構成せず、別の所得である譲渡所得に区分されるため、事業所得に反映させないために「事業主借(=事業主からの借入金)」「事業主貸(=事業主に対する貸付金)」という資産・負債の科目を用いるのです。

1-2.「簿価」を基準に売却益を計算
不動産売却時の利益や損失を計算する際には、「簿価(帳簿上の価値)」を基準とします。
簿価は、不動産の土地部分は取得価額、不動産の建物部分は取得価額から減価償却費を差し引いた金額になります。
例えば、建物の購入価格が1,000万円で、減価償却費が200万円の場合、簿価は800万円になります。
この簿価と売却価格の差額が売却益または売却損です。
法人の場合でいえば、簿価が売却価格より低ければ固定資産売却益、簿価が売却価格より高ければ固定資産税売却損として仕訳します。
1-3.仕訳の日付は「売買契約日」か「引き渡し日」
仕訳を行う際の日付は、「売買契約日」か「引き渡し日」です。
一般的には、実際に所有権が移転する引き渡し日を基準としますが、場合によっては売買契約日を基準にすることもあります。
これは、契約書に明記された日付に従う必要があるためです。正確な日付を設定し、税務上の処理を正確に行いましょう。
1-4.土地部分の売却には消費税がかからない
不動産の売却においては、建物部分には消費税がかかりますが、土地部分には消費税がかかりません。
ただし、不動産会社に仲介してもらい売却した場合は、不動産会社に支払う仲介手数料に消費税がかかります。
土地だけの売却でも、土地の取引自体には消費税が発生しませんが、仲介手数料等の費用には消費税が発生する点に注意しましょう。
「売買契約日」と「引き渡し日」のいずれでも良いと思うかも知れませんが、特に個人事業主の場合には、所有期間が短いと「短期譲渡」として通常よりも高い税率が課されることになりますので選択には注意が必要です。
仮に「売買契約日」と「引き渡し日」が年を跨ぐ場合には、「引き渡し日」を選択すると納税のタイミングを1年遅らせることができます。

2.【個人・法人別】不動産売却の仕訳例
ここでは、不動産事業を行っていない個人事業主と法人が不動産を売却した場合の具体的な仕訳方法を紹介します。
2-1.個人事業主の仕訳方法
個人事業主による事業用の不動産売却では、主に「土地のみを売却する場合」と「土地と建物を同時に売却する場合」があります。また、売却益が出た場合と損失が出た場合のどちらかによっても仕訳方法は変わります。
売却益が出た場合は「事業主借」を使い、損失が出た場合は「事業主貸」を使いましょう。
土地のみを売却した場合
土地のみを売却した場合、消費税がかからないため、売却金額をそのまま計上します。
例えば、次の前提で仕訳してみます。
売却益が出た
- 売却金額:1,000万円
- 取得価額:800万円
- 仲介手数料:30万円
この場合、不動産売却時の仲介手数料は経費算入できるため、借方の普通預金と相殺して計上できます。
仕訳の詳細は、以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 970万円 | 土地 | 800万円 |
| 支払手数料 | 30万円 | ||
| 事業主借 | 200万円 | ||
この例ではわかりやすいように消費税を入れていませんが、実際には仲介手数料には消費税がかかります。
消費税
あとで消費税の仕訳も含めて解説するため、ここでは土地のみの売却時の仕訳をしっかりと理解してください。
次に、以下の条件で仕訳してみましょう。
損失が出た
- 売却金額:700万円
- 取得価額:800万円
- 仲介手数料:30万円
仕訳の詳細は、以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 670万円 | 土地 | 800万円 |
| 支払手数料 | 30万円 | ||
| 事業主貸 | 100万円 | ||
土地と建物を同時に売却した場合
建物を同時に売却した場合は、建物にのみ消費税がかかります。その点に注意して、次の条件で仕訳してみましょう。
売却益が出た
- 売却金額:土地500万円、建物600万円(+消費税60万円)
- 取得価額:土地400万円、建物500万円
- 仲介手数料:50万円(+消費税5万円)
仕訳の詳細は、以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 1,105万円 | 土地 | 400万円 |
| 事業主借 | 100万円 | ||
| 建物 | 500万円 | ||
| 事業主借 | 100万円 | ||
| 支払手数料 | 50万円 | ||
| 仮払消費税 | 5万円 | ||
| 仮受消費税 | 60万円 | ||
わかりやすいように土地と建物で事業主借を分けて仕訳していますが、まとめて計上してもかまいません。
損失が出た
- 売却金額:土地400万円、建物500万円(+消費税50万円)
- 取得価額:土地500万円、建物600万円
- 仲介手数料:50万円(+消費税5万円)
仕訳の詳細は、以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 895万円 | 土地 | 500万円 |
| 事業主貸 | 100万円 | ||
| 建物 | 600万円 | ||
| 事業主貸 | 100万円 | ||
| 仮受消費税 | 50万円 | ||
| 支払手数料 | 50万円 | ||
| 仮払消費税 | 5万円 | ||
2-2.法人の仕訳方法
法人による不動産売却にも、主に「土地のみを売却する場合」と「土地と建物を同時に売却する場合」があります
法人が不動産を売却した際に仕訳で使う勘定科目は「固定資産売却損」や「固定資産売却益」です。個人事業主とは仕訳方法が違うため注意してください。
土地のみを売却した場合
以下を例にして仕訳してみましょう。
売却益が出た
- 売却金額:1,000万円
- 取得価額:800万円
- 仲介手数料:30万円(+消費税3万円)
仕訳の詳細は、以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 967万円 | 土地 | 800万円 |
| 支払手数料 | 30万円 | ||
| 仮払消費税 | 3万円 | ||
| 固定資産売却益 | 200万円 | ||
損失が出た
- 売却金額:700万円
- 取得価額:800万円
- 仲介手数料:30万円(+消費税3万円)
仕訳の詳細は、以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 667万円 | 土地 | 800万円 |
| 支払手数料 | 30万円 | ||
| 仮払消費税 | 3万円 | ||
| 固定資産売却損 | 100万円 | ||
土地と建物を同時に売却した場合
それでは、土地と建物を同時に売却したとして、以下を例に仕訳しましょう。注意すべきは、土地には消費税がかからず、建物に消費税がかかる点です。
売却益が出た
- 売却金額:土地500万円、建物600万円(+消費税60万円)
- 取得価額:土地400万円、建物500万円
- 仲介手数料:50万円(+消費税5万円)
仕訳の詳細は、以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 1,105万円 | 土地 | 400万円 |
| 固定資産売却益 | 100万円 | ||
| 建物 | 500万円 | ||
| 固定資産売却益 | 100万円 | ||
| 仮受消費税 | 60万円 | ||
| 支払手数料 | 50万円 | ||
| 仮払消費税 | 5万円 | ||
「固定資産売却益」はわかりやすいように「土地」と「建物」で分割して算出しましたが、まとめて計上しても問題ありません。
損失が出た
- 売却金額:土地400万円、建物500万円(+消費税50万円)
- 取得価額:土地500万円、建物600万円
- 仲介手数料:50万円(+消費税5万円)
仕訳の詳細は、以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 895万円 | 土地 | 500万円 |
| 固定資産売却損 | 100万円 | ||
| 建物 | 600万円 | ||
| 固定資産売却損 | 100万円 | ||
| 仮受消費税 | 50万円 | ||
| 支払手数料 | 50万円 | ||
| 仮払消費税 | 5万円 | ||
3.不動産売却にかかる経費の仕訳方法
不動産を売却する際には、さまざまな経費が発生します。これらの経費についても正確に仕訳を行い、会計帳簿に記録することが重要です。ここでは、不動産売却にかかる代表的な経費とその仕訳方法について詳しく解説します。
ここでは以下の費用の仕訳方法を解説します。
- 仲介手数料
- 登記費用
- 解体費用
- 修繕費用
3-1.仲介手数料
まず、不動産の売却に際しては、不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。先述しましたが、この手数料には消費税が課されるため、消費税部分も含めて仕訳を行います。
以下の例で仕訳してみます。
・仲介手数料:30万円(消費税3万円)
仲介手数料は「支払手数料」の勘定科目で仕訳します。仕訳の詳細は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 支払手数料 | 30万円 | 普通預金 | 33万円 |
| 仮払消費税 | 3万円 | ||
仲介手数料は「売却金額 × 3% + 6万円」に消費税が加算される計算式が一般的であり、不動産を売却する際には、最終的な手取り金額がいくらになるかが最大の意思決定ポイントになるはずですから、あらかじめこの算式に当てはめることで、手取り金額の目安を試算することができるでしょう。

3-2.登記費用
不動産売却に伴う登記の変更手続きが必要です。この登記費用も経費として計上します。
以下を例に仕訳しましょう。
・登記費用:10万円
登記費用も司法書士などに支払う手数料のため、勘定科目は支払手数料です。仕訳の詳細は、以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 支払手数料 | 10万円 | 普通預金 | 10万円 |
不動産の売却の登記義務者は売主にあり、売主が負担する登記費用は司法書士に「登記原因証明情報(一般的に売渡証書と呼ばれるもの)」を作成してもらうための報酬になります。
そして、登記により買主に所有権が移転しますが、その際に法務局に支払う登録免許税は買主が負担するのが通常ですので、売主は気にする必要がありません。

3-3.解体費用
古い建物を解体して土地を売却する場合は、解体費用が発生します。消費税がかかる場合は、仲介手数料の例を参考に消費税も記載してください。
以下の前提を基に、仕訳しましょう。
・解体費用:50万円
解体工事の費用には「固定資産除却損」の勘定科目を使用してください。仕訳の詳細は、以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 固定資産除却損 | 50万円 | 普通預金 | 50万円 |
3-4.修繕費用
売却前に建物をリフォームする場合には、この費用も経費として計上します。また、リフォーム費用(修繕費用)には、消費税がかかる場合もあります。
以下を例にして仕訳をしましょう。
・修繕費用:20万円(消費税2万円)
仕訳の勘定科目には「修繕費用」を使用するため、以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 修繕費用 | 20万円 | 普通預金 | 22万円 |
| 仮払消費税 | 2万円 | ||
不動産売却に伴うそのほかの経費としては、事務手数料やその他雑費が挙げられます。これらの費用には、支払手数料や雑費などの勘定科目を使用しましょう。
4.不動産売却の仕訳を行う際の注意点
不動産売却後に仕訳を行う際には、いくつかの重要なポイントに注意してください。注意点を理解して正確に仕訳を行うことで、税務申告や会計処理がスムーズになります。
4-1.個人と法人では会計処理が異なる
先述したとおり、個人事業主と法人では、不動産売却に関する会計処理の方法が異なります。
個人事業主の場合、事業用不動産の売却であっても「譲渡所得」に区分されます。
これに対して、法人の場合は所得区分は関係なく、法人税が課されます。
また、個人事業主は簡易な仕訳方法を用いる場合が多いのに対し、法人はより詳細な勘定科目を用いて仕訳を行うのが一般的です。
4-2.個人と法人では減価償却の方法が異なる
不動産の減価償却の方法も、個人事業主と法人で異なります。
建物の減価償却方法には定率法と定額法がありますが、どの方法を用いるかは原則として、法律で決められています。
個人の場合は、定額法。
法人の場合は平成10年3月31日以前の取得であれば定率法、以降の取得であれば定額法となります。
なお、償却方法を選択することもできますが、その場合は税務署への届け出が必要になります。
4-3.経費計上のため領収書は確実に保管する
不動産売却に伴う経費を正確に計上するには、支出に関する領収書を確実に保管することが重要です。
仲介手数料や登記費用、修繕費用など、売却に関連するすべての経費の領収書を保存し、経費計上の際に活用しましょう。
領収書がないと経費として認められない場合があるため、注意が必要です。
5.不動産売却の仕訳で困ったときの相談先
不動産売却の仕訳で困った場合には、以下のような専門家に相談してみましょう。
- 税務署
- 税理士
- 公認会計士
- 不動産会社の担当者
個人事業主であれば、まず税務署への相談を検討してみましょう。税務署への相談は無料のためです。
記帳に関する相談は、個人課税部門が行います。記帳指導担当へ連絡してみましょう。
税務に関する専門家は税理士、会計に関する専門家は公認会計士です。
仕訳含めた記帳に関する相談や代行は、税理士と公認会計士のどちらにも依頼できます。
また、不動産を売却した不動産会社に相談する方もいらっしゃいます。
不動産が関わる仕事を担う不動産会社ですから、知っている範囲で助言をしてくれるでしょう。
ただし、税理士法により具体的な税計算の指南や、代行を行うことはできません。
個人事業主の場合は1月1日から12月31日までが計算期間であり、その申告は2月16日から3月15日までの間に行いますが、この時期の税務署はかなり混雑しており、丁寧なアドバイスを期待することは難しいでしょう。
したがって、不動産の売却をしたタイミングで早めに(少なくとも年内に)税務署に相談することをお勧めします。

まとめ
不動産を売却したあとには、正確な仕訳が重要です。個人事業主と法人では仕訳方法や経費計上の方法が異なります。
個人事業主の場合、所得は「譲渡所得」として処理し、「事業主貸」「事業主借」の勘定科目で仕訳を行います。
一方の法人は事業所得として処理し、「固定資産税売却益」「固定資産税売却損」の勘定科目で仕訳を行います。
不動産売却にかかる経費には、仲介手数料や登記費用、解体費用、修繕費用などが含まれます。消費税を含めて正確な仕訳を行いましょう。
また、これらの経費を証明する領収書等は、確実に保管しておきましょう。
不動産売却の仕訳で困ったときは、税理士や公認会計士、不動産会社の担当者、税務署に相談しましょう。
必要に応じて専門家のアドバイスを受け、正確な仕訳と適切な会計処理を行いましょう。
通常の売上、仕入れ、給与支払いなどとは異なり、不動産を売却したときの会計処理はそう頻繁にあるものではなく、それでいて税額に与えるインパクトは大きいものですから、会計処理の誤りひとつで税金の払い過ぎになることや、一転して過少申告によるペナルティを支払うことに発展しかねません。
したがって、根拠資料(契約書や領収書)を見せながら、不動産の売却時の会計処理だけでも確認をしてもらうという専門家の利用方法も一案ではないでしょうか。

- 「不動産を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格
- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
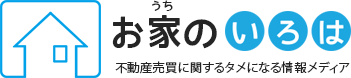
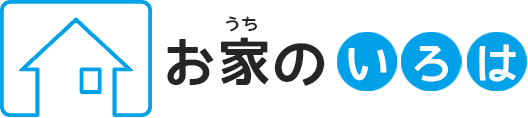

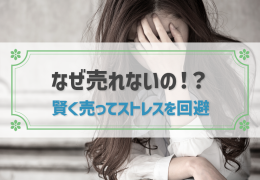






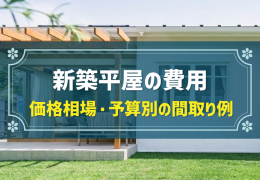

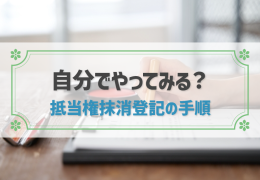




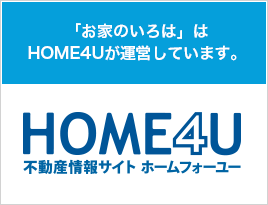
![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)
![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)