
マンションを売却するには、いくらかの税金がかかります。
売却に伴って必ずかかる税金と、売却益が出た際に支払い義務が発生する税金があるため、自身が「どの税金を」「いくら払うのか」を正しく理解しておきましょう。
まだマンションの売却を行っていない方も、税金の仕組みやおおよその税額を知っておくことで、より明確な売却計画を立てられるようになります。
マンション売却について基礎から知りたい方は、『マンション売却の流れ』を併せてご覧ください。
また、マンション以外を売却されている方は『不動産の売却で税金はいくらかかる?』をご覧ください。

松浦 玉枝
東京税理士会所属。準大手税理士法人で約10年の経験を積み、2023年に品川区で独立開業。 法人や個人に対し幅広い税務サービスを提供。クライアントのニーズに柔軟に対応することをモットーとしている。 プライベートでは2児の母。
Contents
1.【一覧表】マンションの売却にかかる税金
マンションを売却するには、以下の税金がかかります。
| 税金の名称 | 課税の特徴 | 目安 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 必ずかかる税金 | 200円~48万円 契約金額により異なる |
| 登録免許税 | 必ずかかる税金 ※住宅ローンを返済中の場合 |
不動産1件につき1,000円 |
| 譲渡所得税 | 売却益がある場合に かかる税金 |
譲渡所得(売却益)の 20.315%又は39.63% |
| 消費税 | 事業として売却する 場合にかかる税金 |
建物売却金額の 10% |
- 印紙税:売買契約書時に必ずかかる税金
- 登録免許税:住宅ローンを借りている方のうち、抵当権抹消登記を済ませていない場合にかかる税金
- 譲渡所得税:譲渡所得(売却益)がある場合にかかる税金
- 消費税:投資物件や事業用不動産を売却する課税事業者にかかる税金
以下でそれぞれを詳しく解説していきます。
1-1.必ず支払う税金
- 印紙税
- 売買契約書の作成にかかる税金。
売買契約書に記載する契約金額に応じて税額が異なり、最低200円、最大48万円となります。
例えば、契約金額が1千万円超え5千万円以下の場合なら、印紙税は1万円です。
なお、令和9年3月31日までは軽減税率が適用されています。印紙税早見表
契約金額 本則税額 軽減税額 10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円 50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円 100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円 500万円を超え 1千万円以下のもの 1万円 5千円 1千万円を超え 5千万円以下のもの 2万円 1万円 5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円 1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円 5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円 10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円 50億円を超えるもの 60万円 48万円 出典:国税庁.”不動産売買契約書の印紙税の軽減措置”.(参照2024-05-21)
- 登録免許税
- 住宅ローン設定時の抵当権抹消にかかる税金。
住宅ローンでマンションを購入した場合、売却時に住宅ローンの完済と抵当権を抹消する手続きが必要です。
抵当権抹消の手続きにかかる登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。
マンション1室の手続きの場合、土地と建物でそれぞれ1件と数えるため、合計2,000円がかかります。
1-2.売却益がでたら支払う税金
- 譲渡所得税
- 譲渡所得(売却益)にかかる税金。
マンションを売却し、譲渡所得が発生した場合は、確定申告が必要です。譲渡所得が発生しない場合(譲渡損失が出る場合)は、原則として確定申告は不要となります。
譲渡所得に対しては、所得税(復興特別所得税を含む)および住民税が課税されます。なお、本記事では、譲渡所得にかかる所得税(復興特別所得税を含む)と住民税をあわせて、「譲渡所得税」と表記します。
譲渡所得は、物件を売却する時点の所有期間によって『短期譲渡所得』と『長期譲渡所得』に分かれ、税率も異なります。
(相続した物件の場合は、被相続人の所有期間を受け継ぎます。)
| 所有期間 | 分類 | 住民税 | 所得税 | 税率合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 9% | 30.63% | 39.63% |
| 5年超え | 長期譲渡所得 | 5% | 15.315% | 20.315% |
※2037年12月31日まで、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされます。上表の所得税率には、復興特別所得税分も含まれています。
譲渡所得は売却金額ではなく、売却で得た利益です。
そのため、マンションを売却しても税金がかからないことも多くあります。
譲渡所得の計算は少し複雑なため、3.マンション売却でかかる税金の計算方法で詳しく解説します。
1-3.事業目的での売却でかかる消費税
- 消費税
- 事業として不動産を売却する場合にかかる税金
投資・事業としての売却や事業用不動産の売却は、いずれも『事業』とみなされ、消費税の課税対象となります。
不動産の売却では、建物部分のみ消費税の課税対象となり、申告と納税が必要です。
ただし、全事業者が消費税を納めるわけではなく、基準期間(通常2年前)の課税売上高が1,000万円を超えている場合など、『課税事業者』に該当する場合のみ申告・納税義務が生じます。
投資用マンションの売却を考えている方は、『【2024年】投資用マンションは売り時?コツを知って利益を最大化しよう』も併せてご覧ください。
印紙税や譲渡所得税、消費税の税額は、売却金額により異なります。
不動産会社の査定を受けて「いくらで売れそうか」を知っておくことで、税金を含めた資金計画をより明確に立てられます。
ただし、必ずしも査定額通りに売却できるとは限りません。
査定額はあくまで予想で、査定を担当する不動産会社や担当者によって結果も異なるので、できるだけ複数社を比較しましょう。
NTTデータグループが運営する、不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)を利用すれば、全国から厳選された2,500社の優良不動産会社の中から、最大6社にまとめて査定依頼ができます。
是非、ご活用ください。
マンションを売却すると、さまざまな税金が発生します。
特に、所有期間によって税率が大きく異なるため、売却のタイミングが重要になります。
また、一定の要件を満たせば、3,000万円の特別控除や譲渡損失の繰越控除といった税負担を軽減する制度が利用できることもあります。
適用できる特例や最適な売却時期はケースによって異なるため、事前に専門家へ相談し、税額を抑える工夫をするのがおすすめです!

2.マンション売却の税金を支払うタイミング
1章で解説したマンション売却にかかる税金は、それぞれ納税のタイミングが異なります。
『印紙税』は、売買契約書を作成するタイミングで支払います。
契約金額に応じた印紙税を、収入印紙を購入し、売買契約書に貼付することで納税となります。
『登録免許税』は、マンションを引き渡すタイミングで支払います。
引き渡し日に、買主が売却金額を決済したのち、住宅ローン完済手続き、並びに抵当権抹消手続きを行い納税となります。
『譲渡所得税』は、売却の翌年に支払います。
所得税(復興特別所得税を含む)は、売却の翌年2月16日~3月16日、確定申告をして納税します。
住民税は、確定申告の後、6月ごろから分割で徴収されます。(一括で支払うことも可能です。)
『消費税』は、課税事業者のみ支払います。
確定申告をへて支払うのが基本ですが、前年の消費税額が48万円を超えている場合は、中間申告と中間納付が必要になります。

3.マンション売却でかかる税金の計算方法
売却時にかかる税金の額を正確に把握するためには、譲渡所得を正しく計算し、適切な税率をかける必要があります。
以下の手順で計算方法を確認しましょう。
STEP1.譲渡所得を計算する
まずは、マンションの売却益である譲渡所得を計算していきます。
※『5.マンション売却で節税できる控除の特例』で解説する控除が適用できる場合は、さらに控除額を差し引きます。
譲渡価額は、マンションを売却した金額です。一般的には売却金額と呼ばれます。
取得費は、マンションの購入金額や、購入時にかかった諸費用です。
譲渡費用は、マンションの売却にかかった諸費用です。
このうち取得費の計算が最も複雑です。マンションの購入代金をそのまま取得費とするのではなく、減価償却費を考慮する必要があるためです。
取得費について
取得費は、マンションの購入金額や、購入時にかかった諸費用です。
取得費のうち『購入にかかった費用』には、購入当時の仲介手数料や購入にかかった手数料、改良費などが含まれます。
『マンションの購入金額』の部分は、当時の建物購入金額から減価償却費相当額を差し引いて求めます。
減価償却とは、資産の価値を時間経過とともに減少させ、経費としていく会計上のルールです。
マンションの資産価値も時間経過とともに減少していくため、減価償却費(これまでに減少した価値)相当額を、購入金額から差し引き取得費とします。
なお、時間経過で価値が減少するのは建物部分で、土地の価格はそのまま取得費にできます。
減価償却費の計算方法には、『定額法』と『定率法』の2つがあります。
マンションの建物部分の減価償却費計算には、定額法を用いるのが一般的です。
以下が定額法の計算式です。
償却率は、建物の耐用年数により異なり、耐用年数は建物の構造や用途により異なります。
居住用マンションのうち、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造は耐用年数70年であり、償却率は0.015となります。
取得費が分からない場合はどうする?
建物の購入金額などが不明な場合、取得費を計算できません。
相続で取得した不動産など、取得時期から長い期間が経過した不動産ほど、こうした取得費不明の状況に陥りやすくなります。
取得費が不明の場合は、不動産を売却した金額の5%を取得費にできます。
譲渡費用を求める
譲渡費用は、売却するためにかかった仲介手数料や、売主が負担した印紙税、建物の解体費用などが含まれます。
引っ越し費用や、維持のための修繕費、固定資産税などは、譲渡費用に含まれません。
STEP2.譲渡所得に税率をかける
譲渡所得を求めたら、所有期間に応じた税率をかけて、税額を求めます。
| 所有期間 | 分類 | 住民税 | 所得税 | 税率合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 9% | 30.63% | 39.63% |
| 5年超え | 長期譲渡所得 | 5% | 15.315% | 20.315% |
例えば、所有期間7年のマンションを売却し、譲渡所得が1,000万円発生した場合は、以下の通り計算します。
<内訳>
・住民税 = 1,000万円 × 5% = 500,000円
・所得税 = 1,000万円 × 15% = 1,500,000円
・復興特別所得税 = 1,500,000円 × 2.1% = 31,500円
取得費が少ないと譲渡所得が多くなり、結果的に税額も増えてしまうので、購入時の資料をしっかり探して確認しましょう。
また、譲渡費用に含められるもの・含められないものが決まっているため、誤って計算しないように注意が必要です!
不安な場合は、専門家に相談すると安心ですね。

4.マンションの売却金額別税額シミュレーション
マンションの売却額によって、実際に支払う税金の額は大きく変わります。
ここでは、売却価格ごとの税額シミュレーションを行い、売却後にどれくらいの税金がかかるのかを具体的に見ていきます。
- マンションを2,000万円で売却した場合
- マンションを3,000万円で売却した場合
なお、『5-1』で解説する3,000万円特別控除の特例は使わずに計算しています。
3,000万円特別控除の特例は、マイホームの売却で使える控除制度です。
今回の例で言えば、どちらも譲渡所得は3,000万円以下になるので、特例の適用により譲渡所得税は0円になります。
2,000万円で売却したマンションの場合
- 対象:自宅マンション
- 所有期間:20年
- 譲渡価額:2,000万円
- 取得費:1,700万円
- 譲渡費用:80万円
まずは、マンションの譲渡所得(売却益)を計算していきましょう。
所有期間は5年を超えており、長期譲渡所得とされるため、税率は20.315%です。
譲渡所得に税率をかけてみましょう。
内訳
・住民税 = 220万円 × 5% = 110,000円
・所得税 = 220万円 × 15% = 330,000円
・復興特別所得税 = 330,000円 × 2.1% = 6,930円
3,000万円で売却したマンションの場合
- 対象:自宅マンション
- 所有期間:20年
- 譲渡価額:3,000万円
- 取得費:2,600万円
- 譲渡費用:110万円
まずは、マンションの譲渡所得(売却益)を計算していきましょう。
所有期間は5年を超えており、長期譲渡所得とされるため、税率は20.315%です。
譲渡所得に税率をかけてみましょう。
内訳
・住民税 = 290万円 × 5% = 145,000円
・所得税 = 290万円 × 15% = 435,000円
・復興特別所得税抜き = 435,000円 × 2.1% = 9,115円
以上、2,000万円、3,000万円でマンションを売却した場合の譲渡所得税を計算しました。
今回のシミュレーションでは、いずれも譲渡所得がありましたが、譲渡所得がなく税金が発生しないケースも多くあります。
確定申告時は譲渡所得の計算を大変に感じるかと思いますが、国税庁のe-Taxを利用すれば、指示通りに入力を進めるだけで譲渡所得や税金の計算をしてくれます。
確定申告を行う方は、是非活用してみましょう。
なお、確定申告については『不動産売却で確定申告を行う手順』で詳しく解説しています。
- 「マンションを売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格
- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
5.マンション売却で節税できる控除の特例
『4.マンションの売却金額別税額シミュレーション』では、控除等を利用せずに計算を行いました。
実際のマンション売却では、以下に紹介するような税金で得する様々な特例制度が設けられているので、対象の方はぜひ活用していきましょう。
なお、いずれの特例も、確定申告での申請が必須になります。
5-1.3,000万円特別控除の特例
3,000万円特別控除の特例は、マイホーム(居住用財産)の売却に適用できる特例で、譲渡所得を最大3,000万円まで控除できます。
マイホームの売却で、譲渡所得が3,000万円以上になるケースは多くないため、特例の適用でほとんどの方が税金を無しにできるでしょう。
ただし、3,000万円特別控除の特例には、併用できない特例がいくつかあります。
中でも、住宅ローン控除との併用ができないため、マンションの買い替えを考えている方は、どちらの制度を利用すべきか慎重に考える必要があります。
なお、マイホームに絞って解説をしていますが、相続した不動産でも一定の要件を満たせば3,000万円の控除が適用できる場合があります。
こちらは、被相続人が生前に、一人でマイホームとして利用していた一定の家屋で、相続後に空き家となるものが対象となります。
3,000万円特別控除について詳しくは、『【3,000万円特別控除】マイホーム売却で使える特例の詳しい要件や申請方法』をご覧ください。
都市部を中心に不動産価格が上昇しているため、売却益が多くなるケースも増えています。
そんなときに3,000万円の特別控除を活用できれば、税負担を大幅に抑えられるので、とても有益な制度です。
ただし、適用には一定の要件があるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
特に、住宅ローン控除との併用ができない点には注意が必要です!

5-2.10年超所有軽減税率の特例
10年超所有軽減税率の特例は、所有期間が10年を超えるマイホームを売却する際に、譲渡所得税(住民税と所得税)の軽減税率を適用できる特例です。
本来は、所有期間5年を超えたマンションには20.315%の譲渡所得税がかかりますが、マイホームの売却かつ所有期間10年超であれば、税率14.21%に軽減されます。
ただし、軽減税率が適用される範囲は、譲渡所得の6,000万以下部分となっています。6,000万円を超える部分は、通常の20.315%で計算されます。
10年超所有軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と併用できますが、住宅ローン控除とは併用できません。
5-3.譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例は、マイホームの買い替えに伴って、譲渡損失が発生した場合に適用できる2つの特例です。
損益通算は、譲渡損失を他の所得と合算できる特例です。
例えば、給与所得500万円の方が譲渡損失300万円の取引をした場合、給与所得から300万円を控除し、その年の所得を200万円にできます。
繰越控除は、損益通算で相殺しきれなかった譲渡損失を、最大3年にわたって繰越できる特例です。
例えば、損益通算を適用しても、譲渡損失200万円分が相殺しきれなかった場合は、この200万円を翌年の損失として計上できます。
通常、譲渡損失は他の不動産の売却益としか相殺できませんが、自宅として住んでいたマンションなら、一定の条件を満たせば給与や事業の収入とも相殺可能です。
さらに、控除しきれなかった損失は3年間繰り越せるので、翌年以降の税負担も軽減できます。
損失が出ても適切に申告すれば税金を抑えられるため、ぜひ活用を検討してみてください!

5-4.取得費加算の特例
取得費加算の特例は、相続した不動産を売却した場合に、相続税の一部を、譲渡所得の計算に扱う取得費に加算できる特例です。
取得費が大きくなることで譲渡所得は減り、譲渡所得税の負担が抑えられます。
なお、小規模宅地の特例と併用する際は、小規模宅地の特例で計算された金額が基準となり取得費加算の特例の効果が小さくなる可能性があります。
6.税金で損をしないために注意したい3つのこと
マンション売却の税金で損をしないためには、次の3つにご注意ください。
6-1.購入代金がわかる書類を探しておく
取得費が分からない場合は、売却金額の5%を取得費として計算します。
この計算では、多くの場合で譲渡所得が大きくなり、税金も高くなってしまいます。
そのため、余計な税金を払わないようにするためには、マンション購入時の書類を探すことが大切です。
売買契約書でなくても、預金通帳の写しなど、購入代金が客観的に確認できるような資料があれば認められる可能性もあるので、証拠書類を集めて税務署に相談してみてください。
6-2.「3,000万円の特別控除」と「住宅ローン控除」は併用不可
「3,000万円の特別控除」はとても有利な制度ですが、マンションを売却して買い替える場合にはご注意ください。
マンションの売却時に「3,000万円の特別控除」を利用すると、2年以内に購入する新居について「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」が利用できなくなります。
※2年以内とは
新居に入居した年、その前年又は前々年に、「3,000万円の特別控除」を受けた場合には、「住宅ローン控除」の適用を受けることはできません。
新居に入居した年の翌年又は翌々年中に、「住宅ローン控除」の対象となる資産以外の資産を譲渡して「3,000万円の特別控除」の適用を受ける場合にも、「住宅ローン控除」の適用を受けることはできません。
このため、「3,000万円の特別控除」と「住宅ローン控除」のどちらを使ったほうがお得なのかを、検討することが大切です。
どうしても両方使いたい場合には、
- 売却時に「3,000万円の特別控除」を使って、賃貸住宅に3年以上住んでから「住宅ローン控除」を使って新居を購入する
- 「住宅ローン控除」を使って先に新居を購入し、3年目の年初から年末までの間に旧宅を売却す
るといった工夫が必要になります。
6-3.売却のタイミングは税制と特例の要件を参考に決める
売却のタイミングを決める際は、税制と特例の要件を考慮しましょう。
譲渡所得税は、所有期間『5年以下』と『5年超』で税率が倍近く異なります。
そもそも譲渡所得が発生しない取引であれば、気にする必要ありませんが、譲渡所得が発生する見込みがある場合は考慮しましょう。
また、各種特例の適用可否に関しても、売却の時期が関係する場合がありますので注意しましょう。
- 3,000万円特別控除:住まなくなってから3年以内の売却で適用
- 取得費加算の特例:相続から3年10カ月以内の売却で適用
売却を始めたい方のうち、税制や特例を考慮しても「タイミングが良い」と言える方は、不動産会社への査定依頼を始めていきましょう。
査定額や売却の力量は、不動産会社や担当者によって異なります。
NTTデータグループが運営する不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)を利用すれば、簡単に複数の不動産会社を比較できるので、信頼できる不動産会社探しにご活用ください。
まとめ
マンションの売却で発生する税金のうち、譲渡所得(売却益)に対して課税される住民税と所得税(復興特別所得税)は、大きな金額になる場合もあるため注意が必要です。
これら住民税と所得税は、まとめて譲渡所得税とよばれることも多いので、税金について学ぶ際は、混同に注意しましょう。
また、譲渡所得税の他に『印紙税』『登録免許税』、投資目的の売却では『消費税』がかかる場合もあります。
譲渡所得税に比べると少額で、また税額の計算も難しくありません。
譲渡所得税の計算のうち、譲渡所得の算出については、抵抗を感じる方も多くいます。
本記事『4.マンションの売却金額別税額シミュレーション』を参考に、計算に慣れておきましょう。
- 「マンションを売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格
- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
不動産を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
特に譲渡所得税は、所有期間によって税率が変わるため、売却のタイミングが重要です。
3,000万円特別控除などの節税できる特例もあるため、適用条件を確認しましょう。
また、納税のタイミングも異なるため、計画的な資金準備が大切です。
税額試算や最適な節税対策のためにも、税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

あなたのマンション、いくらで売れる?
無料で査定価格をお取り寄せ

「これからマンションを売ろうと思っているけど、何から始めれば良いかが分からない」
と、お悩みでしたら、不動産会社に査定を依頼してみることから始めましょう。
「HOME4U(ホームフォーユー)」は、複数の不動産会社にまとめて査定を依頼できるサービスです。
しかも、大手不動産会社も、地域に密着した中小企業とも、提携している一括査定サイトは「HOME4U」だけ。
NTTデータグループが23年以上運営している老舗の不動産一括査定サイト。提携している不動産会社は、厳しい審査を潜り抜けた信頼できる会社のみです。安心して査定をご依頼ください。
完全無料
最大6社の査定価格を
まとめて比較でより高く!
マンション売却の記事を探す
マンション特有の管理費や修繕積立金、売却のコツ、査定ポイントまで詳しく解説。失敗しない売却に向けた実践的なノウハウを提供します。
税金・控除の記事を探す
不動産売却時の譲渡取得税や住宅ローン控除、登録免許税・不動産取得税など、不動産売買や建築に関わる各種税金の仕組みと節税対策をわかりやすく解析しています。 最新の税制改正や控除条件のほか、申告手続きや必要書類、よくある誤解についても丁寧に紹介しています。 初めての取引でも安心して臨める知識を身につけたい方に役立つ情報をまとめています。




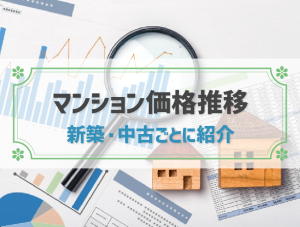
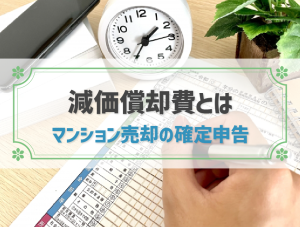
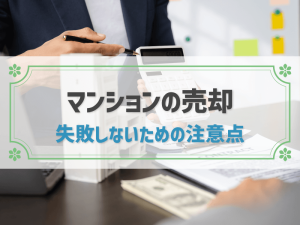
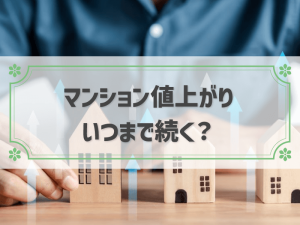




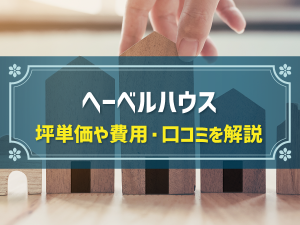
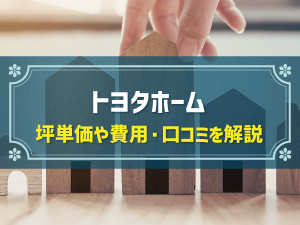


![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)
![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)