
不動産を売却するときには、さまざまな税金が発生します。なかには計算方法が複雑なものもあるため、売却をスタートする前に仕組みをきちんと理解しておくことが大切です。
今回は不動産売却でかかる税金の種類や計算方法、支払いのタイミングをまとめて解説します。また、計算が複雑な譲渡所得税については、いくつかの具体例をもとにシミュレーションしながら見ていきましょう。
不動産売却について基礎から詳しく知りたい方は『不動産売却の基本』『マンション売却で失敗・損しないための注意点』も併せてご覧下さい。
Contents
1.不動産を売却したときにかかる税金の一覧

不動産売却に関係する税金は全部で4種類あります。まずはどのような税金があるのか、一覧表でチェックしておきましょう。
| 費用の項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 売買契約時の契約書に かかる税金 |
1,000円~60,000円 |
| 登録免許税(※) | 抵当権の抹消登記に かかる税金 |
1,000円× 件数 |
| 消費税 | 仲介手数料などに かかる税金 |
- |
| 譲渡所得税 | 売却によって利益が 出た場合にかかる税金 |
譲渡所得× 所有期間に応じた税率 |
※抵当権が設定された不動産を売却する場合に発生
それぞれの税金は計算方法だけでなく、発生するタイミングも違います。
それぞれの内容や費用について、解説します。
1-1.印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約書に貼付する収入印紙代のことです。売買契約においては、売り主と買い主のそれぞれに契約書を用意する必要がありますが、通常はお互いが1通分ずつ費用を負担することとなります。
印紙税額は取引金額によって異なり、不動産売買においては、令和9年3月31日までに契約書を作成すれば、通常よりも低い軽減税率が適用されます。取引額ごとの税額は以下の通りです。
| 契約金額 | 通常の 税額 |
軽減後 税額 |
|---|---|---|
| 100万円超 500万円以下 |
2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 |
10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 |
20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 |
60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超 5億円以下 |
100,000円 | 60,000円 |
軽減措置の適用期間については、本来令和2年の3月31日までとされていたものが、現行の状態まで2年間延長されたという経緯があります。今後も変更が行われる可能性も十分に考えられるので、令和4年3月31日以降の取引を検討している場合には、最新の情報を確認しておきましょう。
1-2.登録免許税
登録免許税とは、不動産の名義変更を行うときに必要となる税金です。不動産売却時に支払いが発生する場合があります。
売り主に登録免許税の支払いが発生しないケースは、抵当権の設定のない売り主から買い主へ所有権の移転登記手続きを行う場合です。こちらについては買い主が費用を負担するのが一般的です。
売り主が登録免許税を支払わなければならないケースは、「金融機関による抵当権が設定されているとき」です。住宅ローンを借りて購入した不動産を売却するときには、引き渡しまでに返済を行って、金融機関による抵当権を抹消しなければなりません。
また、すでに完済をしていたとしても、抵当権の設定登記は自動的に抹消されるわけではないので、売却前に手続きを行う必要があります。完済したタイミングで、金融機関から手続きに関する書類が送付されるので、案内にしたがって済ませましょう。
このとき、登記の費用として「1件あたり1,000円」の登録免許税が発生します。「件数」は不動産の筆数を示しており、たとえば通常の一戸建てやマンションなら「土地と建物それぞれの費用」が必要です。
そのため、登録免許税は「2,000円」となります。しかし、まれなケースではありますが、2筆の土地にまたがって建物が建てられている場合には、2筆分の土地と建物の「計3件分」の費用が発生します。
費用としてはそれほど大きなものではありませんが、手続きにミスがあると売却時にトラブルが生じてしまう可能性もあるので、丁寧に状況を把握することが大切です。
1-3.消費税
不動産の売却においては、不動産会社に支払う「仲介手数料」、司法書士に支払う「登記代行手続き費用」、金融機関に支払う住宅ローン繰り上げ返済の「事務手数料」などが消費税の課税対象です。2021年10月現在は10パーセントの税率が適用されています。参考までにそれぞれの費用の計算方法や目安金額を見ておきましょう。
仲介手数料は法律によって上限額が決められており、400万円を超える取引では「売却代金×3パーセント+6万円」で計算することができます。たとえば、売却代金が3,000万円なら、「3,000万円×3パーセント+6万円=96万円(上限)」に消費税10パーセントが加算されるため、合計では「105.6万円」となります。
司法書士に支払う報酬とは、抵当権の抹消手続きを依頼した場合の費用です。「1~2万円」が相場とされているので、手続きが難しく、自分で行うのに不安がある場合には、専門家である司法書士に依頼するほうが安心です。
また、住宅ローン残債がある不動産を売却するためには、引き渡しまでに一括返済を行う必要があります。このときに発生するのが事務手数料であり、費用は金融機関や利用する窓口によって異なりますが、数万円程度が相場です。
売却にかかる他の費用について詳しくは『 【不動産売却の費用・税金一覧】計算方法や各手数料も併せて解説 』をご覧ください。
マンションを売却される方は『マンション売却時の税金と節税で注意したい5つのこと』も併せてご覧ください。
2.不動産売却で発生する譲渡所得税について

不動産売却後は税金を確定申告しなければならない可能性があります。確定申告が必要となるのは、「譲渡所得」が発生した場合です。
「譲渡所得」とは、不動産の売却によって発生した売却益で、譲渡所得税の課税対象となります。つまり、利益が出た分には税金がかかるということです。ただし、不動産取引においては、単に売却できた金額を利益として扱うわけではありません。
売却代金からさまざまな費用を差し引けるため、譲渡所得が発生しないケースも多いです。譲渡所得税の仕組みはやや複雑なので、1つずつ理解を進めていきましょう。
2-1.譲渡所得税の仕組み
譲渡所得税とは、不動産売却で生まれた譲渡所得に対して課税される「所得税+復興特別所得税+住民税」の総称です。不動産の所有期間によって税率が異なります。譲渡所得が発生したときには、確定申告を行ったうえで、適切な税額を納税しなければなりません。
ただ、先ほどもご紹介したように、譲渡所得は単に売却代金を示すものではありません。次に、譲渡所得の計算方法について見ていきましょう。
2-2.譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、以下の計算式で求めます。
譲渡価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
「譲渡価格」とは、不動産の売却価格に固定資産税と都市計画税の精算金を足したものになります。精算金とは1月1日時点の所有者がその1年分の各税金を課せられますが、不動産を売却する際に買い主から売り主に支払う、売却後の期間の税金相当額です。
「取得費」とは、売却した不動産を「購入・取得するためにかかった費用」のことです。具体的には「不動産の購入代金」「土地の造成費用・測量費用」、「購入時の仲介手数料」などが含まれます。
ただ、不動産の購入代金のうち、建物については年数の経過によって価値を消費したとみなされるため、「減価償却費」を差し引いて計算する必要があります。減価償却費は建物の用途によって計算方法が異なり、居住用住宅であれば以下のように求めることができます。
建物の取得価格×0.9×償却率×経過年数=減価償却費
償却率は建物の構造によって異なるので、以下の表を参考にしてください。
| 建物の構造 | 償却率 (マイホーム等) |
償却率 (賃貸マンション) |
|---|---|---|
| 木造 | 0.031 | 0.046 |
| 鉄骨造 (3mm以下) |
0.036 | 0.053 |
| 鉄骨造 (3mm超〜4mm以下) |
0.025 | 0.038 |
| 鉄筋コンクリート造 | 0.015 | 0.022 |
なお、取得費が明確でない場合は、代わりに「概算取得費」として「売却価格の5パーセント」を計上することもできます。しかし、多くの場合は実際の取得費よりも低くなってしまうので、結果的に譲渡所得が膨らんでしまう点には注意が必要です。
「譲渡費用」とは、「売却のためにかかった費用」のことであり、売却時の仲介手数料や印紙税、土地を売るために建物を取り壊した費用などの合計です。売却代金から取得費と譲渡所得を差し引いても利益がある場合には、譲渡所得があったとみなし、譲渡所得税を計算する必要があります。
3.譲渡所得税の具体的な計算方法

譲渡所得を割り出すことができれば、譲渡所得税を計算するのはそれほど難しくありません。ここでは、譲渡所得税の計算方法を解説したうえで、いくつかの具体例をもとに実際に不動産売却にかかる税金のシミュレーションをしてみましょう。
3-1.譲渡所得税の税率
譲渡所得税は、「課税譲渡所得×税率」で求めることができますが、不動産の所有期間5年を境に異なる税率が適用されます。適用区分は、不動産を売却した年の1月1日を基準として、取得から5年が経過しているものは「長期譲渡所得」、5年以下のものは「短期譲渡所得」として扱われます。
区分による税率は以下のとおりです。
| 渡所得の区分 | 税率 |
|---|---|
| 短期譲渡所得 (所有期間5年以下) |
39.63パーセント |
| 長期譲渡所得 (所有期間5年超) |
20.315パーセント |
3-2.譲渡所得税のシミュレーション
譲渡所得税の計算方法をおさらいする意味でも、いくつかの具体例でシミュレーションをしてみましょう。まずは、1つ目のパターンとして、以下の条件で計算を行います。
- 購入物件:3,000万円の鉄筋コンクリート造マンション(居住用)
- 購入額の内訳:土地代1,000万円、建物2,000万円
- 売却価格:3,500万円
- 譲渡費用:120万円
- 購入時にかかった費用:200万円
- 所有期間:3年(短期譲渡所得)
上記の条件では購入にかかった費用と譲渡費用が明確になっているので、まずは建物の減価償却費を計算する必要があります。鉄筋コンクリート造マンションの償却率は、「0.015」なので、計算式は以下の通りになります。
減価償却費
2,000万円(建物購入額)×0.9×0.015×3年=81万円
ここから、譲渡所得税の計算は以下の手順で進めていきます。
取得費
計算式:土地購入額+(建物購入額-減価償却費)+購入にかかった費用
1,000万円+(2,000万円-81万円)+200万円=3,119万円
課税譲渡所得
計算式:売却価格-(取得費+譲渡費用)
3,500万円-(3,119万円+120万円)=261万円
譲渡所得税額
計算式:課税譲渡所得額×税率
261万円×39.63パーセント(短期譲渡所得の税率)=103.4万円
続いて、2つ目のパターンとして、以下のケースで譲渡所得税を計算してみましょう。
- 購入物件:3,000万円の木造一戸建て住宅(居住用)
- 購入額の内訳:土地代1,000万円、建物2,000万円
- 売却価格:3,500万円
- 譲渡費用:120万円
- 購入時にかかった費用:200万円
- 所有期間:8年(長期譲渡所得)
このケースでも、先ほどと同じように建物の減価償却費から計算する必要があります。居住用の木造住宅の償却率は「0.031」なので、計算式は以下の通りです。
減価償却費
2,000万円(建物購入額)×0.9×0.031×8年=446.4万円
ここから、譲渡所得税額を計算すると、以下のようになります。
取得費
計算式:土地購入額+(建物購入額-減価償却費)+購入にかかった費用
1,000万円+(2,000万円-446.4万円)+200万円=2753.6万円
課税譲渡所得
計算式:売却価格-(取得費+譲渡費用)
3,500万円-(2753.6万円+120万円)=626.4万円
譲渡所得税額
計算式:課税譲渡所得額×税率
626.4万円×20.315パーセント(長期譲渡所得の税率)=127.3万円
最後に、3つ目のパターンとして「取得費がわからない」ケースの具体例についてシミュレーションしてみましょう。
- 購入物件:取得費不明の土地
- 売却価格:1,200万円
- 譲渡費用:80万円
- 所有期間:25年(長期譲渡所得)
相続などで土地を取得したときには、購入者が自身ではないため、取得費がわからなくなってしまうケースも少なくありません。この場合は、概算取得費を使って計算することができます。
また、土地のみの場合は減価償却に関する計算は必要ありません。
取得費
売却価格×5パーセント
1,200万円×5パーセント=60万円
課税譲渡所得
計算式:売却価格-(取得費+譲渡費用)
1,200万円-(60万円+80万円)=1,060万円
譲渡所得税額
計算式:課税譲渡所得額×税率
1,060万円×20.315パーセント(長期譲渡所得の税率)=215.3万円
上記のように、取得費が不明の場合は、売却価格に対して大幅な税金がかかってしまうケースが多いです。そのため、売却を検討したときには、できるだけ取得価格がわかる書類を収集することが大切です。
4.譲渡益・譲渡損失の特例

マイホームの売却で生まれた譲渡所得税にはさまざまな特例が設けられており、上手に活用すれば税金が大幅に節約できたり、場合によっては非課税になったりすることもあります。ここでは、「譲渡益が出たとき」と「譲渡損失が出たとき」の2つのパターンに分けて、利用できる特例の仕組みをご紹介します。
4-1.譲渡益の特例
譲渡益が出たときに利用できる特例には以下のようなものがあります。
- 3,000万円の特別控除
- 軽減税率の特例
- 買い換えの特例
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
4-1-1.3,000万円の特別控除
3,000万円の特別控除とは、一定の要件を満たしたマイホームを売却したときに、譲渡所得から最高で3,000万円までが控除される制度です。居住用不動産の売却で3,000万円以上の利益が出るケースはまれなため、要件に適合していれば、多くの場合で譲渡所得税が非課税となります。
4-1-2.軽減税率の特例
「軽減税率の特例」とは、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合に、「6,000万円まで」の譲渡所得が本来の「20.315パーセント」から「14.21パーセント」まで軽減される制度です。この特例は「3,000万円の特別控除」とも併用できるのが大きな特徴です。
4-1-3.買い替え特例
「買い換えの特例」とは、マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年間で買い換えを行った場合に、一定の要件を満たすことで譲渡所得税の課税を繰り延べられる制度です。具体的には、所有期間や売却価格の制限などの条件に適合する場合、新居を売却するときまで課税を先送りにできるという仕組みです。
ただし、この特例はあくまで「繰り延べ」であり、減税されるわけではない点に注意が必要です。また、「3,000万円の特別控除」や「軽減税率の特例」とは併用ができません。
4-1-4.被相続人の居住財産
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」とは、相続で取得した住居を相続開始日から3年後の12月31日までに売却した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除できる仕組みです。
4-2.譲渡損失の特例(損益通算)
マイホームで売却損(譲渡損失)がうまれた場合は、次の2つのケースにおいて、損益通算および繰越控除の特例を利用することができます。
- 住宅ローン残債のあるマイホームの売却で損失が発生した場合
- 一定の要件を満たしたマイホームの買い換え時に損失が発生した場合
1つ目の特例は、所有期間5年以上で住宅ローン残債のあるマイホームを売却したときに、損失分をその年のほかの所得(給与所得や事業所得など)と損益通算できる制度です。その結果、その年に給与所得等で収める所得税や住民税の額を軽減することができます。また、その年だけで通算しきれなかった部分については、以降3年間にわたって繰越控除をすることも可能です。
2つ目の特例は、マイホームの買い換えにおいて、「旧居の所有期間5年以上」「新居を住宅ローンで購入」といった条件を満たした場合に損益通算および繰越控除ができる制度です。
5.不動産に関する税金を納めるタイミング

不動産売却にまつわる税金は、それぞれ納めるタイミングが異なります。
| 税金の種類 | 納付のタイミング |
|---|---|
| 印紙税 | 売買契約時 |
| 登録免許税 | 不動産の引き渡し時 |
| 消費税 | 各種取引が発生したとき |
| 所得税・ 復興特別所得税 |
売却した翌年の2月中旬~3月中旬 |
| 住民税 | 売却した翌年度の6月ころ |
特に注意しておきたいのは、所得税・復興特別所得税と住民税の納付時期が異なる点です。住民税については単体で申告する必要はなく、所得税の申告によって自動的に手続きが済みます。
しかし、確定申告の時期に納付する所得税・復興特別所得税とは異なり、住民税の支払い時期は次年度となります。住民税は地方税なので、具体的な仕組みは市区町村によって異なりますが、4期に分けて納付できるのが一般的です。
「特別徴収」を利用すれば、給与から天引きしてもらうことも可能なので、忘れてしまいそうな場合はこちらを選択しておくと安心です。
6.不動産の確定申告を行う手順
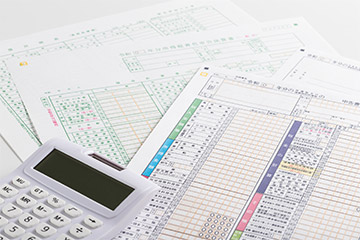
これまで見てきたように、不動産売却によって譲渡益が出たときには、確定申告を行う必要があります。また、譲渡損失が出たときにも、特例を利用するのであれば確定申告を行わなければなりません。
ここでは、確定申告の手順について見ていきましょう。
- 必要書類をそろえる
- 譲渡所得税額を計算する
- 確定申告を行う・必要事項を記入する
- 書類を提出する
6-1.必要書類をそろえる
確定申告に必要な書類は、税務署や国税庁のホームページで入手できるものがほとんどです。具体的な必要書類の種類と入手方法は以下の通りです。
| 書類の種類 | 内容 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 確定申告書B | 所得の種類にかかわらず利用できる申告書 | 税務署・国税庁ホームページ |
| 分離課税用申告書 | 分離課税を申告する際に必要な書類 | 税務署・国税庁ホームページ |
| 譲渡所得の内訳書 | 売却した不動産の情報を記載する書類 | 税務署・国税庁ホームページ |
| 売買契約書のコピー | 取得費の証明に必要な書類 | 購入時・売却時の両方を用意する |
| 各種領収書 | 取得費・譲渡費用の証明に必要な書類 | 各手続き時に発行される |
| 特例に関する書類 | 各種特例を利用するために必要な書類 | 書類によって異なる |
利用する特例によっては、登記事項証明書や耐震基準適合証明書・住宅性能評価書などが必要となるケースもあります。また、住宅ローン利用が条件とされる特例では、金融機関を通じて住宅ローン残高証明書を用意しておく必要もあります。
国税庁のホームページでは、特例の適用を受けるための必要書類チェックシートが用意されているので、事前に確認しておくと良いでしょう。
6-2.譲渡所得税額を計算する
譲渡所得税額を算出するためには、前述の通り、物件の購入費用・譲渡費用・減価償却費などを計算して、課税譲渡所得を割り出す必要があります。各種の特例を利用する場合には、この段階で計算に反映させておきましょう。
譲渡益があった場合には、所有期間の区分に応じた税率をかけて譲渡所得税額を計算します。
6-3.確定申告を行う・必要事項を記入する
税額の計算が済んだら、用意した書類に必要事項を記入していきましょう。主に「申告分離課税用の確定申告」と「譲渡所得の内訳書」を記入にしていきます。
記入する内容に迷ってしまったときには、国税庁のホームページから「確定申告書等作成コーナー」というサポートシステムを利用するのがおすすめです。
また、国税庁の問い合わせ専用窓口を通じて、作成方法やシステムの操作方法について電話で質問をすることも可能です。
6-4.書類を提出する
確定申告書などの提出は、税務署に直接持参するか、郵送、電子申告などの方法でも行えます。損益通算で還付を受ける予定の方は、電子申告のほうが通常よりも1~2週間ほど還付のタイミングが早まるので、受け取りたい時期に合わせて適した方法を選択しましょう。
確定申告についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
7.まとめ
不動産を売却したときにかかる税金には、大きく分けて「印紙税」「登録免許税」「消費税」「譲渡所得税」の4つがあります。
このうち、印紙税や登録免許税、消費税は売却手続きの流れで発生するものです。
しかし、譲渡所得税は売却後に自分で確定申告を行う必要があるため、計算方法や納税の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。特例を活用すれば大幅な節税も可能なので、あらかじめ制度の仕組みや条件を確認しておきましょう。
- 「不動産を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格
- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
この記事のポイント まとめ
不動産の売却で発生した売却益を「譲渡所得」といいます。
譲渡所得は所得税の課税対象となります。ただし不動産売却においては売却して得た金額の全てを利益として扱うわけではなく、費用なども差し引くことができるため、譲渡所得が発生しないケースも珍しくありません。
詳しくは2章「不動産売却で発生する譲渡所得税について」で解説しています。
譲渡益・譲渡損失の特例は主に次の4つです。
- 3,000万円の特別控除
- 軽減税率の特例
- 買い換えの特例
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
詳しくは4章「譲渡益・譲渡損失の特例」で解説しています。

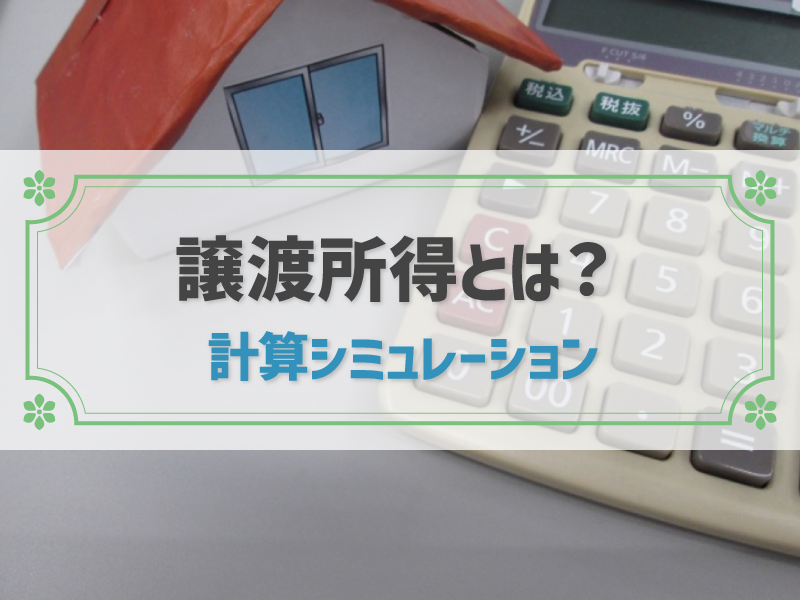
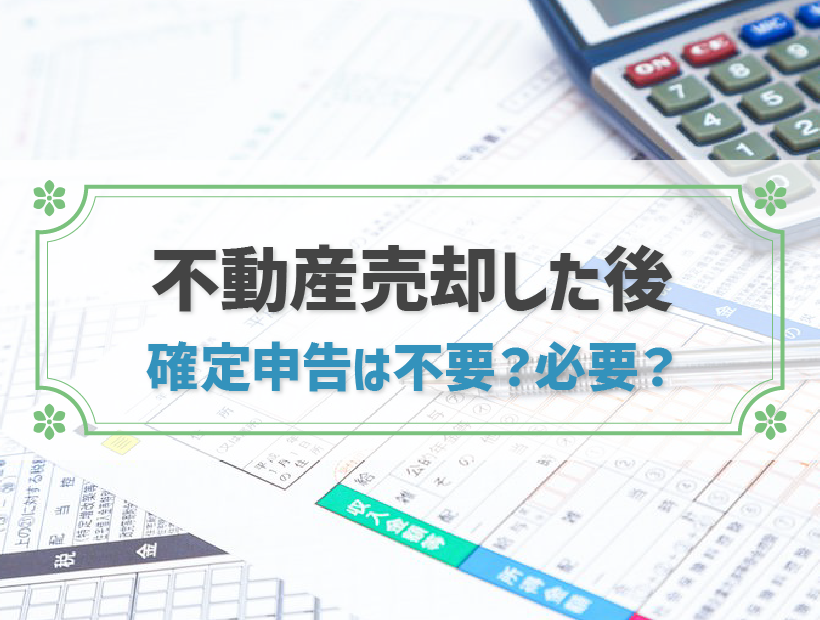






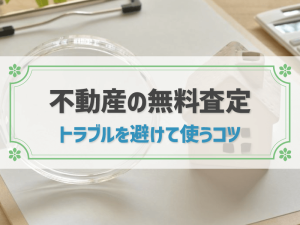
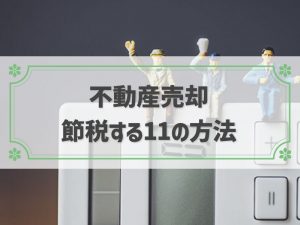


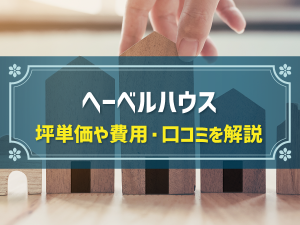
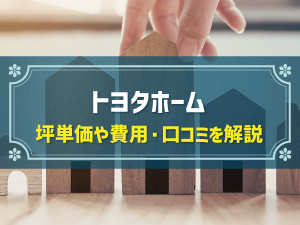


![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)
![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)