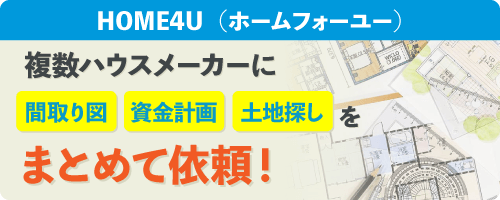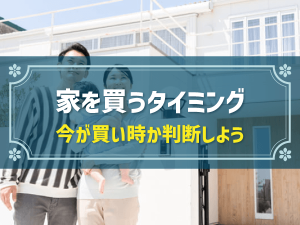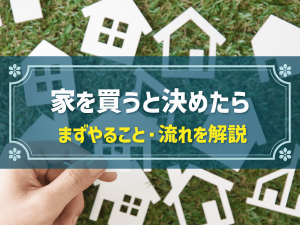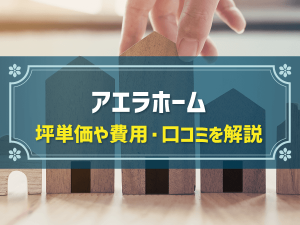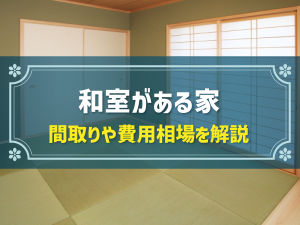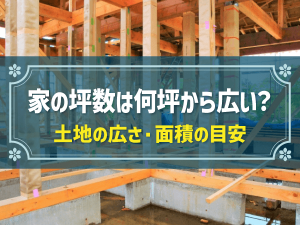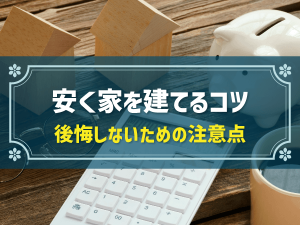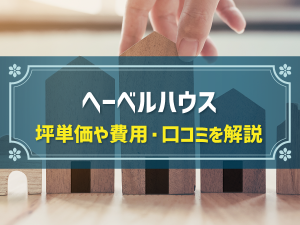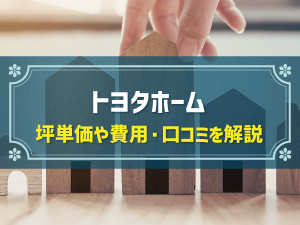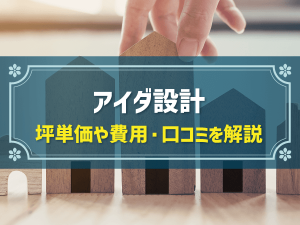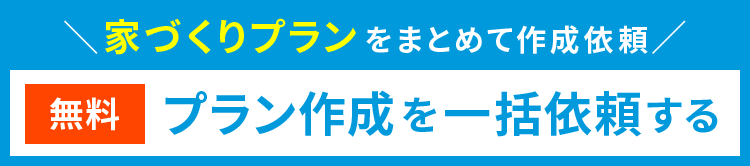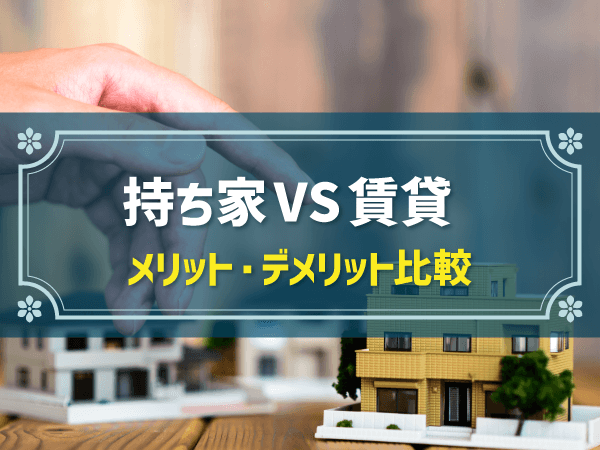
家族が増えて手狭になり、住まいについて本腰を入れて考え始めたけれど、持ち家と賃貸のどちらが得なのか迷っている方もいるのではないでしょうか。
「持ち家」と「賃貸」の比較は、以前から度々注目されているテーマですが、実際にはどちらを選んでいる人の割合が多いのでしょうか?
総務省調べによると、住居世帯のうち、持ち家は調査対象全体の61.2%、賃貸は35.6%となっており、持ち家が約6割を占めていることがわかります。(参考:総務省統計局「 ![]() 平成30年住宅・土地統計調査結果」)
平成30年住宅・土地統計調査結果」)
そこでこの記事は、持ち家か賃貸かを検討している方に向けて、持ち家と賃貸の費用シミュレーションやメリットデメリットなどについて詳しく解説します。
持ち家を選ぶ場合、「注文住宅」にするべきか、「建売住宅や分譲住宅」にするべきかの判断ポイントもお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。
- 持ち家と賃貸の費用シミュレーション
- 持ち家と賃貸のメリット・デメリット
- 注文住宅と建売・分譲住宅の比較
自分はどちらを選択すれば理想の暮らしが叶うのか、マイホームを考える際の参考にしてください。
まとめて依頼!
戸建てにしようかマンションにしようか、あるいは注文住宅にしようか…と、マイホームの種類に迷っている方は「住み替え」の記事もご覧ください。
Contents
1.持ち家と賃貸の費用シミュレーション比較
 まずは、持ち家と賃貸に住み続けた場合、それぞれの生涯コストはどのようになるのか比較してみましょう。
まずは、持ち家と賃貸に住み続けた場合、それぞれの生涯コストはどのようになるのか比較してみましょう。
今回は50年間同じ住まいに暮らすことを想定し、持ち家は家の価格3,000万円、賃貸は家賃15万円に設定してシミュレーションします。
| 費用項目 | 持ち家 | 賃貸 |
|---|---|---|
| 初期費用 |
|
|
| ランニングコスト (毎月) |
|
|
| ランニングコスト (都度) |
|
|
* 返済期間35年、金利1%で計算
上記はあくまでシミュレーションなので、実際にかかる費用は人それぞれ異なります。
参考程度にとどめておきましょう。
1-1.【持ち家】費用シミュレーションのポイント
まず、持ち家の場合、多くの方は住宅ローンを利用します。
この時準備できる頭金(自己資金)の額や返済期間によって、全体の費用に差が出てきます。
持ち家の頭金は家の価格の1~2割程度用意するのが一般的なので、上記シミュレーションでは3,000万円の1割である300万円を35年間で返済する条件で計算しています。
住宅ローンには利息があるので、返済期間が長い分、支払い総額も増えます。
より多くの頭金を用意できたり、毎月の返済負担額を増やせたりするのであれば、結果的には全体の費用を抑えて家を建てられることになります。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
1-2.【賃貸】費用シミュレーションのポイント
一方、賃貸の場合、支払う家賃の額により生涯コストも変わります。
上記シミュレーションでは15万円の家賃で計算していますが、家族が多かったり、職場兼自宅にしたかったり、そもそも家賃相場が高いエリアに住む必要があったりする場合はより多くの家賃がかかるでしょう。
どのような条件で比較するかで、持ち家と賃貸の生涯コストは変わりますが、毎月の負担を抑えたいのであれば、持ち家のほうがおすすめです。
住宅ローンの返済が終われば、毎月支払っていた返済額分家計が楽になりますし、家は資産になります。万が一何かあった際には、家を売却すればよいため、精神的に余裕が持てるでしょう。
また、家が資産として認められていると、クレジットカードや自動車ローン、教育ローンの審査に通りやすくなる傾向にあります。
2.【持ち家】メリット・デメリット比較
 これから新居を考えるのであれば、おすすめは持ち家ですが、持ち家にはメリット・デメリットがあります。
これから新居を考えるのであれば、おすすめは持ち家ですが、持ち家にはメリット・デメリットがあります。
双方を確認したうえで本格的な検討に移るようにしましょう。
2-1.持ち家のメリット
持ち家のメリットは以下のとおりです。
- 資産になる
- 担保価値がある
- 個人の信用度が増す
- 老後の住居費負担が楽
- リフォームなどを行える
先述のとおり、持ち家は資産になるため担保価値もあり、個人の信用度が高まることにつながります。
住居が経年変化で古くなってきても、ある一定の資産価値があるので、将来的に担保として融資を受けることも可能です。
また、住宅ローンを完済したあとは、住居費の負担がかなり楽になります。
老後は固定資産税や維持費用の支払いだけになるので安心感があり、高齢になったとき暮らしやすいように手軽にリフォームができる点もメリットとなります。
2-2.持ち家のデメリット
持ち家のデメリットは以下のとおりです。
- 土地込で資金がかかる
- 税金がかかる
- 住宅ローン金利で返済の負担がある
- 容易に住まいを移せない
- 転勤が多い職業は単身になることが多い
- メンテナンス費用が掛かり続ける
持ち家となると、まとまった購入資金が必要になります。戸建てなら土地代金も予定しなければなりません。また、所有している間は固定資産など税金がかかり続けます。
持ち家を容易に手放すことは現実的ではありませんので、近所トラブルなどがあったり、転勤があったりしても、住み替えは難しいかもしれません。
なお、住宅は経年劣化していきますが、持ち家の場合オーナーがメンテナンス費用の負担をしなければなりません。将来的には、建て替えも検討する時期が来る可能性もあります。
3.【賃貸】メリット・デメリット比較
賃貸のメリット・デメリットには、次のようなことが考えられます。
3-1.賃貸のメリット
- 住み替えが簡単にできる
- 常に新しい物件に移ることができる
- 住居の管理が楽
- メンテナンス費の負担がない
- 収入に合わせて家賃とのバランスを図れる
賃貸は、住み替えを好きなタイミングで自由に行うことが可能です。今よりも築年数の新しい住まいへの住み替えも容易にできる点は、大きなメリットのひとつです。
また賃貸の場合、住居の管理は大家さんや管理会社などが行います。住居が劣化したとき、設備の不具合があったときなど、メンテナンス費用の負担は基本的に負う必要はありません。
収入に変動があったときは、家賃負担が少ない賃貸に移ることも可能です。ずっと固定的な家賃にしばられる心配がなく、家計のバランスを図ることができます。
3-2.賃貸のデメリット
- 老後も住居費負担がある
- 自分でリフォームできない
- 資産がなく信用度が低い
賃貸は、住宅ローンの負担がないかわりに、常に家賃負担があります。老後になっても家賃を払い続けなくてはならない点はデメリットといえます。
また基本的に、賃貸物件は自由にリフォームすることができません。設備が古くなったり、内装が劣化したりしても、不具合がない限り現状維持になります。
賃貸のデメリットとして、資産がないことも挙げられます。個人の信用度としては持ち家に比べて弱いとされることもあります。
4.老後の生活面で見る持ち家と賃貸の比較ポイント
持ち家を前向きに検討している方の中には、「老後も住み慣れた持ち家に住み続けたい」「老後は新築のバリアフリー住宅でのんびり暮らしたい」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、やはり賃貸に比べて「損をしないか」といった不安もありますよね。
老後の生活で持ち家か賃貸かで迷った際には、以下のポイントに注目してみましょう。
- 持ち家に資産価値があるか
- 賃貸を契約する際の保証人はいるか
まず、持ち家が自身の所有物であれば、資産価値があります。持ち家が資産であると、以下のようなメリットがあります。
- リバースモーゲージを利用できる
- 持ち家を売却してバリアフリー住宅新築の資金にできる
- 持ち家を売却して高齢者施設入居の一時金にできる
なお、老後に賃貸暮らしを考える際には、保証人が確保できるかどうかを事前に確認しておきましょう。
最悪の場合、賃貸が借りられなかったり、更新ができなくなったりします。
また、仕事をしているうちは賃貸で暮らし、退職後に持ち家を購入すると考える方もいるかもしれませんが、持ち家を検討するなら早めに行動したほうがお得です。
賃貸で支払った家賃は資産になりませんが、持ち家に支払うお金には資産価値家が生まれます。
さらに言うと、住宅ローンの借り入れには年齢制限があることがほとんどなので、「いずれ買おう」と検討しているのであれば、老後ではなく、なるべく早めに行動したほうがよいでしょう。



5.持ち家を建てるなら「注文住宅」がおすすめ!
持ち家を検討する際には、「注文住宅」や「建売住宅」「分譲住宅」などの選択肢があります。
注文住宅であれば、自分の理想の住まいを実現しやすいため、後悔の少ないマイホームを手に入れやすいです。
下記表で、各住宅の特徴を比較してみましょう。
| 比較項目 | 注文住宅 | 建売・分譲住宅 |
|---|---|---|
| 価格面 | こだわると予算オーバー | 土地+住宅で割安 |
| 設計・工事 | ゼロから建てる | すでに建築済 |
| スピード | 時間がかかる | 購入後に入居できる |
| 完成イメージ | モデルハウスでイメージ | 完成後に見学可 |
| 間取り | 自由に決められる | 変更不可 |
| 設備・こだわり | 自由に決められる | 選択範囲内で可能 |
| デザイン | 自由に決められる | 完成前なら一部可能 |
| アフターサービス | 10年(特約で20年)の保証 ※ | |
| 将来のリフォーム | 設計時に要望可 | 要望不可 |
| ローン | つなぎ融資などで対応 | 一度に手続きできる |
※国土交通省「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にて規定
以下より詳細を解説します。
5-1.注文住宅の特徴とメリット・デメリット
好きなハウスメーカーや工務店を選び、間取りや設備を選択して、自分の好みに合わせて一から家づくりをするのが注文住宅です。
中には、ある程度規格が決まっているタイプの「セミオーダー」と呼ばれる注文住宅もあります。すでに持っている自分の土地に建てるだけでなく、土地から探して注文住宅を建てることもできます。
注文住宅のメリット
注文住宅のメリットは、間取り・外壁・内装・設備、全てにおいて自分で自由に選べることです。家族構成や、ペットのいる生活や家事動線に合わせて、要望を盛り込んだ家づくりが可能です。
こだわりたいポイントを決めて、予算の中でうまくメリハリをつけ調整することもできます。
構造においては、木造系と鉄骨系のメーカーに大きく分かれます。間取りの自由度や断熱性など、それぞれの工法の特徴を比べて、気に入ったメーカーで建築ができます。
注文住宅はオーダーメイドで建てるので、建売住宅のように似た家が建ち並ぶということはありません。
注文住宅のデメリット
一邸ずつ打ち合わせをしてオリジナルの家をつくるため、建築会社との打ち合わせ回数が多くなります。また、設備を選ぶためにショールームへ出向いたり、実際の建築現場や工場へ見学に行ったりすることがあります。
個人差はあるものの、プランが決定するまで、ある程度の時間的な負担は避けられません。また、実例やサンプルを見て、ついつい品質の良いものばかり選んでしまうと予算オーバーになる傾向も見られます。
どこにこだわりを持つのか、メリハリをつけて予算内にまとめられるように選択する必要があります。
5-2.建売・分譲住宅との違い
一般的に、土地と建物がセットになって売られている住宅を建売住宅といいます。
分譲住宅は、いくつかに分割された土地に家が建てられ、セットで販売される住宅のことです。
間取りから外構まで、ほとんどのプランが決まっている状態で販売されます。
すでに完成している場合もありますが、建物完成前から販売活動が行われるケースが大半です。
建売・分譲住宅のメリット
土地と建物がセットで売られるため、一般的に土地と建物(注文住宅)を別々に購入するよりも割安となる傾向があります。
建物が完成前でも概ねのプランが決まっているため、打ち合わせの手間も少なく、入居までの期間が短く済むのもメリットのひとつです。
また、建売・分譲住宅ともに物件の見学会が開催されるため、マンションのモデルルームのように、入居した後のイメージを掴みやすいというメリットもあります。
建売・分譲住宅のデメリット
建売住宅のデメリットは、「自分の好みに合わせて建材などを自由に選べないこと」です。床の色や設備のグレードアップなど、多少は選べるケースもありますが、選択肢が限られます。また、ご自身によっては不要となる設備を除外したり、好みでないデザインの修正をしたりすることもできません。
また、一般的に建売住宅の建物や設備のグレードがそこまで高くはない傾向にあります。注文住宅のモデルハウスを見学することで、建売住宅と注文住宅の差を知ることができるでしょう。
都心や大手ハウスメーカーでは高級路線の建売住宅もありますが、基本的に建売住宅は安価な材料を使用することが多く、購入しやすい価格帯にすることが優先されます。
また、一つのエリアに複数の建売住宅が建てられる場合が多く、外観が似たような家が建ち並ぶためオリジナリティに欠ける点をデメリットに感じるかもしれません。
5-3.注文住宅に向いている人の特徴
注文住宅と建売・分譲住宅の特徴から、それぞれの住宅がどんな人が向いているのかを見ていきましょう。
- 間取りを自由に決めたい
- デザイン、素材、設備をこだわりたい
- 入居(引っ越し)まで1年以上の時間がある
- ハウスメーカーや工務店で選びたい
- すでに土地を持っている
デザインや間取り、品質など細部までこだわりたい方には注文住宅がおすすめです。
ただし、入居予定時期まで9か月~1年くらいの期間が必要ですので、入居を急いでいる方は注意してください。
なお、ある程度の決まった選択肢の中から選びたい場合は、セミオーダー住宅や規格住宅がおすすめです。完成までにかかる日数を短縮することができます。
- 土地と住宅をセットで購入したい
- 安価で新築の一戸建てがほしい
- 間取りやデザインを一から決めるのが面倒
- すぐに入居(引っ越し)したい
- 住みたいエリアに建売住宅・分譲住宅がある
土地を持っていないが希望の建築エリアで建売が販売されているという方、間取りやデザインを一から決めるのが面倒に感じる方、実物を見てから決めたい人、半年以内に入居したい人などは建売・分譲住宅が向いています。

建築条件付きの「売建住宅」とは?
建築条件付き土地の「売建住宅」は、住宅を建てる前に販売をし、契約が締結したのちに、すでに決まっている住宅を建てるケースを指します。購入後に建てらえる建売住宅と理解するとわかりやすいでしょう。
ディベロッパーやハウスメーカーによって定められた選択肢の中から、デザインや間取りを選びます。自由に間取りを組んだり、素材を選んだりすることは難しいのが一般的です。
6.ハウスメーカーの種類と工法
 注文住宅の場合、自分の好きな土地に好きな建築会社で家を建てることができます。
注文住宅の場合、自分の好きな土地に好きな建築会社で家を建てることができます。
ここからは、ハウスメーカーで建てる場合の工法の種類や特徴について解説します。
なお、ハウスメーカーの中には、木造の複数の工法を扱っていたり、木造と鉄骨造の両方に対応していたりする企業もあります。
注文住宅を建てるならハウスメーカーだけでも選択肢は膨大にありますので、まずは無料のHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスである程度絞り込んでから、モデルハウスを見学して詳しい説明を受けるとよいでしょう。
6-1.木造系のハウスメーカー
構造の主要な部分が木材で造られているのが木造住宅です。
日本では木造住宅の文化が長いこともあり、多くのハウスメーカーが木造を採用しています。
木造住宅は「木造軸組工法」「木造枠組壁工法」の2種類に大きく分けられます。
木造軸組工法(在来工法)
積水ハウス、大和ハウス、一条工務店、タマホームなど。日本の木造住宅における主流な工法です。
「柱」「梁(はり)」「すじかい」によって建物を支えます。外壁材や屋根の形状、間取りの自由度が高く、増改築が容易です。
木造枠組壁工法(2×4工法・木質パネル工法)
三井ホーム、三菱地所ホーム、住友不動産ハウジング、ミサワホーム、スウェーデンハウスなど。北米では長い歴史のある工法です。
規格化された木材(2インチ×4インチなど)で枠組みを作り、その上に合板を接合して、面的な床や壁を作ります。
木造軸組工法よりも間取りの自由度がやや低くなりますが、面で支える構造のため耐震性が高くなりやすいです。
また、工場で木材を加工できるため工期が短くすみます。
6-2.鉄骨造系のハウスメーカー
鉄骨造系は構造の主要部分が鉄骨・鉄筋で作られている家です。無機質なイメージを持つかもしれませんが、内装には木材をふんだんに使うこともできます。
鉄骨造
へーベルハウス、積水ハウス、ダイワハウス、セキスイハイム、トヨタホーム、パナソニックホームズなど。
ほとんどは厚さ6ミリ以下の「軽量鉄骨造」ですが、3階建てなど一部の家は6ミリを超える「重量鉄骨造」で造られる場合もあります。
鉄筋コンクリート造
三菱地所ホーム、大成建設ハウジング、レスコハウスなど。鉄筋とコンクリートの両方を組み合わせているため、大きな空間をつくることができます。断熱性や耐火性、遮音性も高いですが、コストは最も高くなります。
6-3.ローコストなハウスメーカー
材料費や人件費を徹底的にコストダウンする、宣伝費をかけない、モデルルームを作らないなど、様々な工夫によってローコストを実現している企業もあります。
- ヤマダホームズ
- タマホーム
- アイフルホーム
- 富士住建
- ユニバーサルホーム
- アイダ設計
このような企業は、若い子育て世代からの需要が特に高い傾向があります。ただし、ローコストな建築会社であっても、グレードの高い設備などのオプションをたくさん付ければ、それなりに建築費は高くなっていきます。
ハウスメーカーを最終的に決定するときには、具体的な間取りプランと見積書の提案を受けた上で、予算とのバランスを見ながら理想を実現できるかどうか検討しましょう。
まとめ
賃貸と持ち家、どちらがよいかは、比較する年齢のタイミングや持ち家の購入条件、家賃負担の額などに違いがあるため、一概には結論を出すことは難しいです。
しかし、約6割の方が持ち家を持っていることは、一定数の方が持ち家を支持していることを意味しているともいえます。
この記事のポイント
総務省調べによると、住居世帯のうち、持ち家は調査対象全体の61.2%、賃貸は35.6%となっており、持ち家が約6割を占めていることがわかります。(参考:総務省統計局「 ![]() 平成30年住宅・土地統計調査結果」)
平成30年住宅・土地統計調査結果」)
- 持ち家に資産価値があるか
- 賃貸を契約する際の保証人はいるか
詳細は「4.老後の生活面で見る持ち家と賃貸の比較ポイント」をご覧ください。
例えば、持ち家には以下のようなメリットがあります。
- 資産になる
- 担保価値がある
- 個人の信用度が増す
- 老後の住居費負担が楽
- リフォームなどを行える
「2.【持ち家】メリット・デメリット比較」以降では、各メリット・デメリットを詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。