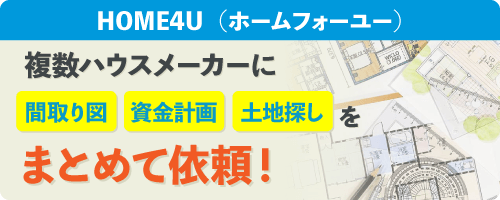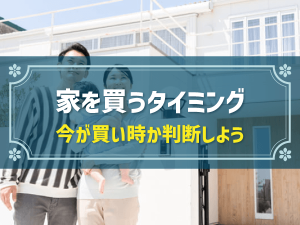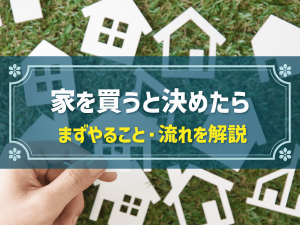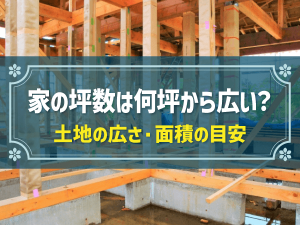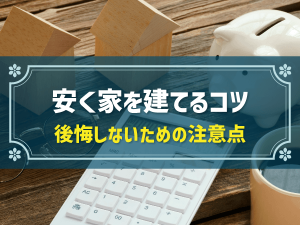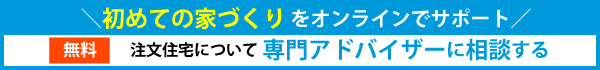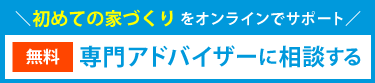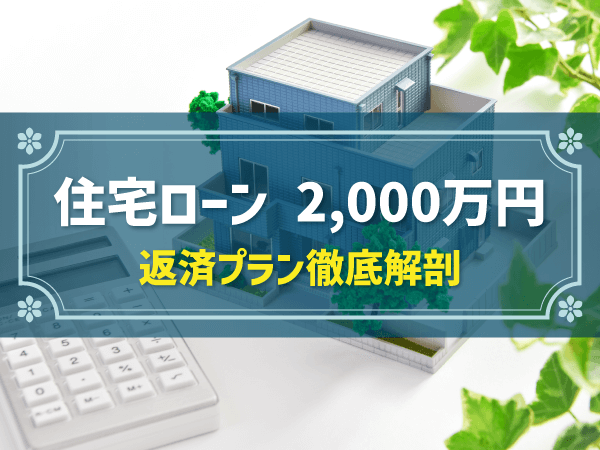
この記事では、2,000万円の住宅ローンを組んで新築住宅を建てたいと考えている方に向け、以下の内容を解説します。
- 2,000万円の住宅ローンを組むのに必要な世帯年収
- 2,000万円で住宅ローンを組むシミュレーション
- 住宅ローンの返済を早く終わらせるコツ
2,000万円の住宅ローンを組む際に必要な情報をまとめたので、ぜひ資金計画の際の参考にしてください。
年収・年齢別の目安や借入額別シミュレーションについてはこちらの記事で解説しています。
Contents
1.住宅ローン2,000万円を組むための世帯年収
初めに、2,000万円の住宅ローンを組むために必要な世帯年収を解説いたします。
2,000万円の住宅ローンを組むために必要な年収は、以下の通りです。
2,000万円の住宅ローンを組むために必要な年収は……
最低でも350万円、理想的には400万円から
※あくまでも目安です。実際には細かな基準による審査が設けられ、他に借入金がないかどうかなども関わってくるため、銀行にご相談ください。
一般的に、適正な借入金額は額面年収の5~6倍を目安にするとよいとされています。
この基準に照らし合わせると、以下の計算式が成り立ちます。
2,000万円÷5~6=約333万~400万円
世帯年収350万円の6倍で考える場合には、2,100万円程度を借り入れられることになります。
より詳しく適切な借入金額を知りたい場合は、返済負担率を確認しましょう。
返済負担率とは、年収のうち、年間返済額がどれだけの割合を占めているかを示す数値のことで、自分の年収に借り入れたい金額がふさわしいかどうかをチェックできます。
返済負担率は、以下の計算式によって求められます。
負担率の計算式
返済負担率=年間返済額 ÷ 額面年収×100
返済負担率は、25%程度におさめられると無理がなく、20%程度におさめられると余裕をもった理想値といわれています。
2,000万円を借り入れる場合の、年収ごとの返済負担率を比較してみましょう。
条件は以下の通りです。
金利……1.8%
返済方法……元利均等返済
返済期間……35年
月々の支払額6.5万円
※金利がずっと一定で変わらないとした場合で計算しています。なお、この計算で返済負担率が適正になったとしても、実際に金融機関で組んだ計算とは違う場合がございますので、あくまでも目安としてお使いください。
| 年収 | 350万円 | 400万円 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 負担率 | 22.3% | 19.5% | 15.6% |
※住宅金融支援機構「借入希望金額から返済額を計算」で算出
いずれも負担率が25%までに抑えられていますが、以下の点に注意してください。
1-1.世帯年収350万円の場合のポイント
返済負担率は22.3%におさまっています。
月々の手取りを23万円として考えると、ローン返済分の負担は3割を切るため、余裕を持った返済が可能でしょう。
しかし、住宅金融支援機構の調査によると、注文住宅を購入した人の平均世帯年収は623.7万円。(詳細はコラムで解説)
年収350万円はこれよりかなり下回っているため、返済負担率以外の項目で住宅ローン審査に引っかかる可能性があります。
1-2.世帯年収400万円の場合のポイント
年収400万円になると、返済負担率は理想値の20%を下回ります。
月の手取りが26万円だとすれば、同じ計算で25%が返済のために割かれる計算になります。
余裕を持って住宅ローン組むのであれば、400万円から検討するのが安全でしょう。
1-3.世帯年収500万円の場合のポイント
年収500万円で月の手取りが33万円程度の場合、19%程度の負担になるため、かなり余裕を持った返済計画を立てられます。
住宅ローンの返済が負担に感じることは、今の年収が大幅に落ちない限りあまり心配いらないでしょう。
年収がいくらであっても、まずは無料のHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスで、あなたが建てたい家の費用相場を確認し、現実的な予算を把握しておきましょう。
スマホやパソコンから簡単にあなたの予算に合ったハウスメーカー・工務店をピックアップできるうえ、実際の費用や住宅プランを確認しながら検討できるので、難しい資金計画がスムーズに立てられますよ。
現実的な資金計画を立てるために、ぜひご活用ください。

全国の住宅ローンを組んでいる人のデータ
住宅金融支援機構によると、全国の住宅ローンを組んでいる人に関するデータは以下の通りです。
| 世帯年収 | 623.7万円 |
|---|---|
| 年齢 | 46.2歳 |
| 借入額 | 2,967.2万円 |
| 建設費 | 3,715.2万円 |
年収は平均して600万円台、年代は40代になってから組む人が多いようです。借入金は2,967.2万円とあり、建設費の約8割をローンで借り入れている傾向があります。
ローンを組む期間は、おおむね30~35年が多いですが、40代から組み始めると完済時には70代になっています。
余裕を持つためには、30代で検討してもよいでしょう。返済期間を5年延ばせるだけで、毎月の負担は軽減されます(ただし、総支払額は増えてしまいます)。
平均よりも年齢が若く、今後給料が上がっていくことが明らかな場合には、返済期間を反対に短くすることで、総支払額を抑えることも出来ます。
参考:住宅金融支援機構「![]() 2022年度 フラット35利用者調査」
2022年度 フラット35利用者調査」
2.金利・返済方法の種類とシミュレーション
住宅ローンには金利があり、選ぶタイプによってパーセンテージが異なります。
また、返済方法にも種類があり、何を選ぶかによって月々の支払額や総支払額に差が出てくるので、ここでチェックしておきましょう。
2-1.金利の種類と特徴・選び方
金利には、大きく分けて以下3つの種類があります。
- 全期間固定金利
- 固定金利期間選択
- 変動金利
それぞれの特徴と、メリット・デメリットは以下の通りです。
| 全期間固定金利 | ||
|---|---|---|
| 特徴 |
|
|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
| 固定金利期間選択 | ||
| 特徴 |
|
|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
| 変動金利 | ||
| 特徴 |
|
|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
これらの情報を元に、選び方のポイントを解説すると、以下のようになります。
| 選び方のポイント | |
|---|---|
| 全期間固定金利 |
|
| 固定金利期間選択 |
|
| 変動金利 |
|
一般的な解釈では、
- 「金利の上昇下降に一喜一憂することなく、金額が一定で返済計画を立てやすい方を選びたい」という人が全期間固定金利
- 「家庭の出費が集中する時期は決まっているから、とりあえず固定にしておいてそのあとの出方を考えたい」という人が固定金利期間選択
- 「もし金利が上昇しても資金的にカバーできるだけの余裕があるから、低金利によって受けられる恩恵は受けておきたい」という人が変動金利
を選んでいる傾向にあります。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
2-2.金利のパーセンテージによる差額
金利0.4%・1.5%・2%では、総支払額・総利息額にどの程度の差が出るのかシミュレーションしてみます。
- 0.4%…変動金利の借入時に多い
- 1.5%…固定金利期間選択の10年固定や、かなり安い金利の35年固定金利などの借入時に設定されていることが多い
- 2%…35年固定金利に多い
返済期間……35年
返済方法……元利均等返済
※返済期間中、金利に全く変動がなかったものと仮定する
| 金利 | 0.4% | 1.5% | 2% |
|---|---|---|---|
| 月々の支払額 | 51,038円 | 61,236円 | 66,252円 |
| 総支払額 | 2,143万5,960円 | 2,571万9,120円 | 2,782万5,840円 |
| 総利息額 | 143万5,960円 | 571万9,120円 | 782万5,840円 |
このように、金利0.4%と2%では、総支払額・総利息額になんと約640万円も差が出ます。
各パーセンテージのポイントを見てみましょう。
変動金利に多い「金利0.4%」の場合
月々の支払額は51,038円で済みます。
仮に年収400万円で計算すると、返済負担率はわずか15%におさまり、月々の手取りに占める負担も2割程度になるため、やや余裕を持った返済計画が立てられるでしょう。
ただし、変動金利は5年ごとに価格改定が行われるため、0.4%の金利がいつまでも続くわけではないことに注意が必要です。
固定金利10年・安い35年に多い「金利1.5%」の場合
月々の支払額は61,236円です。
年収400万円で計算すると、返済負担率は18.4%となります。
固定金利35年に多い「金利2%」の場合
月々の支払額は66,252円で、年収400万円で計算した時の返済負担率は19.9%です。
▶あなたのこだわりが詰まった「家づくりの相場」をチェック(無料)
2-3.返済方法の種類と特徴・選び方
返済方法には、「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があります。
それぞれの特徴とメリット・デメリットは以下の通りです。
| 元利均等返済 | ||
|---|---|---|
| 特徴 |
|
|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
| 元金均等返済 | ||
| 特徴 |
|
|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
| 選び方のポイント | |
|---|---|
| 元利均等返済 |
|
| 元金均等返済 |
|
元利均等返済は、総返済額が高くなるものの、借入当初の返済額が元金均等返済に比べて少なく、毎月ずっと一定であることから返済計画が立てやすい特徴があります。
元金均等返済は、総返済額が元利均等返済に比べて低くなりますが、借入当初の返済額は高い傾向にあります。
審査の際に必要な年収も高くなるため、資金に余裕がないと選択は厳しいでしょう。
また、元金均等返済は取り扱っていない銀行も多く、そもそも選べないという可能性もあります。
2-2のシミュレーションを用い、元利均等返済と元金均等返済による支払額の差額を見てみましょう。
| 金利 | 0.4% | 1.5% | 2% |
|---|---|---|---|
| 月々の支払額 | 51,038円 | 61,236円 | 66,252円 |
| 総支払額 | 2,143万5,960円 | 2,571万9,120円 | 2,782万5,840円 |
| 金利 | 0.4% | 1.5% | 2% |
|---|---|---|---|
| 月々の支払額 | 54,285円 (+3,247円) |
72,618円 (+11,382円) |
80,952円 (+14,700円) |
| 総支払額 | 21,40万3,099円 (-32,861円) |
25,26万2,260円 (-456,860円) |
27,01万6,429円 (-809,411円) |
※( )は元利均等返済との差額
※総利息額の差は、総支払額の差に等しい
以上のように、金利や返済方法によって月々の支払いや総支払額には違いがあるため、金利の動向をチェックしながら自分たちのライフスタイルに合った資金計画を立てる必要があります。
無料のHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスなら、あなたの予算に合ったハウスメーカー・工務店が簡単に絞り込めるうえ、ハウスメーカー・工務店選びや補助金活用・資金計画で迷うことがあれば、コーディネーターや注文住宅のプロに無料で相談することができます。
3.住宅ローンの返済を早く終わらせるために出来る工夫
最後に、住宅ローンの返済を早く終わらせるために出来る工夫として、助成金・補助金や減税制度について紹介いたします。
住宅ローンの返済を早く終わらせるためには、国や自治体の助成や補助、減税制度を賢く使うことが大切です。
代表的なものでは、例えば以下のような類があります。
※すでに終了している制度もあります。随時新着情報を更新いたします。
| 概要 | 手続き期間 | |
|---|---|---|
| こどもエコすまい支援事業 | 子育て世帯・若者夫婦を対象として、高いZEHレベルの新築住宅の取得、既存住宅の省エネ改修をした場合、特定の条件を満たすことで1戸あたり100万円の補助がされる。 公式サイト:https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/ ※後継事業「子育てエコホーム支援事業」 |
2023年9月28日に受付終了 |
| ZEH支援事業 | 国が設けた基準を満たしたZEH住宅であって、更に対象基準を満たすことで、補助金額が交付・加算される。 出典: |
2024年1月9日に受付終了 |
| LCCM住宅整備推進事業 | 特定の補助要件を満たす、CO2排出量を削減した脱炭素化住宅(LCCM住宅)について、最大140万円/戸の支援がなされる 出典:国土交通省 LCCM住宅整備推進事業 概要 |
2023年9月19日に受付終了 |
| 地域型住宅グリーン化事業 | 国土交通省から採択を受けた、地域における中小工務店を中心とした木造住宅の関連事業者が連携を行ってグループを作り建てた、省エネルギー・耐久性能に優れた新築・中古の木造住宅に対して補助金が交付される制度 出典:地域型住宅グリーン化事業 |
2023年6月2日に受付終了 |
※2024(令和6)年の情報は公表され次第更新いたします。
また、以下のような減税制度もあります。
| 概要 | 主な要件 | |
|---|---|---|
| 住宅ローン減税 | 住宅ローンを利用した新築住宅の取得、もしくは増改築をしたときに特定の条件を満たすことで、各年末の住宅ローン残高から0.7%を最大13年間所得税額などから控除する制度。 出典: |
など |
2024年1月から「住宅ローン減税」の仕組みが以下のように変更されました。
借入限度額
子育て世帯・若者夫婦世帯※が2024(令和6)年に入居する場合、以下の水準を維持する。
認定住宅:5,000万円/ZEH水準省エネ住宅:4,500万円/省エネ基準適合住宅:4,000万円
※18歳以下の子どもがいる、 もしくは夫婦のいずれかが39歳以下の世帯
床面積要件緩和措置の期限
新築住宅の床面積要件を40平米以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分)の建築確認の期限を以下のとおり延長する。
2023(令和5)年12月31日 → 2024(令和6)年12月31日
新築住宅の条件
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準を満たす住宅であることを条件とする。
※借入限度額は省エネ性能に応じて異なる
※申請には「省エネ基準以上適合の証明書」が必要
参考:国土交通省「住宅ローン減税」
また、以下のような住宅そのものの購入の他にかかる減税制度もあります。
- 登録免許税の税率軽減
- 不動産取得税の軽減
- 固定資産税の軽減
- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
その他にも、自治体による補助金や助成金、家を新築した際の優遇制度もあります。
情報は随時更新されているため、注文住宅のプロに相談しながら情報を整理してみてくださいね。



まとめ
2,000万円の住宅ローンを組む際に、押さえておきたい情報をお伝えしました。
住宅ローンを組む際には、これらをしっかり理解し、後悔のない組み方を選択しましょう。
それではおさらいです。
この記事のポイント
住宅ローンを借りる人の平均的な数値は以下の通りです。
- 年収:600万円台
- 年代:40代
- 借入金: 2,967.2万円
このことから、40歳で2,000万円の住宅ローンを借り入れることは平均よりも返済の負担が軽いことがわかります。
詳細はコラムで解説しています。
例えば、以下のような条件の場合は、月々の支払額は65,000円となります。
- 金利……1.8%
- 返済方法……元利均等返済
- 返済期間……35年
「1.住宅ローン2,000万円を組むための世帯年収」で詳細をご確認ください。
最低でも350万円、理想的には400万円からです。
詳細は「1.住宅ローン2,000万円を組むための世帯年収」で解説しています。
住宅ローンの組み方まとめ