
住宅ローンを考える際、連帯債務の仕組みや、メリット、デメリットについて分からない方も多いのではないしょうか。また、連帯保証やペアローンとの違いも気になるところです。
この記事では、連帯債務のメリットやデメリット、他のローン形態との違い、住宅ローンの借り方を決める基準まで詳しく解説します。
住み替えに伴い売却を行う方は『不動産売却の基本』『ローン中の家を売る方法』も併せてご覧ください。
- 「不動産を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格
- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
Contents
1.住宅ローンの連帯債務とは?
連帯債務とは、複数の人が同じ債務に対して全額の返済義務を負う仕組みです。
住宅ローンにおいては、夫婦や家族が共同で借り入れる際に利用され、2人のうち1人が主債務者となり、もう1人が連帯債務者となります。
以下では、連帯債務の理解に重要な収入合算と、連帯債務者にできる人について解説します。
1-1.収入合算ができる一本の住宅ローン
連帯債務で住宅ローンを組むと、連帯債務者となる夫婦や家族の収入を合算して、融資の審査を受けられます。
そのため、単独では借りられないような高額なローンを借りることができるのが大きなメリットです。
例えば、夫婦それぞれが500万円と300万円の年収がある場合、合計年収800万円が融資額を決める基準となります。
連帯債務の住宅ローンは、あくまで一本の住宅ローンであり、「一つのローンを二人で協力して返済していく」方法です。
連帯債務と混同されやすいペアローンは、それぞれ別のローンを契約して、「それぞれが別のローンを返済していく」方法になります。
詳しくは、「4.連帯債務・連帯保証・ペアローンの違い 」で詳しく解説します。

1-2.連帯債務者にできる人
連帯債務者として収入を合算できる人には、以下のような要件があります。
- 申込者本人の親・子ども・配偶者などであること
- 申込時の年齢が70歳未満であること
- 申込者本人と同居していること
住宅ローンでは、上記の要件を満たす方のうち1名のみを連帯債務者に指定することが可能です。
そして、連帯債務者として指定された方の収入を合算できます。
例えば、住宅金融支援機構の「フラット35」という商品では、合算者の年収全額までが合算可能です。
しかし、「合算者の年収の50%を超える場合は、借入期間が短くなる」といった借入期間の条件があります。
細かい条件等は金融機関により異なるため、事前に確認をしておきましょう。
2. 連帯債務で住宅ローンを組むメリット
連帯債務で住宅ローンを組むことには、収入合算による高額ローンの取得や、税制上のメリットなど、住宅購入を検討している際に非常に有利な要素が多く存在します。
ここでは、以下3つの連帯債務のメリットを解説します。
2-1. 収入合算で高額なローンも通りやすい
連帯債務型の住宅ローンでは、収入を合算して審査に望むことができます。
例えば、夫婦それぞれが500万円と300万円の年収があった場合、合計年収800万円が審査の基準となり、より高額な融資を受けやすくなります。
また、単独では希望通り融資を受けられるか不安な場合では、収入合算にすることで審査を通りやすくできます。
2-2. 連帯債務者も住宅ローン控除を受けられる
連帯債務のもうひとつの大きな利点は、連帯債務者も住宅ローン控除の対象となることです。
住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高に対して税金の控除を受けられる制度ですが、連帯債務者もその控除を利用できるため、税金の負担を軽減できるというメリットがあります。
2-3. ペアローンより諸費用が少ない
4章で紹介するペアローンは、夫婦がそれぞれ別々のローンを組むことで、より多くの融資が受けられる仕組みです。
ペアローンは2本のローンを組むため、住宅ローン契約にかかる諸費用が2倍になります。
夫婦二人の収入で多くの融資が受けられるという点は、連帯債務での収入合算と同様です。
連帯債務型住宅ローンなら、契約にかかる諸費用は1本分です。
3. 連帯債務で住宅ローンを組むデメリット
連帯債務にはもちろんデメリットも存在します。収入減少リスクや、団体信用生命保険に関する制約など、慎重に考慮しなければならないポイントがいくつかあります。
これらのデメリットを理解し、対策を講じることが重要です。
3-1.債務者それぞれが返済する必要がある
連帯債務では、主債務者と連帯債務者のそれぞれが、借入金負担に応じた返済を行うのが基本です。
例えば、主債務者2,000万円、連帯債務者が1,000万円の負担で合計3,000万円を借り入れた場合、自身の負担分をそれぞれ返済します。
もし、連帯債務者が2,000万円を返済した場合、主債務者に対して1,000万円の贈与をしたことになります。
贈与とみなされれば、贈与が発生するため注意が必要です。
ただし、贈与額は暦年で計算され、基礎控除額の110万円以下である場合は、贈与税はかかりません。
上記の1,000万円の贈与の例は、ローン完済時の最終的な数字であり、実際には毎年110万円以下の贈与に留まるケースがほとんどです。
3-2. 主債務者しか団体信用生命保険に加入できない
住宅ローンは融資額が大きいため、債務者が死亡した場合に残った債務を保証する「団体信用生命保険(団信)」に加入することがほぼ前提となります。
ただ連帯債務の場合、団信に入れるのは主債務者だけが一般的であるため、連帯債務者死亡時の負担が大きくなりやすいのです
「連生団信(連生団体信用生命保険付住宅ローン)」というプランでは、連帯債務者も団信に加入できますが、通常の団信に比べて保険料が高くなります。
4.連帯債務・連帯保証・ペアローンの違い
よく混同されやすい、住宅ローンの3つの借り方『連帯債務型・連帯保証型・ペアローン』について違いを解説します。

1章で解説したように連帯債務では、一つの住宅ローンに対し、複数人の債務者(主債務者と連帯債務者)を設定します。
収入合算ができて、お互いが協力して住宅ローンを返済していくイメージです。

連帯保証では、住宅ローンの返済を債務者とともに保証する、連帯保証人を設定します。
連帯保証人は、あくまで債務者の返済が滞った場合に残債を保証する立場であり、連帯債務のように「お互い協力して返済していく」立場とは異なります。
連帯保証でも収入合算は可能です。
連帯債務との大きな違いとしては、連帯保証はあくまで単独での購入になるため、不動産の所有権も単独になるのが一般的です。
夫婦で連帯債務を利用した場合は、「2人で購入した不動産」になるため、所有権を分け合っている状態になります。

ペアローンでは、夫婦がそれぞれ別々の住宅ローンを組み、互いを相手のローンの連帯保証人として設定します。
両者が独立したローンを組むため、それぞれ団信に加入でき、住宅ローン控除も適用されます。
連帯債務の収入合算とは異なりますが、両者が個別に融資をうけるため、借入額は高くなります。
一方で、二つの住宅ローンを組むため、契約にかかる費用が二重に発生します。
3つを比較して、それぞれの収入状況や将来の計画に応じて最適な住宅ローンを選びましょう。
以下の表は、連帯債務、連帯保証、ペアローンの特徴をまとめた比較表です。
| 項目 | 連帯債務 | 連帯保証 | ペアローン |
|---|---|---|---|
| 債務の負担 | 各自が全額を負担 | 連帯保証人は補助的に負担 | 各自が独立したローンを負担 |
| 収入の合算 | 可能 | 可能(【フラット35】では連帯保証型の選択不可) | 不可(各自の収入を根拠に別のローンを借りるため融資額は大きい) |
| 団信の加入 | 主債務者のみが一般的 | 主債務者のみ | 各自で加入可能 |
| 住宅ローン控除の適用 | 持分に応じて各自適用可能 | 主債務者のみ適用可能 | 各自で適用可能 |
| 費用 | 1契約分で済む | 1契約分で済む | 契約分の費用が発生 |
5.住宅ローンの借り方を決める基準
住宅ローンを選ぶ際には、収入状況や将来のライフプランに合った方法を選ぶことが重要です。
単独契約、連帯債務、ペアローンなどの選択肢がありますが、それぞれの特徴とリスクを理解した上で、自分たちに最適な方法を選びましょう。
この章では、住宅ローンの借り方をきめるための、以下3つの基準を解説します。
5-1.基本は単独契約でリスクを回避
住宅ローンを組む際、リスクを最小限に抑えるためには、まず単独契約を検討するのが良いでしょう。
住宅ローンでは、収入合算をする必要がない場合には、連帯保証人の設定なく、単独での契約が可能です。
単独契約では、一人の収入を基にローンを組むため、家計全体で見た借り入れの負担額は小さくなりやすく、収入減少への考慮も一人分で済みます。
万が一債務者が死亡した場合でも、団信により残債はゼロになります。
単独契約はリスクを管理しやすく、将来の不安を軽減する選択肢と言えるでしょう。
5-2.共働きで収入差が大きいなら連帯債務や連帯保証で収入合算
共働きで収入差が大きい場合には、連帯債務や連帯保証を利用して収入を合算する方法がおすすめです。
収入を合算することで、少ない収入を持つパートナーの負担を軽減しながら、ローンの借入額を増やすことが可能です。
例えば、夫が主要な収入源であり、妻の収入が比較的少ない場合、収入合算を活用することで希望する住宅を購入できる可能性が高まります。。
収入差がある夫婦でも、収入合算を活用すれば、負担を分散しながらローンを組むことができるのです。
また、収入差が大きい場合には、借入額が過度に増えるリスクも少なく、無理のない返済計画が立てられるため、安心して住宅購入に踏み切ることができるでしょう。
5-3.共働きでどちらも収入が多い場合はペアローン
夫婦ともに収入が多く安定している場合、ペアローンを選ぶのが効果的です。
収入が大きい夫婦であれば、自然と借り入れ額も大きくなりやすく、収入が途絶えた際のリスクも増します。
しかしペアローンを利用すれば、夫婦それぞれが独立したローンを組み、両方が団体信用生命保険(団信)に加入できます。
万が一の事態が発生した場合でも、残された家族の負担を軽減できるため、リスクを抑える効果があります。
さらに、ペアローンでは夫婦双方が住宅ローン控除を受けられるため、節税効果も期待できます。
収入が高い夫婦にとって、ペアローンはリスク軽減と節税の両面で有利な選択肢と言えます。
まとめ
連帯債務型住宅ローンは、夫婦や家族が収入を合算して高額な家を購入するためにはおすすめの選択肢です。その一方で、お互いが全額の返済責任を負う点はリスクとも言えます、
連帯債務とペアローン、連帯保証の違いを理解することで、最適な借り方を選ぶことが可能です。それぞれの特徴を把握し、将来の収入やライフプランを考慮しながら慎重に判断することが重要になります。
住宅ローンの選び方は、家族の将来を左右する大きな決断です。最適なローンを選び、家族が安心できる生活を実現させましょう。
- 「マンションを売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格
- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます





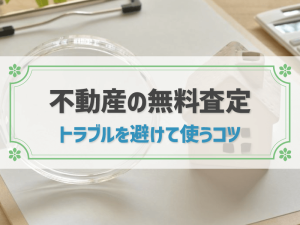
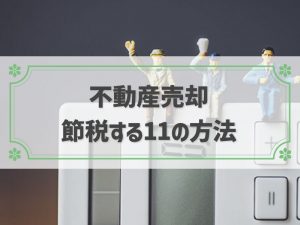


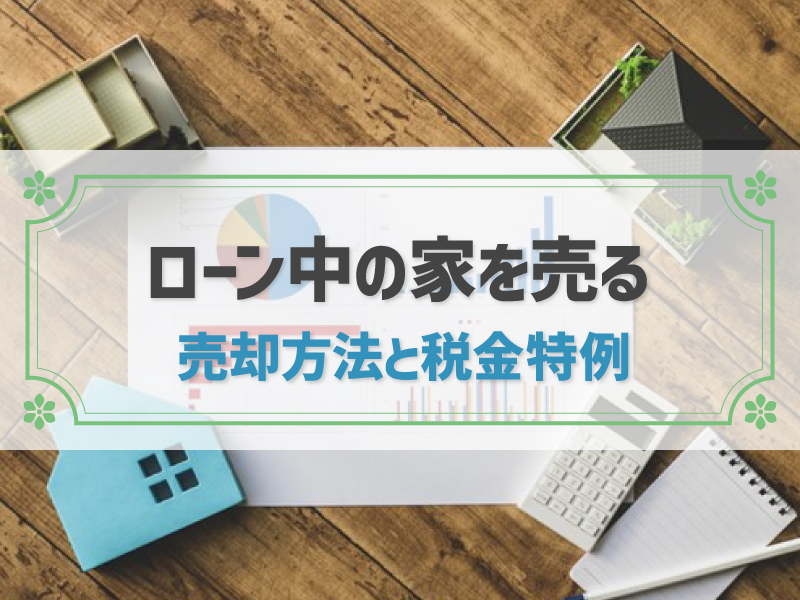




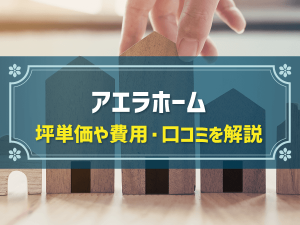
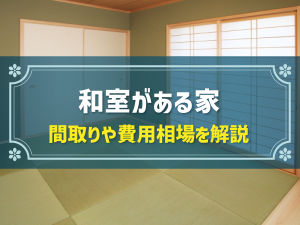


![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)
![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)