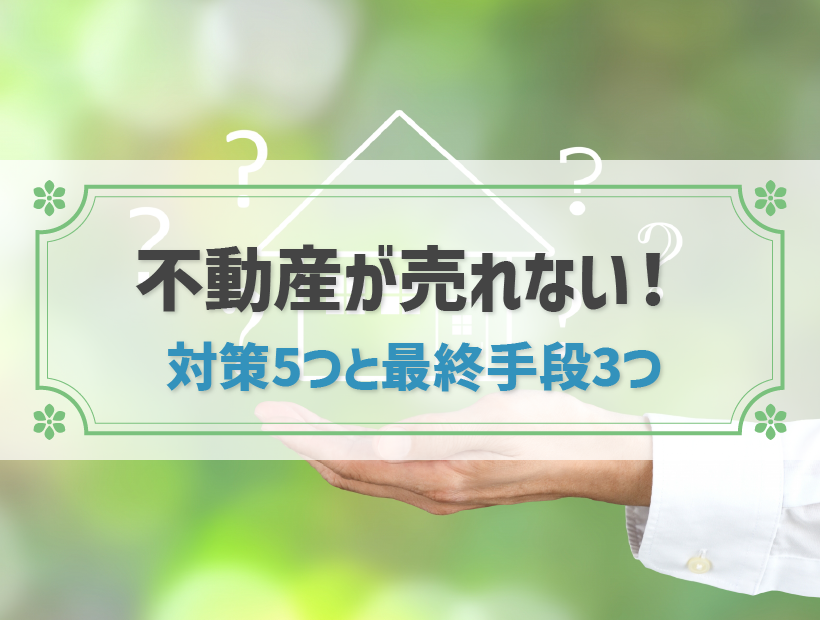
不動産を売却しようとしても、思うように売れず「このまま売れ残るのではないか」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
家が売れないのは、相場よりも価格を高く設定しているなど、いくつかの原因があります。ただし対策をしても、不動産売却の流れにのれず、なかなか売れないケースもあります。本記事ではそうした場合の最終的な解決策も解説しています。ぜひ最後までお読みください。
不動産・マンションの売却について基礎から詳しく知りたい方は『不動産売却の基本』、『マンション売却の基本』も併せてご覧ください。
Contents
1.現状から考える不動産が売れない原因
不動産がなかなか売れない原因は様々あります。
この章では、現状に照らし合わせて、どんな原因で売れないのかを考えていきましょう。
「売れない」と感じている今の状況は、大きく分けると、以下の2パターンに分けられます。
- 内覧予約が入らない・少ない
- 内覧まで進が購入まで至らない
1-1.内覧予約が入らない・少ない
平均的に、売り出しから3~6カ月程度で売却できます。
この間、複数組みの内覧を経て、購入へと至るのが一般的です。
一戸建ての場合は、マンションに比べて売却にかかる時間が長い傾向にありますが、3カ月間全く内覧予約がない場合は、警戒すべき自体です。
内覧予約が入らない・あるいは少ない場合は、以下のような原因が考えられます。
- 売り出し価格が相場より高すぎる
- 広告が魅力的ではない
- 不動産会社が囲いこみをしている
売り出し価格が高すぎると、内覧まで至らない確率が高くなります。
購入希望者は、WEB上で多くの物件を閲覧しているため、相場感が養われており、割高物件に反応しにくくなります。
広告の魅力がかけている場合は、割安感の物件でないと内覧されにくいでしょう。
囲いこみが行われると、購入希望者が集まりにくくなります。
囲いこみとは、仲介を担う不動産会社が、他社に買手を紹介されない様に、売却の情報を囲いこむ行為です。
1-2.内覧まで進むが購入に至らない
問題なく内覧までは実施されるも、なかなか購入に至らないケースも少なくありません。
そうした場合は、以下のような原因が考えられます。
- 広告写真よりも、実物の方が見劣りする
- 内覧当時の対応が悪い(売主あるいは不動産会社担当者)
内覧まで進むということは、相場よりも割高な物件だとしても、いくらかの魅力を感じていると考えられます。
それにも関わらず、購入に至らないのは、購入希望者が前もって抱いていた印象を、内覧で超えることができなかった可能性があります。
広告写真よりも、実物の方が見劣りするような物件は、購入されにくいでしょう。
また、内覧当日の対応も重要です。
不動産会社の担当者はもちろん、売主の対応が悪いケースもあるため注意が必要です。
【対策1】相場を調べて適正価格か確認する
不動産会社に頼るだけでなく、自分で相場を調べて、適正価格か確認することが大切です。
自分で相場を調べる方法として、「土地総合情報システム」と「レインズマーケット・インフォメーション」があります。
| 自分で相場を調べる方法 | 概要 |
|---|---|
| 土地総合情報システム | 国土交通省が運営しており、不動産売買に関する情報をデータ化しているWebサイト。 |
| レインズマーケット・インフォメーション | 国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営・管理しており、直近1年間に売買された価格情報が調べられるWebサイト。 |
土地総合情報システムは、戸建やマンションの他に、土地や農地などの価格も調べられます。
レインズマーケット・インフォメーションは、戸建とマンションの価格情報を検索でき、データ量が豊富で、更新頻度が高いことが特徴です。
2つとも、誰でも無料で利用できるサービスで、不動産の売却相場や過去の成約事例などを確認できます。
ただし、詳細な住所や物件名までは調べられないので、目安として参考にしましょう。
【対策2】広告内容や不動産会社の活動状況を見直す
なかなか売れない場合は、広告内容や不動産会社の活動状況を見直しましょう。売れない原因を見直すことで、より買い手に効果的なサービスを提供できます。
見直すポイントは、以下のとおりです。
- 積極的に広告活動を行っているか
- 魅力的な写真が使われているか
チラシやインターネット広告に、積極的に掲載しているか確認しましょう。
掲載されていたら、間取りや部屋の広さなどの基本情報だけでなく、商業施設が近い、日当たりがよいなどのアピールポイントなども掲載されているかチェックしましょう。売却の可能性が上がります。
また、不動産の写真が魅力的に掲載されているかも重要です。
家の外観や周辺環境の写真、部屋や設備の写真が魅力的でなければ、買い手の購買意欲が下がります。そのため、撮り直したり差し替えたりするように、不動産会社に提案するのも効果的です。
注意点として、広告費が別途かかる場合もあるので、不動産会社と相談しながら活動状況を見直しましょう。
【対策3】水回りを掃除し当日は丁寧な対応を
内覧前に水回りを掃除し、当日は丁寧な対応を心がけましょう。
特に、水回りの清掃は重要です。いくら部屋が綺麗でも、水回りが汚れていると、手入れを怠っている印象を与え、不動産全体の魅力が低下します。
もし、自分で掃除するのが難しい場合は、ハウスクリーニングを依頼するのもおすすめです。
また、買い手は信頼できる売り手から購入したいと考えています。内覧時は、質問や疑問点に的確に回答し、ゆっくりと家を見て回れるように配慮しましょう。
事前に、内覧の際にどのような流れで案内するのか、不動産会社と相談しておくとスムーズに進みます。
【対策4】売り出し時期や売却スケジュールを見直す
売り出し時期や売却スケジュールを見直すことも重要です。
不動産の購入需要が高まる時期は、新学期シーズンの2月〜3月頃が最も多いです。次いで、9月〜11月頃も転勤シーズンなので、購入需要が高い傾向にあります。
一方で、不動産売却の取引が少ないのは8月頃です。8月頃は気温が高く、天候が不安定なこともあり、買い手の活動意欲が下がります。
多くの購入希望者を集めて、スムーズな売却を成功させるためにも、売却の時期やスケジュールを適切なタイミングに設定しましょう。
【対策5】不動産会社の見直しを検討する
不動産会社の見直しを検討して、信頼できる担当者を見つけることが大切です。
不動産会社を変更することで、新たな戦略を立ててくれて、より効果的なアプローチをしてくれる不動産会社を見つけられる可能性があります。
見直す際は、売却する物件が不動産会社の得意分野と一致しているか確認しましょう。
マンションや戸建て、土地など、不動産会社ごとに得意とする分野は違います。得意とする不動産であれば、実績や経験があるため、買い手に適切に広告活動などのアプローチができます。
不動産会社を見直すなら、不動産一括査定サイト「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」を活用して査定を依頼しましょう。
国内初の不動産の一括査定サービス「不動産売却 HOME4U」は20年の実績を元にした審査基準をもとに、最適な不動産会社を提案します。
査定を依頼する会社は厳選された優良企業2,100社の中からお客様の条件にあった会社を「不動産売却 HOME4U」がピックアップし、その中から最大6社まで選択することができます。
査定を依頼する会社を探すなら、「不動産売却 HOME4U」をぜひご活用ください。
2.対処をしても不動産が売れない場合にすべき3つのこと

対処しても不動産が売れない場合にすべき3つのことは、以下のとおりです。
- 最低限のリフォームを行う
- 築年数が古い戸建ての場合は更地にしてから売る
- 不動産買取を依頼する
売れない理由を分析して、適切な方法を選びましょう。
2-1.最低限のリフォームを行う
最低限のリフォームを行なって、内覧時の印象を良くすることも検討しましょう。
特に古い物件の場合は、水回り設備や壁、ふすまなど、汚れや破損している箇所が多くなります。ペットも住んでいた物件であると、壁の劣化などはさらに大きいでしょう。そういった物件では、修繕することで買い手の購買意欲を高められます。
リーズナブルな価格な上に、設備が整っている物件として売却できるメリットがあります。
ただし注意点として、買い手によってリフォームするかどうか見極める必要があります。自分好みにリノベーションをしたい層にはリフォームしていない安い物件が好まれますし、逆にリフォーム済みの手間のかからない物件が喜ばれるケースもあります。
リフォームは、自分の意思だけでは決めず不動産会社とよく相談して判断しましょう。
2-2.築年数が古い戸建ての場合は更地にしてから売る
築年数が古い戸建ての場合は、更地にしてから売る方が良い場合もあります。
物件を購入したい買い手にではなく、土地を購入したい買い手に訴求することで、早く売却できるだけでなく、高値での売却に期待できます。
更地にしてからの売却は、買い手が解体にかかる費用や手間を負担することなく、すぐに新居を建てられるので需要が高いです。
ただし、更地にすると翌年の固定資産税が通常の4倍〜6倍程度高くなるので、解体するタイミングは不動産会社と相談するのがおすすめです。
2-3.不動産買取を依頼する
さまざまな対処をしても売却が困難であれば、不動産買取の依頼を検討しましょう。
不動産買取とは、一般の買主を探す「仲介」とは違い、不動産会社が直接物件を買い取ってくれる方法のことです。仲介手数料がかからず、短期間での売却に期待できます。
ただし注意点として、通常の仲介と比べて、売却額が相場の7割程度の価格で取引される可能性があります。
そのため、思い通りに売却が進んでおらず、長期化が予想されるのであれば、不動産買取の依頼を検討するのもおすすめです。
不動産買取の依頼は「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」が便利です。無料査定依頼の際、入力フォームの要望欄に「買取希望」とご記入ください。ご希望に沿った不動産会社がきっと見つかります。買取で売却を検討されている方はぜひご活用ください。
まとめ
不動産が売れないとお悩みの方は少なくありません。
家や土地が売れない場合、「売り出し価格を高く設定し過ぎている」「不動産の購入需要が低い時期に売り出している」「不動産会社の担当者と相性が悪い」など、主に5つの原因が考えられます。
不動産が売れない場合の5つの対処法は、以下のとおりです。
- 相場を調 べて適正価格か確認する
- 広告内容や不動産会社の活動状況を見直す
- 水回りを掃除し当日は丁寧な対応を
- 売り出し時期や売却スケジュールを見直す
- 不動産会社の見直しを検討する
ただし、対処をしても不動産が売れないケースもあります。その場合は「最低限のリフォーム」や「解体工事で更地にする」などを検討しましょう。
また不動産買取を行っている不動産会社に相談することもおすすめです。ただし不動産買取を行っている不動産会社は限られています。「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」を活用して、信頼できる不動産会社を探しましょう。



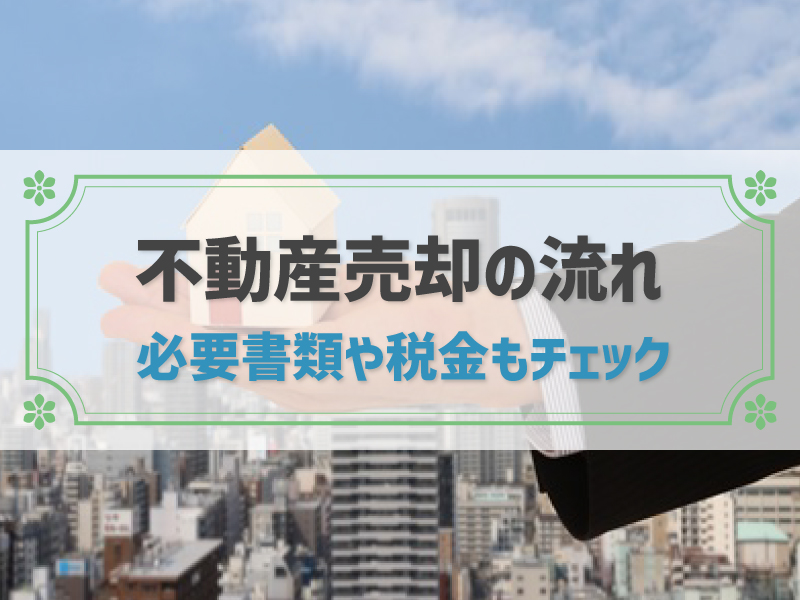







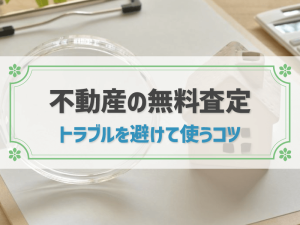
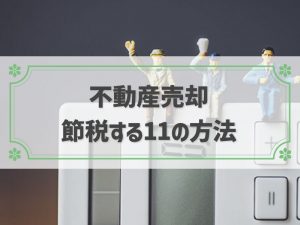




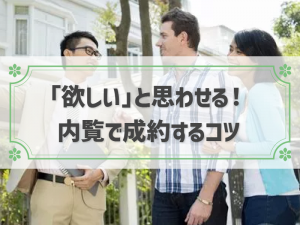

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)
![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)