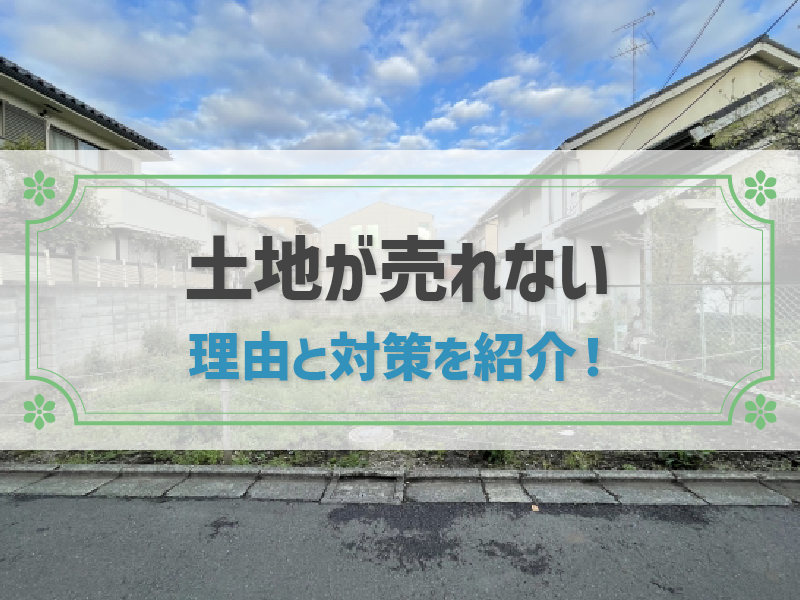
土地を保有していると、維持費や税金がかかり続けます。
売りに出したものの、なかなか売れないとお困りの方も多いのではないでしょうか。
土地が売れないときには、その理由に応じた対策が必要です。
この記事では、土地が売れない理由を明確にし、速やかに売るための対策方法をお伝えします。
この記事を読めば、適切な対策を取って土地を売却、もしくは手放すことができるようになります。
土地の売却について基礎から詳しく知りたい方は『土地売却の流れ』も併せてご覧ください。
Contents
1.土地が売れない原因とは?

土地の売却活動にかかる期間は、一般的には3ヵ月といわれています。
3ヵ月たっても売れない土地は、何らかの売れない原因があると考えて良いでしょう。
土地が売れない原因は、大きく以下の3つに分けることができます。
- 売り方に問題がある
- 土地自体に問題がある
- 不動産会社に問題がある
売却を成功させるため、土地が売れない原因を詳しく見ていきましょう。
1-1.売り方に問題がある
土地が売れないときは、売り方に問題がある可能性があります。
以下4つに該当していないか確認していきましょう。
- 売り出し価格が高すぎる
- あまり需要がないタイミングで売っている
- 広告の出し方に問題がある
- 古家付き土地として売っている
それぞれ詳しく見ていきます。
1-1-1.売り出し価格が高すぎる
売り出し価格が相場より大幅に高いと売れにくくなります。
売り出し価格は、相場より少し高く設定するケースが一般的です。
しかし、あまりにも相場とかけ離れた高値だと、そもそも買い手の検討対象にならないことも多いのです。
なかなか売れないときは、売り出し価格が相場に即しているか確認してみましょう。
1-1-2.あまり需要がないタイミングで売っている
土地を含め、不動産の売却には、適した時期とそうでない時期があります。
一般的に、転勤や進学のシーズンで不動産を探す人が多い2~4月は、不動産取引が活発です。
また、人事異動の影響で9月~11月にかけても需要が増加します。
一方、8月は不動産会社の閑散期といわれており、需要自体が低下するので、売却は難しいでしょう。
土地の内覧も暑い気候なので避けられる傾向があります。
1-1-3.広告の出し方に問題がある
広告の写真や図面で、物件の魅力が伝えきれていない場合も、土地は売れにくくなります。
また、ターゲット層に合っていないアピールをしている場合にも、売却の難易度が上がります。
たとえば、ファミリー層が少ない地域なのに、土地の広さをアピールしているケースです。
単身者や定年退職後に夫婦で居住するなら、土地が広いことは魅力的なアピールポイントになりません。
土地が売れないときは、物件の魅力をターゲット層に合わせたアピールができているかを確認してみましょう。
1-1-4.古家付き土地として売っている
築年数の古い家が建っている土地は敬遠されやすい傾向にあります。
そのような土地は、購入者が費用を負担して建物を取り壊す必要があるからです。
例えば、30~40坪の土地に古家が建っている場合、取り壊すには150万円ほどの解体費用が必要になります。
古家付きの場合は更地にして売るのも選択肢のひとつです。
1-2.土地自体に問題がある

売り出し方に問題がないのに土地が売れない場合、その土地自体に問題がある可能性が考えられます。
以下の点に該当しないか確認してみましょう。
【売れにくい土地の特徴】
- 不整形地である
- 敷地面積が広大・または狭小
- 前面道路が私道である
- 前面道路が狭い
- 崖の近くにある
- 災害危険区域内にある
- 市街化調整区域にある
- 人気のないエリアにある
- 境界が明確でない
- 土壌汚染・埋設物などの懸念がある
それぞれの特徴について、詳しく紹介します。
1-2-1.不整形地である
旗竿地や三角型、L字型、傾斜地などの「不整形地」は活用方法が限られるため売りにくくなります。
特に接道義務が問題になり、希望する建物が建てられないことも少なくありません。
接道義務とは、「道路に2メートル以上接している土地でないと建物を建てられない」という建築基準法上の決まりのことです。
また、土地の評価も下がるため、金融機関からの融資が難しいことも売れない要因になります。
1-2-2.敷地面積が広大・または狭小
土地の敷地面積が広過ぎる場合は購入費用が高くなるため、敬遠されることがあります。
また、狭すぎる場合には建てられる建物が限られます。
いずれの場合も土地の活用が難しいため、買い手が付きにくくなります。
1-2-3.前面道路が私道である
前面道路が私道の場合も買い手に敬遠されがちです。
私道の持分がある土地の場合、持ち主がその管理を行わなければなりませんし、周辺の持ち主との交渉なども必要になります。
ほかの人が所有する私道の場合、通行のトラブルが生じる可能性もあるので、購入が敬遠されることが多いのです。
1-2-4.前面道路が狭い
前面道路の幅員が狭い場合も、需要が少なくなります。
幅員が4メートルの場合、建築基準法は満たせますが、駐車や車種によってすれ違いが困難になるなどのデメリットが生じます。
また、前面道路の幅員が道幅1.8メートル以上4メートル未満のみなし道路(2項道路)の場合には、セットバックの義務があります。
セットバックとは、道路に面した建物を境界線から2メートル後退させることです。
建築や土地の自由な使用が制限されるため、買い手に選ばれにくくなります。
1-2-5.崖の近くにある
崖の近くにある土地は、自然災害などで崖が崩れるおそれがあるため、自治体ごとのがけ条例によって建築が制限されます。
がけ崩れから建物を守るため、擁壁を設けるか建物の距離を離さなければなりません。
また、建築にあたり、耐震補強のため地盤改良や造成など特殊な工事が必要となります。
平地に建てるよりはるかに高額の費用がかかるため、崖の付近の土地は敬遠されがちです。
1-2-6.災害危険区域内にある
災害危険区域とは、建築基準法によって津波や高潮、出水(洪水)などの危険が著しく高いとされた区域です。
区域内の土地は、必要性があれば住居の建築や構造が制限されます。
そもそも災害リスクが高ければ買い手も付きづらくなります。
土地が災害危険区域に該当するかどうかは、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」で確認が可能です。
1-2-7.市街化調整区域にある
市街化調整区域とは、都市計画法により自治体ごとに定められた市街化を抑制する地域で、山林や農地などとして活用されています。
原則、住宅や商業施設などの建物建築が認められておらず、新築や建て替え、増改築などの際には自治体の許可が必要です。
建ぺい率・容積率などが制限されるため、市街化調整区域には買い手が思ったような建物を建てられません。そのため、売れにくくなります。
土地が市街化調整区域に該当するかどうかは、自治体が公表する都市計画図から確認が可能です。
1-2-8.人気のないエリアである
土地が人気のないエリアにある場合には、そもそも土地を探している人が少なく、人目に触れる機会が少ないため、売却の機会が限られます。
エリアの人気・不人気は、地価からある程度判断できます。
地価は国土交通省が運営する「土地総合情報システム」で確認が可能です。
土地総合情報システムでは、公示価格や地価調査のデータから、地価の動向を調べられます。
また、不動産情報ポータルサイトに掲載されている人気ランキングなども、土地の需要がどの程度あるかの参考になるでしょう。
1-2-9.境界が明確でない
土地の境界が明確でない場合、隣地の所有者と境界をめぐってトラブルになる可能性があるので、買い手が付きにくくなります。
境界を明確にするには、登記事項証明書や地図、地積測量図などから確認可能です。
しかし、地積測量図はすべての土地について備え付けられているわけではありません。
地積測量図がない場合には、測量士や土地家屋調査士に依頼する必要があります。
土地家屋調査士であれば、登記までまとめて依頼可能です。
1-2-10.土壌汚染・埋設物などの懸念がある
土壌汚染や埋設物の懸念がある場合も、買い手がつきにくくなります。
土壌汚染が認められる土壌汚染対策法上の要措置区域や形質変更時要届出区域に指定されている場合や、工場跡地など、過去に汚染が考えられる地歴がある場合は敬遠されるでしょう。
埋設物がある場合も、建築の支障が出る可能性があるので、売却が難しくなります。
1-3.不動産会社に問題がある
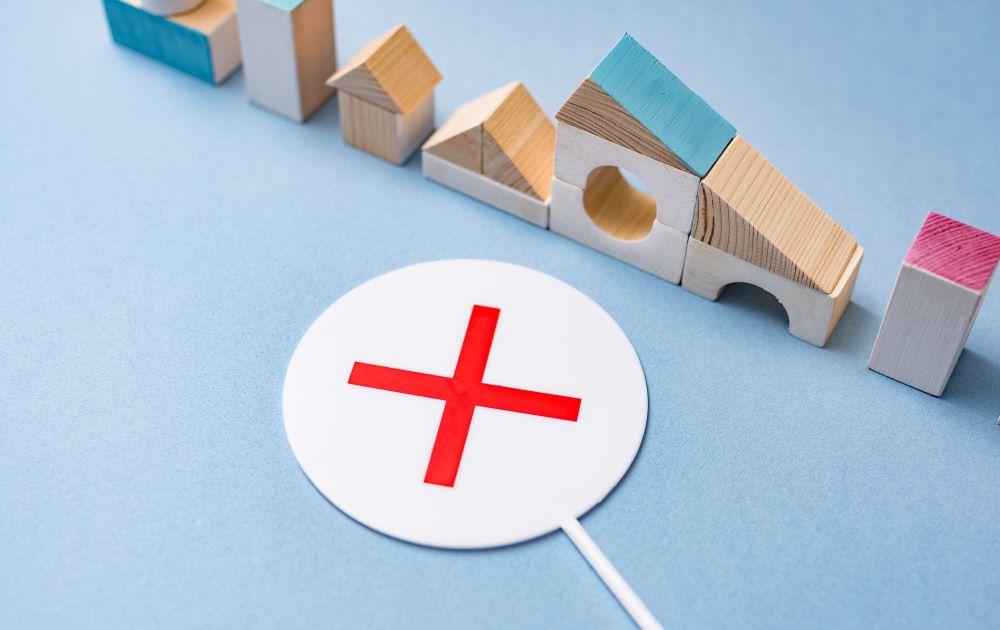
売り方や土地に問題がないにも関わらず、なかなか買い手が現れないこともあります。
その場合、不動産会社の売却活動が不十分であるなど、不動産会社に問題があることも少なくありません。
どのような場合に売れにくくなるのか、事例をご紹介します。
1-3-1.不動産会社が囲い込みをおこなっている
不動産会社の「囲い込み」とは、売り手から仲介依頼を受けた際に、他社に紹介せず自社のみで買い手を探そうとする行為です。
囲い込みが起こる要因は、仲介手数料にあります。
不動産会社は、売り手から仲介手数料を貰い売却活動を進めますが、買い手を自社で見つけた場合、さらに買い手からも仲介手数料を得ることができるのです。
このような双方から仲介手数料を得る「両手仲介」を狙って囲い込みを行う不動産会社も存在します。
仲介依頼先の不動産会社が囲い込みを行っているかどうかは、依頼先とは別の不動産会社に自身の物件について問い合わせを行ってみるとわかります。
商談中などと現在の状態と異なる場合には、囲い込みされているでしょう。
1-3-2.不動産会社がエリアにあまり詳しくない
不動産会社には、得意不得意があります。
依頼先の不動産会社が土地の売却に詳しくない場合や、エリアに詳しくない場合には、土地の需要をよく理解できず、ターゲット設定や売り出し方を誤ってしまうことがあります。
そのため、買い手の目に情報が届かず、いつまでも売れないという事態に陥ってしまうのです。
1-3-3.適切な媒介契約を選んでいない
不動産会社へ仲介を依頼する際の媒介契約方法には、「一般媒介」、「専任媒介」、「専任専属媒介」の3種類があります。
土地の売買では、需要がどの程度あるかによって媒介契約の種類を見極める必要があるのです。
媒介契約別の特徴を以下にまとめました。
| 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
|---|---|---|---|
| 複数の不動産会社への依頼 | 〇 | × | × |
| 自己発見取引 (自分が見つけてきた買い手との取引) |
〇 | 〇 | × |
| レインズへの登録 | 任意 | 契約後7日以内 | 契約後5日以内 |
| 売却活動の報告義務 | なし | 2週に1回以上 | 1週に1回以上 |
需要の高い土地は「一般媒介」で売ると早く売れる傾向にあります。
しかし需要が限られている土地の場合には、営業活動を積極的に行ってもらえる「専任媒介」や「専属専任媒介」のほうがスムーズに売却できるでしょう。
2.売れない土地を売却するための対策

土地が売れない場合、そのまま売却活動を続けていても買い手が現れることは期待できません。
そこで売れない土地を売るために有効な対策を7つ紹介します。
以下を順番に試すと、状況が好転する可能性があります。
【売れない土地を売却するための対策】
- 不動産会社を見直す
- 価格を見直す
- 売り出しのタイミングを考える
- 隣家へ買い増しを打診する
- 瑕疵がある場合には解消してから売りに出す
- 登録免許税を売主負担にするなど特典をつける
- 自治体の空き家バンクに登録する
- 不動産買取を依頼する
ひとつずつ見ていきましょう。
2-1.不動産会社を見直す
不動産会社には得意・不得意があるため、土地が売れない場合には不動産会社を見直すのが有効です。
不動産会社を選ぶ際には、以下に着目すると良いでしょう。
- 土地のエリアに詳しい不動産会社であるか
- 土地の売却に強い不動産会社であるか
- 広いネットワークを持つのか、地域密着型なのか
売れない土地の場合には、エリアや売却に詳しいことはもちろんですが、地域の顧客とのパイプがある不動産会社のほうが売却力を期待できるでしょう。
売れない土地の仲介依頼先を検討しているなら、一括査定がおすすめです。
一括査定は、複数の不動産会社にまとめて査定を申し込みできます。
不動産の取引相場を知ることができる上、査定額や売却プランを比較でき、信頼できる不動産会社に仲介を依頼できることがメリットです。
複数社に査定を依頼する際に便利なのが、NTTデータグループが運営する一括査定サイト「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」です。
「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」はカンタンな情報を入力するだけで、全国の優良な不動産会社2,100社のなかから、6社を選んでまとめて査定依頼ができます。ぜひ「不動産売却 HOME4U」で比較して、信頼できる最適な不動産会社を見つけてください。
2-2.価格を見直す
土地が売れない場合には、適切な値段設定になるように値下げする必要があります。
売り出してから時間が経つと、周辺の相場が変動する可能性があります。
周辺の相場をもう一度確認し、価格を設定し直すと購入希望者が現れるかもしれません。
ただし、極端に価格を低くしないように注意しましょう。
仲介を依頼している不動産会社に相談し、意見を聞きながら価格を調整していくのがおすすめです。
2-3.売り出しのタイミングを考える
不動産の取引は、活発になるタイミングとそうでないタイミングがあります。
一般的に取引の量が増えるのは、2~4月と9~11月です。
新生活に向けての引越しや企業の転勤の発令などがあるため、不動産の需要が増える傾向です。
この需要が高いタイミングで売却を行うと良いでしょう。
2-4.隣家へ買い増しを打診する
土地が売れない場合、隣家に買い増しを打診する方法もあります。
接道条件が悪い土地など、買い増しにより建築条件が緩和されるようなケースでは、交渉が上手くいく可能性があるでしょう。
また、近隣の店舗などに声をかけてみることも有効です。駐車場用地を探している場合もあるので、交渉価値があります。
2-5.瑕疵がある場合には解消してから売りに出す
瑕疵とは、簡単にいうと不具合や欠陥のある状態のことです。
例えば、土地の場合には、境界線がはっきりしていない、土壌汚染が生じている、地中埋設物があるといった瑕疵が考えられます。
瑕疵は、土地由来のもので所有者による解消が困難なものと、解消可能なものがあります。
土地の境界不明瞭などの解消できる瑕疵であれば、解消してから売り出すことで買い手が現れやすくなるでしょう。
2-6.登録免許税を売主負担にするなど特典をつける
売りにくい土地の場合は、買い手にお得感を感じてもらえるような特典を付けると、購入に踏み切る人が現れる可能性があります。
たとえば買主負担の登録免許税を売主負担にするといった方法です。
このような特典をつけると、売却の成功率は上がります。
2-7.自治体の空き家バンクに登録する
空き家バンクとは、空き家の所有者と居住を希望する人をマッチングする自治体主体のシステムです。
空き家バンクは、空き家の解消や周辺住民の生活を守ることを目的に非営利で運営されているため、居住希望者が安く借りたり購入できたりできます。
そのため、地域に住みたいと考える一部の購買意欲の強いユーザーにリーチできる可能性が高いです。
2-8.不動産買取を依頼する
不動産買取とは、不動産会社に直接不動産を買い取ってもらう取引です。
仲介による売却のように、買い手を探す必要はありません。
不動産会社に買取の条件で査定を依頼し、提示された金額や条件に合意できれば売買契約が成立するので、短期間で売却が可能です。
3.売れない土地をすぐに手放す方法

土地が売れないまま持ち続けていると、管理費や税金の負担がかかり続けるので、どうにかして早く手放したいとお考えの方もいるでしょう。
どうしても土地が売れない場合、売却以外の方法で手放すことも可能です。
【売れない土地をすぐに手放す方法】
- 不動産買取を依頼する
- 自治体に買い取ってもらう
- 自治体に寄付する
ひとつずつ見ていきましょう。
3-1.自治体に買い取ってもらう
自治体によって買い取り可能な土地もあります。
公有地拡大推進法により、自治体は街の整備を目的に道路や公園用地などの用地の取得が可能です。
そのため、自治体に土地の買取を希望する旨を申し出ると、場合によっては売却できる可能性があります。
3-2.自治体に寄付する
自治体による買い取りができない場合でも、相談すれば土地を引き取ってもらえるケースもあります。
ただし、自治体が使用できる土地であることが条件です。
寄付は無償のため、土地を手放してもお金は入りません。
しかし今後支払わなければならない固定資産税や、土地の手入れなどに必要な維持費が不要になることは、大きなメリットになります。
3-3.個人に贈与する
不要な土地は、個人に贈与することも可能です。
ただ、個人相手の場合には、無償での譲渡であっても、土地の評価額が110万円を超える場合は相手に贈与税が発生します。
思わぬ高額になってしまうこともあるので、注意してください。
また、贈与契約書の作成や、登記変更にかかる費用の負担者について取り決めることも必要になります。
この記事のポイントまとめ
土地が売れない場合は、以下の対策に取り組むと売れる可能性が高まります。
- 不動産会社を見直す
- 価格を見直す
- 売り出しのタイミングを考える
- 隣家へ買い増しを打診する
- 瑕疵がある場合には解消してから売りに出す
- 登録免許税を売主負担にするなど特典をつける
- 自治体の空き家バンクに登録する
- 不動産買取を依頼する
詳しくは「2.売れない土地を売却するための対策」をご覧ください。

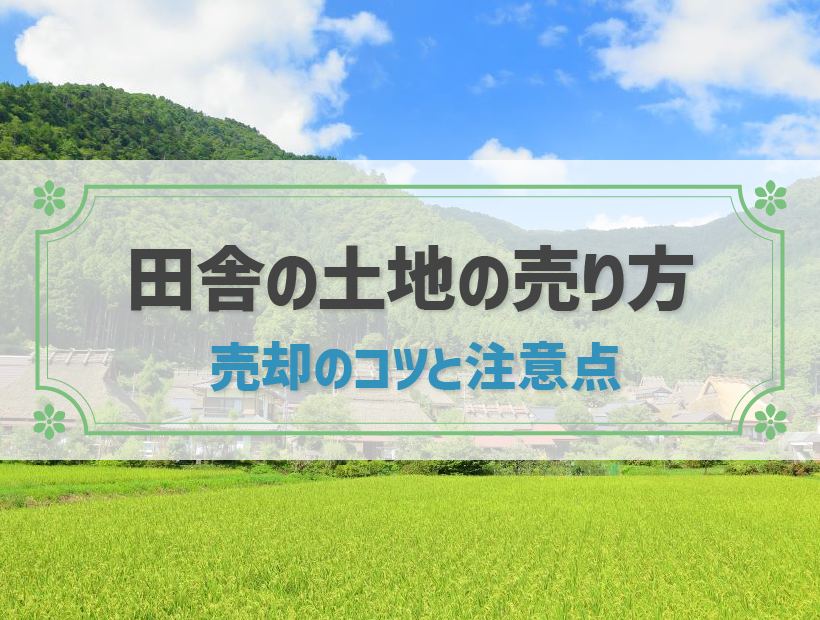



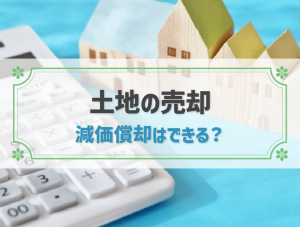







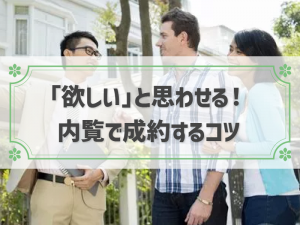

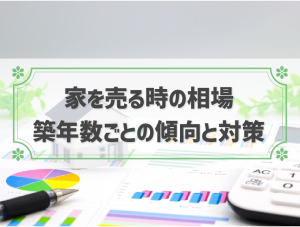
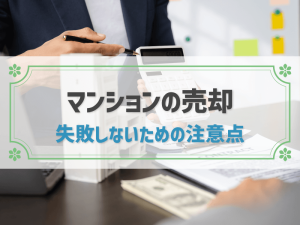



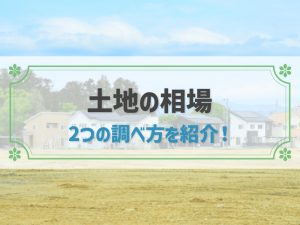
![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)
![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)